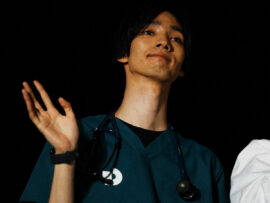世界有数の利用者数を誇る羽田空港。しかし、その広大な敷地の一部には、かつて「羽田三町(はねださんちょう)」と呼ばれる活気ある漁師町が存在していました。第二次世界大戦終結後、突如として住民に「48時間以内の退去」が命じられ、一夜にして消え去った幻の町。そこに暮らしていた人々が抱き続けた平和への願い、そして失われた故郷の記憶は、今なお羽田に息づく伝統的な夏祭りの中に色濃く残されています。本記事では、羽田空港の知られざる歴史と、地域住民がその記憶をどのように継承しているのか、その一端をご紹介します。
 羽田空港の一部に存在した漁師町「羽田三町」の強制退去の歴史を示す写真
羽田空港の一部に存在した漁師町「羽田三町」の強制退去の歴史を示す写真
羽田、強制退去の歴史

羽田に息づく伝統:賑わいと歴史を繋ぐ夏祭り
羽田の町が年間を通じて最も活気づくのは、羽田神社(はねだじんじゃ)の夏祭りです。この祭りは、失われた「羽田三町」の記憶と、現代の羽田を結びつける重要な役割を担っています。
羽田神社の由緒と信仰
羽田神社は、本羽田三丁目、多摩川(たまがわ)近くに鎮座し、その創建は約800年前の鎌倉(かまくら)時代に遡(さかのぼ)ると言われています。江戸(えど)時代には天然痘(てんねんとう)が流行した際、第13代将軍(しょうぐん)徳川家定(とくがわいえさだ)が病気平癒(へいゆ)を祈願(きがん)し、治癒(ちゆ)したという故事から、病気回復を願う多くの参拝者(さんぱいしゃ)が訪れます。
また、羽田神社の大きな特色の一つは、羽田空港(はねだくうこう)が氏子地域(うじこちいき)に含まれている点です。このため、古くから航空安全(こうくうあんぜん)を祈願(きがん)する神社として、航空関係者からも深く信仰(しんこう)されています。氏子とは、その土地を守る氏神(うじがみ)を信仰する人々のことです。
空港と地域が織りなす祭りの華
夏祭りでは、氏子にあたる羽田空港から、全日本空輸(ぜんにっぽんくうゆ)(ANA)や日本航空(にほんこうくう)(JAL)の客室乗務員(きゃくしつじょうむいん)を含む数十名の職員がボランティアとして参加します。神輿(みこし)パレードが行われる弁天橋(べんてんばし)通りの給水所などで飲み物や団扇(うちわ)を配り、祭りに華(はな)を添(そ)え、地域との絆を深めています。
祭りのメインイベントは、7月最終日曜日の午後に開催される神輿(みこし)パレードです。羽田の神輿は「ヨコタ」と呼ばれる独特の担(かつ)ぎ方をします。神輿を左右90度に大きく傾(かたむ)け、ローリングさせながら進むこの担ぎ方は、右の担ぎ手が跳(は)ね上がると左の担ぎ手がしゃがむという、まるで波に揺れる船を漕(こ)ぎ進めるような動きを見せます。これは、かつて漁師町であった羽田の歴史を彷彿(ほうふつ)とさせる、勇壮(ゆうそう)で力強いスタイルです。
弁天橋:記憶を繋ぐ神輿パレード
14基(き)の町会神輿(ちょうかいみこし)は、海老取川(えびとりがわ)に架(か)かる弁天橋(べんてんばし)を渡(わた)り、現在の空港島入口から出発します。そして、弁天橋通りを西に向かって練り歩きます。祭りの日、この弁天橋の欄干(らんかん)には、漁師町の名残(なごり)として幾(いく)つもの大漁旗(たいりょうばた)が海風にはためき、往時(おうじ)を偲(しの)ば)せます。
弁天橋は、あの「48時間強制退去」の日、今の空港島内にあった旧羽田三町(きゅうはねださんちょう)に住んでいた人々が、大急ぎで家財を運び出し、海老取川の西側へと移動するために渡った、まさにその橋なのです。
私もここ数年、毎年夏祭りの日に訪れ、空港島の端(はし)から14基の町神輿が順番に出発していく様子を見守ってきました。この場所にはかつて多くの住民が暮らし、それぞれの生活があったのだという思いを噛(か)みしめながら。
空を見上げれば、ピーク時には1分間に1.5機が離着陸(りちゃくりく)する航空機(こうくうき)の姿(すがた)が目に入ります。そのたび、私は機上の人たちに語りかけたい衝動(しょうどう)に駆(か)られます。
「ここは空港のためだけに埋(う)め立てて造られた土地ではないのです。わずか80年前まで町があり、3000人もの人々が住んでいたことを、どうか知ってください」と。
空の下には、夏の強い日差しを反射して輝く海が広がります。東京23区でありながら、どこかのどかな風景が広がり、潮(しお)の香(かお)りが鼻をくすぐるここ羽田は、今でもリゾート地(ち)の面影を残しています。
熱気と感動に包まれる羽田の夏
神輿の担ぎ手(かつぎて)たちが続々と集まり、羽田神社の神職(しんしょく)が神輿の道中(どうちゅう)の安全を祈り、お祓(はら)いを行うと、いよいよメインイベントのパレードが始まります。
14基の町神輿は、それぞれ弁天橋通りを練り歩き、要所(ようしょ)で立ち止まっては『東京音頭(とうきょうおんど)』などを歌い上げます。そして、神輿役員(みこしやくいん)の「それ、ヨコタでおいで、おいっちにのさん!」の掛け声と共に、威勢(いせい)よく神輿を左右上下にローリングさせる「ヨコタ担ぎ」が始まります。暑さと興奮(こうふん)で、担ぎ手はもちろん、見物客も汗だくになりながら一体となります。弁天橋通りは、夕方まで老若男女(ろうにゃくなんにょ)の熱気で埋め尽くされ、歓声(かんせい)と感動に包まれるのです。
結びに:記憶を繋ぐ祭りの力
羽田の夏祭りは、単なる伝統行事ではありません。それは、戦後わずか48時間で故郷を追われた人々の苦難、そして失われた「羽田三町」の記憶を、現代に生きる私たちに伝え、未来へと繋ぐための大切な架け橋です。この祭りの賑わいの中に、過去の歴史と平和への願いが息づいていることを知る時、羽田空港は単なる国際的な玄関口以上の、深い物語を持つ場所として私たちの心に刻まれるでしょう。
参考資料
- 『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)
- Yahoo!ニュース: https://news.yahoo.co.jp/articles/4051e86d31e2677c8af49f41bb7761d5f93a737e