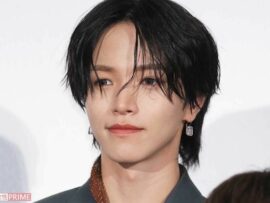近年、日本各地でクマの目撃情報や人身被害が増加し、特に山間部やその周辺地域での遭遇リスクが高まっています。予期せぬ遭遇は命に関わる事態に発展する可能性もあり、適切な知識と冷静な判断が求められます。本記事では、関東屈指の秘境・奥利根を拠点とし、40年以上のキャリアを持つクマ撃ち猟師、高柳盛芳さんの貴重な経験に基づいた、クマとの遭遇を避けるための秘訣と、万一遭遇してしまった際の最善の対処法を詳しくご紹介します。体重190キロもの巨大グマを仕留めたこともあるという高柳さんの言葉は、私たちにクマとの共存、そして生命を守るための重要なヒントを与えてくれるでしょう。
クマとの遭遇を避けるための基本的な心構え
クマの生息域に入る際は、常に警戒心を怠らないことが重要です。高柳さんは、遭遇しないための基本的なコツとして、クマに自分の存在を知らせることを挙げます。鈴やラジオなどで音を出しながら歩く、複数人で行動する、フンや足跡などの痕跡に注意を払うといった対策が有効です。しかし、どれほど注意していても、不運にも鉢合わせしてしまうケースはゼロではありません。万が一の事態に備え、適切な行動を事前に知っておくことが命を守る鍵となります。
クマと鉢合わせ!目をそらさずに距離を取る重要性
運悪くクマに出遭ってしまった場合、最も重要なのは「距離を取ること」だと高柳さんは強調します。ただし、その方法には具体的な注意点があります。絶対に目をそらさず、クマに背を向けてはいけません。クマは人間の目を恐れる性質があるため、目を合わせ続けることで相手に「自分は危険な存在ではないが、あなたを警戒している」というメッセージを送ることになります。
「クマは人間の目が怖いんだよ。それでも、やつらはじっと見てくるから、絶対に目をそらしちゃいけない。もちろんおっかねえけど、そらした瞬間、やつらはかかってくるよ!」と高柳さんは語ります。目をそらさずにいると、クマの方から視線を外し、退路を探して藪に消えていくことが多いとのことです。目を合わせながらゆっくりと後ずさりし、クマとの間に安全な距離を確保することが、最初の、そして最も肝心な一歩です。
威嚇するクマへの対応:体を大きく見せ、冷静に後ずさり
クマが距離を詰めてきたり、立ち上がって威嚇のポーズを取ったりすることもあります。これは「俺はこんなにでっけえんだぞ」という自己主張であり、必ずしも攻撃の意図があるわけではありません。このような状況では、さらに冷静な対応が求められます。
高柳さんのアドバイスは次の通りです。
「鉢合わせしてしまうと、クマは距離を詰めてぐわぁって立ち上がるよ。『俺はこんなにでっけえんだぞ』と威嚇してくるから、そのときは、カッパでもこうもり傘でもいいから広げ、ばさばさ頭の上で振り回す。そうして、後ずさりしながら距離を広げる。」
 山中で遭遇したクマが威嚇する様子
山中で遭遇したクマが威嚇する様子
体を大きく見せることで、クマに「自分は手ごわい相手だ」という印象を与え、攻撃対象から外させる効果が期待できます。クマが再び詰め寄ってきても、こちらが足を止めるとクマも止まることが多いそうです。その都度、体を大きく見せながら後ずさりを繰り返し、クマが諦めて去っていくのを待ちましょう。ここで最も避けるべきは、クマに対して攻撃を仕掛けることです。力でクマに適うはずがなく、かえって事態を悪化させるだけだと高柳さんは忠告します。
実際の遭遇事例から学ぶ教訓
残念ながら、最善の注意を払っていても、不意を突かれてクマに襲われる事例も存在します。高柳さんは、近所で起きた実際の事例を語ってくれました。「近所の人が釣りにいき、車に乗り込もうとしたところで何かを見たと思ったら、これがクマで、あっという間に、襲われたんだわ」。このような事例は、クマが突然現れる可能性があり、常に周囲への注意が必要であることを示唆しています。特に、クマの活動が活発になる時期や時間帯(早朝・夕暮れ時)は、一層の警戒が必要です。
まとめ:冷静な行動が生命を守る
クマとの遭遇は、誰もが避けたい状況ですが、万が一の事態に備えることは非常に重要です。ベテラン猟師の高柳盛芳さんの教訓から、以下の点が特に強調されます。
- クマの生息域では常に警戒し、音を出すなどして存在を知らせる。
- クマと遭遇したら、決して目をそらさず、背を向けずにゆっくり後ずさりして距離を取る。
- クマが威嚇しても、体を大きく見せ、冷静に対処し、攻撃は絶対にしない。
- 常に周囲に注意を払い、不意の遭遇に備える。
これらの知識と心構えを持つことで、クマとの不要な衝突を避け、安全に自然を楽しむことができるでしょう。
参考資料
- 『日本クマ事件簿』(三才ブックス)
- Yahoo!ニュース (https://news.yahoo.co.jp/articles/4fb69a630662b80b2c65efb93c71532014724e77)