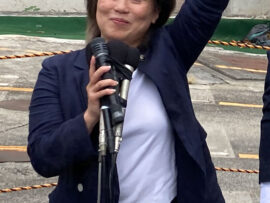ドングリ豊作の年でもクマが人里に現れる現象が近年多発。「山に餌が豊富なら里には下りてこない」という従来の考え方は、もはや通用しないのでしょうか。森林ジャーナリスト田中淳夫氏は、こうしたクマ出没の背景に食性と人間活動による新たな誘引があると指摘します。本記事では、クマが本当に求めているもの、そして現代における彼らの行動要因を、専門家の知見に基づき掘り下げていきます。
「山に餌があれば里には出ない」という誤解
クマの人里出没を防ぐため、山にドングリの木を植えたり、ドングリをばらまいたりする試みがありました。「山に木の実が十分あれば、クマはわざわざ人里に現れない」という思い込みが根底にあります。
しかし、近年のクマは農地の農作物被害、市街地の生ゴミ漁り、家畜や人間への襲撃も発生。ドングリ豊作の年でさえこれらの事例が相次ぎ、「山に餌があれば里には出ない」という単純な説明では不十分です。その複雑な食性と人里への誘引要因を理解することが、適切なクマ対策の第一歩となります。
クマの基本的な食性:9割は植物質と「飢える夏」
日本のヒグマとツキノワグマは雑食性動物で、若葉、花、木の実、イモ、地下茎など植物質餌が約9割を占めます。残り約1割はアリの卵、魚、シカ・イノシシの幼獣や死骸といった動物質餌です。
森の草木は手軽な餌資源ですが、6月から9月の夏季は若芽硬化、木の実未熟のため植物質餌が減少。この時期は、クマにとって意外な「餌不足に陥りやすい飢える季節」なのです。
 森で餌を探すツキノワグマ、人里出没の背景にある食性の変化
森で餌を探すツキノワグマ、人里出没の背景にある食性の変化
カロリー効率と人為的な誘引物
森林ジャーナリスト田中淳夫氏は、木の実など植物質餌はカロリーが低く腹持ちが悪いため、クマは高カロリーの餌を求めると指摘。人間が作り出す誘引が加わります。
人間が食べる匂いの強いもの(調理済み食品、残飯など)、品種改良された甘い農作物、さらには「土中に埋められた肉」(不法投棄された家畜の死骸など)といった高カロリーで魅力的な餌が人里近くに存在。
これらが、山で低カロリーの餌を探すより効率的な選択肢となり、クマを人里へと接近させています。ドングリ豊作の年でも、質の高い餌の誘惑が人里出没の行動要因として強く作用します。
ドングリ豊作でも人里出没するクマの行動は、従来の理解を超える現代の課題です。田中淳夫氏の分析が示す通り、クマは低カロリーな植物質餌だけでは満たされず、人間が作り出す高カロリーな匂いの強いもの、改良農作物、「土中に埋められた肉」といった新たな誘引物に強く引き寄せられています。
木の実を増やすだけでは根本解決になりません。クマの食性と行動要因を深く理解し、生ゴミ管理、農地防護、不法投棄防止といった多角的なクマ対策を講じることが、野生動物との共存には不可欠です。
出典: 森林ジャーナリスト 田中淳夫氏、および各種研究・観察事例 (PRESIDENT Onlineより)