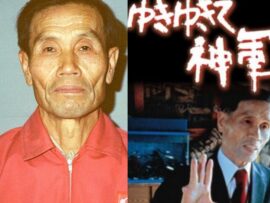外国人排斥を掲げる政治家が支持を集める昨今、彼らが主張する「日本」や「愛国心」の法的・憲法的根拠の欠如が指摘されています。本稿では、元外交官で作家の佐藤優氏が著書『愛国の罠』で提示する視点に基づき、現代における「愛国心」という概念を再整理し、より良い未来を築くための愛国心のあり方について考察します。
 現代社会における愛国心や国家、社会のあり方を思案する男性のイメージ
現代社会における愛国心や国家、社会のあり方を思案する男性のイメージ
自然な「愛着」としての愛国心と排外主義の乖離
人間は、自身が帰属する集団、例えば国や家族、社会に対して何らかの愛着を抱くものです。これは群れをなす生き物としての自然な感情であり、「愛国心」もまた、この「愛着」の表れと捉えられます。しかし、これまで私たちは「愛国心」という言葉を、ややもすればマイナスの側面から捉えがちでした。現代において、排外主義的な政治的言動が勢いを増す中で、この自然な感情としての愛国心と、特定のイデオロギーに結びついた「愛国心」との乖離を認識し、その概念を改めて整理し直すことが喫緊の課題となっています。未来志向の社会を築くためには、どのような「愛国心」を持つべきか、深く考える必要があります。
ゲルナーの「社会3段階発展説」で見る現代の国家と社会
「愛国心」を考察する上で、現代社会の構造を理解することは不可欠です。社会学者アーネスト・ゲルナーは、著書『民族とナショナリズム』において「社会の3段階発展説」を提唱しました。この理論は、社会を「狩猟採集社会」「農業社会」「産業社会」の三つに区分し、それぞれの段階における国家と社会の関係性を分析しています。
「狩猟採集社会」では、集団の規模が小さく、国家は存在しませんでした。「農業社会」になると、巨大な帝国が出現する一方で、国家の影響が及ばない自給自足の村落も併存しました。そして、現代の「産業社会」では、社会と国家が一体化するという特徴が見られます。
産業社会における「愛国心」の二つの側面
なぜ産業社会において社会と国家が一体化するのでしょうか。それは、社会が流動的になり、変化に適応できる労働者が不可欠となるためです。マニュアルを読みこなし、計算ができるといった汎用的な能力を持つ人材を育成しなければ、社会の維持・発展は望めません。このような大規模な教育を提供できるのは国家だけであり、結果として社会と国家は密接に結びつくことになります。
私たちが生きるこの社会と国家が一体化した産業社会では、「愛国心」も大きく二種類に分類できると佐藤氏は指摘します。一つは「社会に根差す愛国心」、もう一つは「国家に根差す愛国心」です。これら二つの愛国心は、それぞれにプラス面とマイナス面を持ち合わせており、その違いを理解することが、現代の複雑な排外主義やナショナリズムを読み解く鍵となります。
現代社会において、「愛国心」という言葉が多義的に用いられる中で、その本質と多様な側面を深く理解することは、健全な国民意識を育み、未来志向の社会を構築するために不可欠です。佐藤氏の分析は、自然な「愛着」としての感情と、政治的に利用される「愛国心」との間の境界線を明確にし、私たちに熟慮を促す重要な視点を提供しています。
参考文献
- 佐藤優『愛国の罠』ポプラ新書
- アーネスト・ゲルナー『民族とナショナリズム』 (邦訳版が存在する場合)