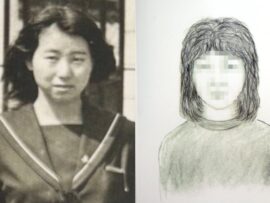公明党は高市政権発足に際し連立離脱をちらつかせ、自民党に揺さぶりをかける狙いでした。しかし、自民党が日本維新の会と連立を組んだことで状況は一変。公明党の立場は弱まり、斉藤鉄夫代表の発言力も低下。新内閣への予想外の高い支持率に、公明党は愕然とする事態に追い込まれています。
高市政権発足と公明党を驚かせた支持率
10月21日、高市早苗氏が内閣総理大臣に選出され、自民党・日本維新の会による高市内閣が発足しました。マスコミ各社の世論調査では新内閣の支持率は軒並み6〜7割と高水準を記録。特に公明党の連立離脱を「評価する」声が多く、日本経済新聞の調査では「よかった」が78%、「よくなかった」はわずか12%でした。自民党支持層はもちろん、公明党支持層でも約7割が「よかった」と回答。ジャーナリストの山田直樹氏は、創価学会関係者が高市内閣の高い支持率、特に若年層からの支持に驚愕していると指摘します。若年層の支持獲得に苦心する創価学会にとって、この結果は深刻な問題です。
 高市政権の発足を控え、自民党の高市早苗氏と公明党の斉藤鉄夫代表が会談する様子
高市政権の発足を控え、自民党の高市早苗氏と公明党の斉藤鉄夫代表が会談する様子
連立離脱は「揺さぶり」ではなかった:創価学会の決定
26年間自民党と連立を組み、「下駄の雪」とまで揶揄された公明党。今回の連立離脱が、単なる自民党への揺さぶりであり、最終的には連立復帰を懇願されると期待していたとの見方もありました。しかし山田氏はこれを否定。連立離脱は公明党の支持母体である創価学会の決定事項であり、公明党の斉藤鉄夫代表でさえ逆らえないと指摘します。この関係性は、公明党委員長を長年務めた竹入義勝氏(1926〜2023)の言葉からも明らかです。
竹入義勝氏が語る「公明党は創価学会に従属していた」
日中国交正常化に尽力した竹入氏は、政界引退後の1998年、朝日新聞のインタビューで公明党と創価学会の関係性を赤裸々に語りました。「私が仮に後継者を指名しても、そうならないのだから仕方ない。委員長を引き受けるときから人事権は学会にあると、明確にされていた。選挙にしても人事にしても、党内はみな学会を向いている。私の同調者になったら干されてしまう。/公明党は財政、組織の上で創価学会に従属していた。(中略)政治家になって学会との調整に八割以上のエネルギーをとられた。公明党・創価学会の関係は環状線で互いに結ばれているのではなく、一方的に発射される放射線関係でしかなかったように思う。」(朝日新聞:1998年9月17日朝刊より抜粋)この発言に対し、池田大作名誉会長(1928〜2023)が激怒し、創価学会が竹入氏への大規模な非難キャンペーンを行ったと山田氏は述べています。
「学会への従属」は今も:連立離脱の決定プロセス
竹入氏の証言から約30年経った今も、「学会に従属する公明党」という構図は変わっていないと山田氏は見ています。斉藤代表が党内投票で選出された代表ではない点も、その一端を示唆します。公明党の政権離脱は、高市氏が自民党総裁に選出された直後の10月4日には、すでに決定事項だったと推測されます。自民党総裁選は10月4日に実施され、高市氏は決選投票を制し党首に。その日のうちに高市総裁は斉藤代表と会談、さらに10月7日にも再び会談しましたが、「政治とカネ」の問題で隔たりが報じられ連立合意は持ち越しに。斉藤代表が連立離脱を正式表明したのは10月10日のことでした。
今回の連立離脱劇は、公明党が直面する厳しい現実を浮き彫りにしました。高市政権の高い支持率と、自民党が日本維新の会との新たな連携を模索したことで、公明党は政局における影響力の低下を痛感しているはずです。今後、その意思決定に深く関与する創価学会の存在が、公明党の政治的立ち位置にどのような影響を与えるのか、引き続き注視が必要です。
参考文献
- Yahoo!ニュース (デイリー新潮)
- 日本経済新聞
- 朝日新聞: 1998年9月17日朝刊
- 山田直樹氏著「創価学会とは何か」(新潮社)