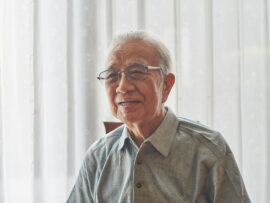1904年(明治37年)、北海道の豊かな自然が広がる下富良野村(現在の南富良野町幾寅)で、人里離れた静かな農村を突如として悲劇が襲いました。わずか11歳の少女が、空腹のヒグマに襲われ命を落とすという、心痛む事件が発生したのです。「下富良野少女ヒグマ襲撃事件」として歴史に刻まれたこの出来事は、人間と野生動物の共存の難しさを浮き彫りにし、現代にもその教訓を伝えています。
明治の悲劇:静かな農村を襲ったヒグマ
事件は1904年7月20日に起こりました。当時、大雪山や十勝岳といった深い山々に囲まれ、空知川をはじめとする清流が随所に流れる下富良野村は、手つかずの自然が色濃く残る地域でした。この日、幾寅に住む農家Aの11歳になる娘Bは、両親が早朝から自宅から約400メートル離れた畑で仕事をしている間、一人で留守番をしていました。
平穏な日常の中、その静寂は突如として破られます。一頭のヒグマが家の中に侵入し、Bをくわえて瞬く間に近くの林へと姿を消しました。事件発生時、周囲に目撃者はおらず、詳細な状況は不明のままでしたが、この予期せぬ遭遇が少女の命を奪うことになったのです。
 北海道の豊かな自然のイメージ。ヒグマが生息する森と清流が広がる。
北海道の豊かな自然のイメージ。ヒグマが生息する森と清流が広がる。
必死の捜索と残酷な発見
夕刻になり、畑仕事から帰宅したA夫婦は、いつもなら家にいるはずのBの姿が見えず、ただならぬ家の状況に気づきました。即座に近隣住民に助けを求め、Bの必死の捜索が開始されました。間もなく、家から約50メートル離れた場所で点々と続く血痕が発見されます。血痕をたどっていくと、さらに約50メートル先でイバラの小枝に引っかかった布切れが見つかりました。それはBの着物の一部であり、両親の不安は募るばかりでした。
捜索隊は範囲を広げ、少女を探し続けました。そして、着物が見つかったイバラの茂みからさらに約600メートル先の林の中の笹藪で、捜索隊は目を疑うような光景に直面します。発見されたBの遺体は、臀部と両足の肉のほとんどが食い尽くされ、周囲には内臓が飛び散り、全身には無数の爪痕が残されていました。それは見るに堪えない、あまりにも無残な姿でした。
「下富良野少女ヒグマ襲撃事件」が残した教訓
この悲劇の後、少女を襲ったヒグマの捜索が続けられましたが、ついに捕獲されることはありませんでした。当時の新聞『北海タイムス』でも報じられたこの「下富良野少女ヒグマ襲撃事件」は、北海道の歴史に深く刻まれ、人間社会と野生動物、特にヒグマとの間に横たわる厳しい現実を突きつけました。
この事件は、『日本クマ事件簿』(三才ブックス)でも取り上げられるなど、後世に語り継がれるべき教訓を私たちに与えています。北海道の雄大な自然は、私たちに多くの恵みをもたらす一方で、時にその厳しく危険な一面を見せます。この事件は、ヒグマと人間の共存がいかに難しいか、そして野生動物の生息域に踏み込むことのリスクを物語る歴史的な一例として、今日の私たちにもその重要性を問いかけています。自然との関わり方、そして地域住民の安全確保について、改めて深く考える機会となるでしょう。