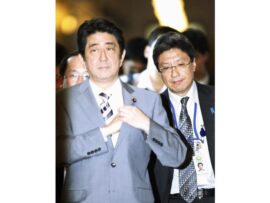ルポライターとして、日本のディープな社会の姿を伝え続けてきた國友公司氏。これまで『ルポ西成 七十八日間ドヤ街生活』や『ルポ歌舞伎町』などで大きな反響を呼んできた同氏が、新たに焦点を当てたのが「路上メシ」というテーマです。新刊『ルポ路上メシ』(双葉社)では、毎週炊き出しの列に並び、生活困窮者と共に食事をしながら取材を続けるという異色の手法で、路上の食の実態に迫ります。この記事では、同書には未収録の『週刊大衆』連載から、白鬚橋での炊き出し再開と、そこで提供されたコロッケ弁当を巡るエピソードを紹介します。
國友公司が追う「路上メシ」と炊き出しの現場
國友公司氏は、単なる傍観者ではなく、自らその現場に身を置くことでリアルな「経験」を読者に届けるルポライターです。彼の活動は、日本の社会の片隅で生きる人々の「専門知識」を深掘りし、「信頼性」のある情報を提供することで、E-E-A-T(経験、専門知識、権威性、信頼性)の原則を体現しています。今回のテーマ「路上メシ」においても、路上生活者や生活困窮者と共に毎週「炊き出し」の列に並び、食事を共にするという「経験」を通じて取材を行うことで、その「専門知識」と「権威性」を確立しています。
白鬚橋炊き出しの「復活」と現場の様子
日本三大ドヤ街の一つ、山谷からほど近い隅田川に架かる白鬚橋。その墨田区側では、毎週木曜日にNPO法人による炊き出しが行われていました。しかし、約半年間、隅田川沿いの防潮堤耐震補強工事の影響で、炊き出しは中断され、その移転先も不明な状態でした。國友氏は、上野公園での炊き出しに参加した際、偶然耳にした情報を頼りに再び白鬚橋を訪れます。
 炊き出しでいただいたコロッケ弁当と五目ごはんのアルファ化米
炊き出しでいただいたコロッケ弁当と五目ごはんのアルファ化米
すると、立ち入り禁止区画が縮小され、以前の場所で炊き出しが再開されているのを発見します。開始時刻の午後2時、すでに約60人が列をなしていました。この日のメニューは、小さなコロッケ弁当とアルファ化米。列の前の方に並んだ人々はコロッケ弁当を2つ受け取っていましたが、後ろの方の人々には1つしか提供されませんでした。
無料の弁当に漏れる不満と、その背景にある現実
「なんだよ、1個かよ。これじゃ、わざわざ来た意味がないよ」――列に並んでいた70代の男性が不満をあらわにしました。このような、無料の支援に対して不満を漏らす「立場のわきまえなさ」は、炊き出しの現場では珍しくない光景だと國友氏は語ります。しかし、NPOのスタッフは「ごめんなさい。でも、アルファ化米もありますから」と低姿勢で対応します。
](https://newsatcl-pctr.c.yimg.jp/t/amd-img/20251119-00813282-bookbang-001-1-view.jpg) 『ルポ路上メシ』國友公司[著](双葉社)
『ルポ路上メシ』國友公司[著](双葉社)
國友氏もコロッケ弁当とアルファ化米を一つずつ受け取り、隅田川を眺めながら食事をする40代の男性に話を聞きました。彼は作業服を着た日雇い労働者と思われ、その若さに國友氏は驚きを覚えます。男性からは、白鬚橋近辺での炊き出しが毎週木曜日に開催される他、毎週土曜日の午前11時にはカレーライスが、さらに第2・第4土曜日の午後1時には「何かしらのごはん」が配られるという詳細な情報も得られました。
路上メシから見えてくる社会の縮図
白鬚橋での炊き出しの再開と、そこで交わされた会話は、単なる食事の提供以上の意味を持ちます。それは、生活困窮者が直面する現実、支援する側の葛藤、そして地域における支え合いのネットワークの存在を浮き彫りにします。國友公司氏の『ルポ路上メシ』は、こうした「路上メシ」という日常の一コマを通じて、現代社会の縮図を描き出し、読者にとって「役に立つコンテンツ」となることでしょう。