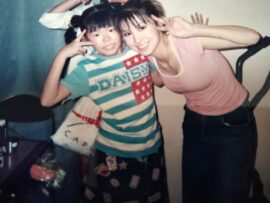日本列島でクマの出没報告が相次ぎ、その数は驚くべき水準に達しています。ノンフィクション作家で人喰い熊評論家の中山茂大氏は、約80年分の北海道の地元紙を分析し、ヒグマによる事件のデータベース化を行いました。その調査結果から、クマが自身を傷つけた人間を記憶し、「復讐」する事例が多数確認されたと警鐘を鳴らしています。クマの行動原理と、高まる人的被害の実態について深く掘り下げます。
日本各地でクマの出没が激増、人的被害は過去最悪に
11月に入っても、全国各地でクマの出没報告が止まらず、その頻度はかつてないほど高まっています。朝日新聞の報道によると、2024年度上半期におけるクマの出没件数は、すでに2023年度の年間総数(2万513件)を超過。さらに深刻なことに、人的被害も過去最悪を更新しています。11月5日時点で、ヒグマによる死者は2人、ツキノワグマによる死亡は11人に達しており、事態の深刻さが浮き彫りとなっています。
 秋の山林にクマが生息するイメージ
秋の山林にクマが生息するイメージ
特にツキノワグマの凶暴化が顕著:岩手県での連続襲撃事件
中でも、ツキノワグマの凶暴化は著しい傾向にあります。岩手県北上市では、立て続けに複数の悲劇的な事件が発生しました。7月4日には、住宅内で81歳の女性がクマに襲われ、その遺体が発見されています。その後、10月8日には、同市内の山林で男性がクマに襲われて死亡。さらに同月17日には、市内の温泉施設で清掃員の男性がクマに襲われ命を落としました。これらの事件はいずれも数キロ程度の範囲内で発生しており、クマの行動範囲から考えると極めて近い場所での連続発生と言えます。この地域では、特定の個体が何らかの理由で異常に凶暴化した可能性が指摘されています。
歴史的獣害事件から見るクマの習性
クマは一度覚えた味をしつこく求める習性があることが古くから知られています。日本史上最悪の獣害事件として語り継がれる大正4年の「苫前三毛別事件」では、ヒグマが女性や子供を含む7人を犠牲にしました。また、明治11年に札幌郊外で発生した「丘珠事件」では、男性ばかり4人がクマに襲われ命を落としています。これらの事件は、クマの持つ恐ろしい執念と学習能力を示唆しています。
人間を「記憶」し「復讐」するクマの行動原理
中山茂大氏の調査からは、クマが自身を傷つけた人間を明確に記憶し、意図的に「復讐」するかのような行動を取る事例が多数確認されています。中山氏が聞いた話では、以下のような事例があります。あるハンターが子グマを射殺した際、そばにいた親グマがこちらを凝視していました。その時は親グマを取り逃がしたものの、翌日、そのハンターが仲間と共に親グマを追跡していると、茂みの中から件の親グマが飛び出し、一列になって歩いていたハンターたちの中から、子グマを撃った当のハンターだけを狙って襲撃したというのです。これはクマの高い記憶力と、人間に対する特定の反応を示す驚くべき例と言えるでしょう。
まとめ:高まるクマの脅威と共存への課題
近年のクマ出没の増加と凶暴化、そして人間に対する「記憶」や「復讐」といった行動原理は、我々が認識している以上にクマが複雑な知性を持つことを示唆しています。人的被害が過去最悪を更新する中、クマとの共存は喫緊の課題であり、より深い理解と対策が求められます。山林に近い地域に住む人々は、これまで以上に警戒を怠らず、クマとの遭遇を避けるための知識と行動を身につけることが不可欠です。