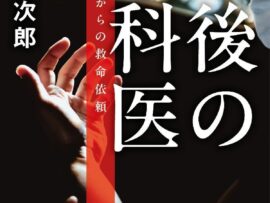中国の歴史上、特に衝撃的な出来事の一つとして知られるのが、1127年に起きた「靖康の変」です。この事件は、北宋王朝の滅亡を決定づけ、その都・開封が金国の軍勢に占領されただけでなく、上皇徽宗と皇帝欽宗、そして数千名に及ぶ皇后や皇族たちが捕らえられ、敵国へと拉致されるという前代未聞の悲劇をもたらしました。本稿では、この激動の時代に翻弄された皇族女性たちの過酷な運命に焦点を当て、歴史の裏側に隠された物語を紐解きます。
靖康の変勃発と皇族の悲劇的な拉致
1127年、金国軍は北宋の首都・開封を陥落させ、上皇徽宗、皇帝欽宗をはじめとする3000名を超える皇族を捕らえました。この「靖康の変」として知られる事件は、中国史上でも類を見ない大規模な拉致事件であり、当時の社会に大きな衝撃を与えました。中国文学者の加藤徹氏が著書『後宮 宋から清末まで』で詳細に論じ、漫画家の青木朋氏の歴史コミック『天上恋歌〜金の皇女と火の薬師〜』でもその前後の宮廷が描かれるなど、現在でも多くの関心を集めています。
徽宗は70人もの子女をもうけ、大規模な後宮を築いていましたが、これは王朝存続のための保険とも言えました。しかし、皮肉にも彼自身と欽宗の二帝、そして彼らの子孫の多くが金に連行されることとなります。
 北宋の皇帝、徽宗の肖像画
北宋の皇帝、徽宗の肖像画
この時、徽宗の九男である康王趙構(こうおう ちょうこう)だけが奇跡的に難を逃れましたが、彼の生母である韋氏(いし)、正妻である●(けい)氏、そして彼の娘たちもまた金へと連れ去られてしまいました。(※「けい」の漢字は开におおざと)
南宋の樹立と元祐皇后孟氏の奇跡の復権
金は当初、宋の領土に対する執着は薄く、傀儡国家「大楚」を樹立させた後、北へと撤収しました。大楚の皇帝には北宋の宰相・張邦昌(ちょうほうしょう)が就任しましたが、彼は愛国者であり、金軍撤収後すぐに帝位を返上します。そして、民間から元祐皇后孟氏(げんゆうこうごう もうし)を迎え、幼い皇帝の代わりに政治を行う垂簾聴政を依頼しました。
元祐皇后孟氏は、かつて哲宗の皇后でしたが廃位され、靖康の変の際には都を離れて実家で隠遁生活を送っていたため、難を逃れることができました。彼女は康王趙構を皇帝に指名し、趙構は即位して南宋の初代皇帝・高宗(こうそう)となります。孟氏は高宗の実母ではありませんでしたが、皇太后として尊ばれました。張邦昌は宋の復興に貢献したものの、金軍の下で一時的に帝位を僭称した罪を問われ、自殺を命じられます。もし靖康の変がなければ、孟氏がこのような形で歴史の表舞台にカムバックすることは決してなかったでしょう。
捕囚の旅路と皇族女性たちの過酷な運命
靖康の変において、高宗(当時の康王趙構)の母と妻子の多くも金軍に捕らえられました。徽宗の側妃であった高宗の生母・韋氏(後の顕仁皇后)、高宗の正妻・●秉懿(けいへいい・後の憲節皇后)、側室の田春羅(でんしゅんら)と姜酔媚(きょうすいび)、そして4歳から2歳までの5名の娘を含む、計9名の女性たちが金へと連行されたのです。(※「けい」の漢字は开におおざと)
金へと向かう北送の旅路は過酷を極めました。趙構の妻である●氏を含め、多くの妊娠中の皇室女性が落馬し、次々と流産してしまいます。趙構の5人の娘のうち、下の3人は道中で命を落としました。目的地である金国に到着してからも、これらの貴婦人たちは金の人々から言葉にできないほどの屈辱を受けました。特に、欽宗の美貌の皇后として知られる仁懷皇后朱氏(じんかいこうごう しゅし)は、その屈辱に耐えきれず、金国到着後に自ら命を絶ったと伝えられています。
このような歴史の悲劇の中で、後宮の女性たちはその美しさや地位ゆえに、最も過酷な運命を辿ることが少なくありませんでした。彼女たちの苦難は、単なる歴史の一幕ではなく、権力争いや戦乱がいかに個人の人生を無慈悲に引き裂くかを示す生々しい証言と言えるでしょう。