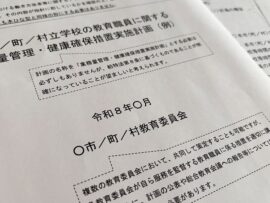OECD国際教員指導環境調査(TALIS)で示されるように、日本の小中学校の教員は世界一多忙な状況にあります。現在、各地の教育委員会はこの問題に取り組むため、学校の働き方改革に関わる計画策定に奔走していますが、「5年以上取り組んできたのに今さら変わるのか」という疑問の声も上がっています。特効薬がなく、財政や人手不足が厳しさを増す中で、計画なくして改革は難しく、予算確保も困難です。本記事では、働き方改革計画が形骸化せず、実効性を持つために必要な視点を探ります。
計画策定が目的化?「残念なケース」の背景
今回の動きの背景には、今年6月に改正された給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)があります。法改正を受け、9月には文部科学大臣が「業務量管理・健康確保措置に関する指針」を改訂しました。給特法とその指針に基づき、各教育委員会は業務量管理・健康確保措置実施計画を策定し、実施状況を公表することが法律上義務付けられています(改正給特法第8条)。文科省は来年4月の改正給特法施行に間に合わせるため、各教育委員会に今年度中の計画策定を呼びかけています。すでに策定していた自治体も、見直しを迫られている状況です。しかし、懸念されるのは、計画策定が目的化し、効果を伴わない事態です。
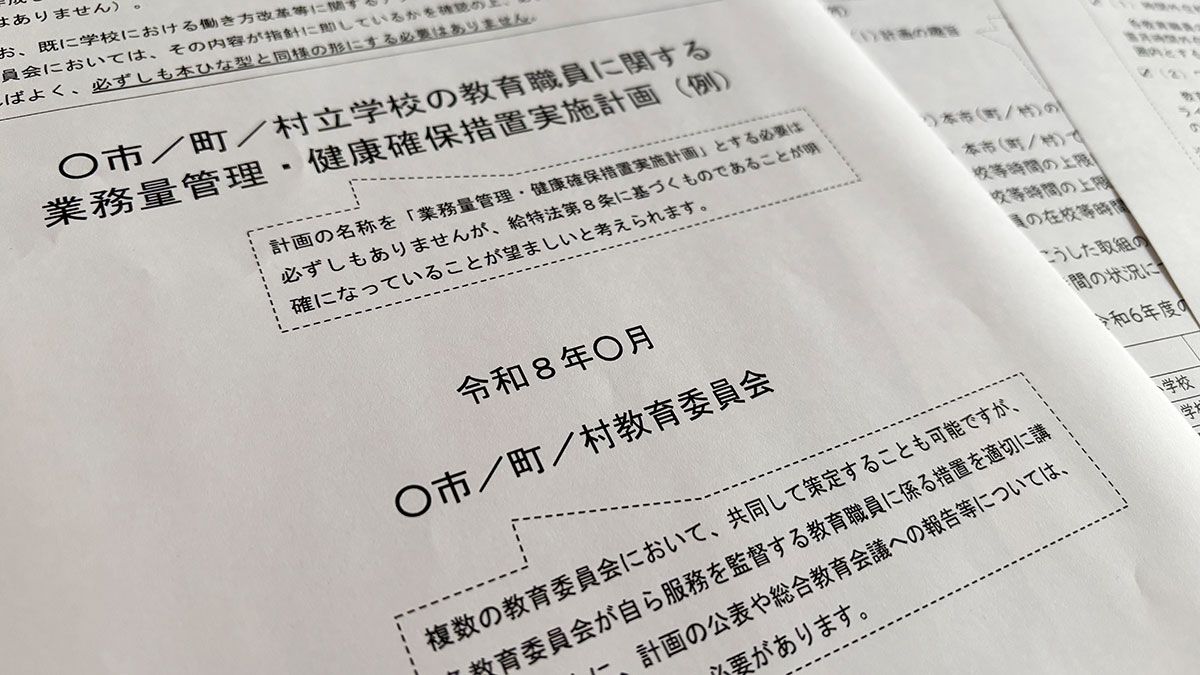 教員の働き方改革計画の進捗状況を議論する関係者
教員の働き方改革計画の進捗状況を議論する関係者
計画の実効性を阻む「残念なケース」
これまでにも以下のような「残念なケース」が数多く見受けられました。
- 教育委員会が学校任せ: 「計画を作りました、あとは学校次第です」と、教育委員会が学校任せで他責的になるケース。
- 学校の疲弊と変革意欲の欠如: 計画ができても、学校が忙しくて疲弊しており、変える気力がないケース。
- 残業の「見えない化」: 教育委員会や校長等から時短圧が高まることで、持ち帰り仕事が増えるなど、残業の「見えない化」が進むケース。
こうした事態では、何のための計画か、誰のための働き方改革か分からなくなります。文科省は指針や関連文書で詳細な留意点や参考ひな型を示していますが、「情報が多く、何に力点を置いたらよいか分からない。とりあえず都道府県や近隣の市区町村が作るのを待とう」と考える市区町村教育委員会も少なくありません。しかし、他地域の計画を安易にコピーしただけで、十分な内容と推進力となるかは疑問です。各自治体・学校の実情に応じた変更が必要であり、特に重要なポイントが4点あります。
結論
教員の働き方改革は、単に計画を策定するだけでなく、その実効性をどう担保するかが問われています。形式的な取り組みに終わらせず、教員が抱える多忙の根本原因を解決し、健全な教育環境を築くためには、教育委員会、学校、そして地域社会が一体となって、具体的な行動へと繋がる計画の運用が不可欠です。
参考文献