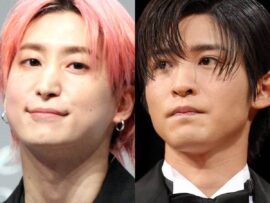過去に計画されながらも完成しなかった「未成線」は、鉄道ファンにとって想像力を掻き立てるロマンであり、「もし開通していれば」という思いを抱かせます。人口減少や財政難が課題となる現代日本において、新たな鉄道路線や既存路線の延伸計画は、時に大きな注目を集めます。本稿では、政治学者であり「鉄学者」としても知られる原武史氏の視点から、未成線が持つ歴史的背景と、現代における成功した新線、そして将来有望な延伸計画の可能性を探ります。
成功を収める新線の事例:宇都宮LRTの挑戦
鉄道は、バスと比較しても公共性が高く、利用者がルートをイメージしやすいという特性から、新線の開通はそれ自体が大きなニュースとなります。現代においても、経営的に成功を収めている新線は存在します。その代表例が、宇都宮市と隣接する芳賀町を結ぶLRT(ライトレール、次世代型路面電車)です。公共交通の新たな形として注目され、都市と郊外を結ぶ効率的な交通手段として地域住民の利便性向上に貢献しています。
 宇都宮市と隣の芳賀町を結ぶLRT
宇都宮市と隣の芳賀町を結ぶLRT
地域活性化を担う注目の延伸・新線計画
日本の各地では、地方創生や観光振興の観点から、新たな鉄道計画や延伸構想が進行しています。これらは単なる交通手段の拡充に留まらず、地域の可能性を切り拓く重要な役割を担っています。
ひたちなか海浜鉄道湊線:観光地アクセス改善への期待
茨城県ひたちなか市を走る「ひたちなか海浜鉄道湊線」の延伸計画は、その一つです。現在の終点である阿字ケ浦駅から、広大な敷地と四季折々の花々で多くの観光客を惹きつける国営ひたち海浜公園までの延伸が計画されており、すでに国への認可申請が行われました。特に花のシーズンには深刻な交通渋滞が発生するため、この延伸が実現すれば、JR常磐線勝田駅とひたち海浜公園が直結され、アクセス向上と渋滞緩和に大きく寄与すると期待されています。
福島臨海鉄道:貨物線からの旅客輸送再開構想
福島県いわき市のJR常磐線泉駅と漁港のある小名浜駅を結ぶ福島臨海鉄道も注目すべき事例です。かつては旅客輸送も行っていましたが、1972年以降は貨物専用線として利用されてきました。しかし現在、小名浜港に建設される新しいサッカースタジアムへのアクセス手段として、再び旅客輸送を行う構想が浮上しています。これは、既存の鉄路を再活用した新たな交通政策の一形態と言えるでしょう。
ひたちなか海浜鉄道と福島臨海鉄道の計画は、宇都宮LRTのような地方中核都市と郊外を結ぶ従来型とは異なり、同一市内における交通政策としての新線計画という点が特徴です。これらの成功は、これまでの鉄道の可能性を広げ、新たな地方交通モデルを提示するものと期待されています。
幻に終わった「九州横断鉄道」が示す可能性
一方で、計画されながらも実現しなかった路線には、今なお惜しまれるものがあります。原氏が特に残念だと感じるのは、熊本県の高森と宮崎県の高千穂を結ぶ「九州横断鉄道」構想です。この路線が開通していれば、熊本と宮崎県の延岡が一本の鉄路で結ばれるはずでした。
1973年に高森側と高千穂側の両方で工事が着工されましたが、高森側のトンネル掘削中に地下水脈に遭遇し、異常出水が発生。沿線地域が断水するという事態に至り、工事は中断・凍結されました。その後、高千穂側の高千穂鉄道は2008年までに廃止され、現在ではその一部区間を利用して「高千穂あまてらす鉄道」が観光用のカートを運行しています。
高千穂へのアクセスは、宮崎空港よりも熊本空港からの方が近いものの、バスの本数が少なく不便なため、タクシーを利用すると2万円を超える費用がかかります。もし九州横断鉄道が実現していれば、高千穂へのアクセスが格段に改善されただけでなく、阿蘇を含む県境を越えた広範な地域での観光開発が促進されたことでしょう。高千穂あまてらす鉄道がインバウンドを含む入場者数を年々増やしている現状を鑑みれば、熊本からの鉄道接続が実現していれば、さらに多くの人々を呼び込み、地域の発展に貢献できたはずだと惜しまれています。
結び
未成線に秘められた夢と、現代に息づく新線・延伸計画の取り組みは、日本の鉄道が持つ多面的な可能性を示しています。宇都宮LRTの成功や、ひたちなか海浜鉄道、福島臨海鉄道のような地域に根差した新たな交通政策は、地方の活性化に貢献するでしょう。また、九州横断鉄道のような「幻の路線」が残した教訓は、将来の鉄道計画において、地理的・経済的・社会的な課題を乗り越えるための重要な示唆を与えてくれます。日本における鉄道の未来は、過去の歴史に学びつつ、新たな価値を創造することで、地域社会に活力を与え続けることでしょう。