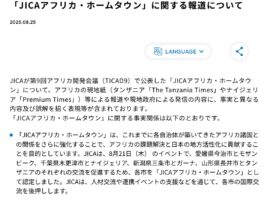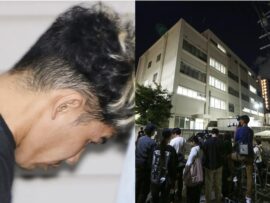小児がん治療に不可欠な基本薬剤が、相次いで出荷停止や供給不安に陥っている。この深刻な状況は、子どもたちの命に関わる重大な問題であり、日本の小児医療が直面している危機を浮き彫りにしている。「この国はどうして、子どもの生命を一番に守ろうとしてくれないのでしょう」——以前取材した小児がんの専門医は、その窮状をメールで訴えた。少子化が進む中で縮小傾向にある小児医療の中でも、小児がん分野は特に厳しい状況に置かれている。
影響が出ている主な薬剤
具体的な影響はすでに現場に出ている。2月には「再発神経芽腫」の基本的な薬剤である「ハイカムチン(R) 注射用 1.1 mg」(一般名:トポテカン塩酸塩)が出荷停止となった。さらに、3月には「横紋筋肉腫」の基本薬剤とされる「コスメゲン静注用0.5mg」(一般名:アクチノマイシン D)も供給不安に陥っている。国立成育医療研究センター・小児がんセンター長の松本公一氏は、これらの必須薬剤が使えなくなることの深刻さを指摘する。ハイカムチン(1.1mg、薬価6070円)は12月まで入手が難しい見込みであり、アクチノマイシンD(0.5mg、薬価4004円)に至っては、全く供給再開のメドが立たない状況だという。
 小児がん治療に使われる可能性のある医療機器のイメージ:深刻な薬剤不足の背景
小児がん治療に使われる可能性のある医療機器のイメージ:深刻な薬剤不足の背景
なぜ必須薬剤が不足するのか:専門家の指摘
松本氏は、こうした事態の背景に構造的な問題を挙げている。「最近、新しい薬がもてはやされる中で、ほとんど利ザヤのない昔からの良薬の供給が滞る事態になっています」。これは、薬価が非常に安く、製薬会社にとって利益が出にくい古い薬剤が、高額な新しい薬の開発・製造に比べて優先度が低くなりがちな現状を示唆している。参考として、2021年に国内承認された小児がん用抗がん剤のある新薬は、1瓶あたり136万5888円と、上記の基本薬剤とは価格が3桁も違う。市場原理が、必須でありながらも収益性の低い薬剤の安定供給を妨げている可能性がある。
小児がん治療薬を取り巻く構造的問題
このような薬剤不足の根底には、小児がんが置かれている特殊な状況がある。日本全体で年間約100万人が新たにがんに罹患する中、15歳以下の小児の罹患数はわずか2000〜2500人に過ぎない。しかも、小児がんはその種類が多岐にわたるため、一つ一つが人口10万人あたり6例未満の「希少がん」に該当する。このように圧倒的マイノリティである小児がんの治療薬開発は、多額の投資をしても回収が難しいと見なされがちだ。そのため、新規の小児がん治療薬の開発に手を出す製薬会社は少なく、海外で承認された画期的な薬剤が日本国内で使用可能になるまでの「ドラッグラグ」も長年の課題となってきた。
命に関わる影響と求められる対応
基本的な薬剤が使えなくなることは、治療方針の変更を余儀なくされたり、場合によっては有効な治療を受けられなくなったりすることを意味し、患者である子どもたちの命に直結する問題である。「治療できない患者さんは、それこそ命に関わるのですが、新薬にばかり社会の目が行って、こういう大切な薬が疎かになっているのが悲しいです」と松本氏は訴える。現在の薬剤不足は、単なる供給の一時的な滞りではなく、希少疾患に対する医薬品開発・供給体制や、古いながらも必須な薬剤の価値を社会全体でどう維持していくかという、日本の医療制度全体の課題を突きつけている。子どもたちの命を守るためには、収益性だけではない視点から、必要な医薬品の安定供給を確保するための仕組み作りが喫緊の課題となっている。