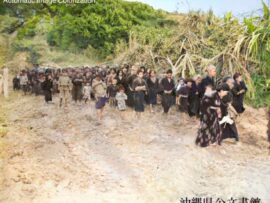カメラが鹿児島港を出港し、夜通し航海を続けた先にあったのは、今回の群発地震で最大震度6弱を観測した悪石島です。南北およそ160キロに及ぶ日本一縦長の村、鹿児島県・十島村。そのほぼ中央に位置する悪石島では、わずか2週間あまりで有感地震が1500回を超えました。しかし、今回取材班が真に向かっていたのは、震源分布図からは外れているように見える「宝島」でした。この宝島で、意外な事実が判明したのです。それは、島の位置が大きく移動していたという観測結果です。
宝島で確認された「移動」の観測データ
宝島に上陸した取材班が発見したのは、「電子基準点 国土地理院」と記された基準点でした。これは衛星と連携し、島の正確な位置を計測するものです。
 宝島の電子基準点。国土地理院が設置し、島の移動観測に使用される測量標識。
宝島の電子基準点。国土地理院が設置し、島の移動観測に使用される測量標識。
この電子基準点のデータから、宝島が先月21日から今月2日(水)までに東北東へ1.8cm、さらに翌3日(木)には南へ4.2cmも移動していたことが明らかになりました。島の位置が数センチ単位で変化するという、通常では考えにくい現象です。
専門家「海底付近に割れ目が開いたことを意味」
この宝島の移動について、東京大学地震研究所名誉教授の笠原順三氏は、「南の方に4cm動いたということは、海底付近に割れ目が開いたということを意味しているので、これは非常に重要なことではないか」と指摘します。「海底付近で割れ目が開いた」とは、一体どういうことなのでしょうか。笠原教授は、やはり地下からマグマがどんどん上がってきた現象があり、(海底の)割れ目に入ったら地震になったり、本当に海底で噴火になったりすると解説します。
今回の群発地震、特異なメカニズム
笠原教授は、この現象を理解するには、今回の群発地震の発生メカニズムを知る必要があると言います。通常私たちがよく知る地震のメカニズムは、「プレートA」により引き摺り込まれた「プレートB」がある限界を超え、跳ね上がることによって起こる、いわゆる「プレート境界型地震」と言われるものです。しかし、トカラ列島で頻発している今回の群発地震は、これとは全く異なるメカニズムで発生しているとのことです。
水とマグマ、地震発生への連鎖
その仕組みとは、フィリピン海プレートの上に乗った柔らかい堆積物が、海水を吸い込み、結晶構造の中に水を含んだままユーラシアプレートの下に沈み込むことです。この水分を含む層が地下深部で高温・高圧にさらされると、まるで陶器を焼くように水分が放出されます。笠原教授は、「ちょうど粘土を焼くと硬くなるのと同じように、だんだんその粘土が、陶器ができるような感じで水が抜ける。そうすると、そこの岩石の融点を下げてしまう」と説明します。これにより、今まで固体だった岩石がマグマ状に軟らかく溶け出すのです。つまり、ユーラシアプレートの下にある「固い岩石」に「不純物である水」が染みこむことで、「融点降下」という現象が起き、「固い岩石」が「マグマ状の液体」に変わります。そのマグマが、海底近くの亀裂に流れ込むことにより裂け目を広げ、その衝撃で地震が発生していると笠原氏は推測しています。
まとめ:宝島移動が示唆するもの
今回のトカラ列島における群発地震と宝島の移動は、プレート境界型地震とは異なる、マグマ活動に関連した特異なメカニズムで発生していることが専門家の見解から明らかになりました。地下から上昇したマグマが海底近くの亀裂に流れ込み、地震を誘発していると推測されます。特に宝島の南方向への移動は海底付近の新たな割れ目を示唆しており、今後の活動を注視する必要があります。