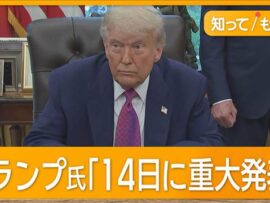日本の政治において「日本人ファースト」を掲げる参政党が公表した「新日本憲法」構想案が注目を集めている。主要メディアでの詳細な報道は少ないが、参院選での動向も踏まえ、その内容を知ることは重要だ。本稿では、この憲法案の主要な条項、特に皇位継承、教育、天皇の権限に関する提案を分析する。
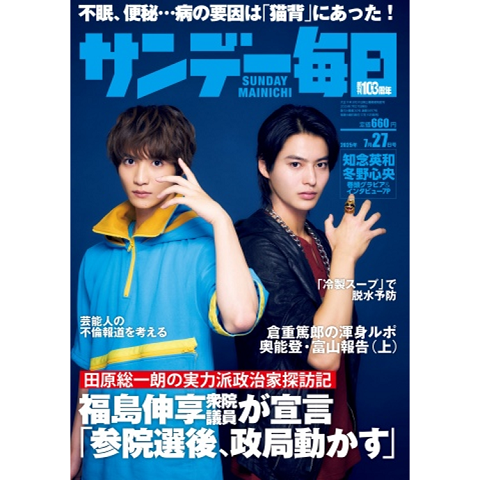 日本ニュース24時間 – 参政党の「新日本憲法」を特集する週刊誌表紙
日本ニュース24時間 – 参政党の「新日本憲法」を特集する週刊誌表紙
「男系男子」継承と皇室の存続
憲法案の第2条「皇位継承」では、「皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する」と明記し、男系継承を基本とする姿勢を示す。さらに、「皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない」とも規定。これは、皇統断絶の危機に際し、旧宮家からの養子縁組による皇籍復帰を念頭に置いている可能性が考えられる。あるいは、代表の神谷宗幣氏が過去に言及した、「天皇陛下に側室を持っていただき、多くの子をもうけていただく」という、近代的な夫婦観を破棄した皇統維持の方法も示唆しているのかもしれない(この発言を含む動画は現在削除されている)。規定の曖昧さが指摘される点だ。
国民の義務と教育のあり方
第9条「教育」では、古典素読、歴史と神話、修身、武道などを必修と定め、教育勅語を含む歴代の詔勅、愛国心、伝統行事が教育において尊重されるべきと規定する。「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」という教育勅語の一節(高橋源一郎氏の口語訳によれば「いったん戦争が起こったら、勇気を持ち、公のために奉仕すべき」といった意味合い)が尊重されることが明記されている点は重要だ。また、第5条「国民」が「子孫のために日本をまもる義務を負う」と定めることから、徴兵制を視野に入れたものとの解釈も可能だ。
国民主権に代わるものと天皇の役割
憲法案では、現行の国民主権と異なり、第4条「国」で主権を「国」に置く。暦と元号は天皇が定め、国歌は君が代、国旗は日章旗とし、公文書での元号使用を必須とするなど、象徴天皇制を超えた規定が並ぶ。第3条「天皇の権限」では、「天皇は、全国民のために、詔勅を発する」と定める。詔勅は国民に権利義務を生じさせないとされるが、戦前の例を見れば、詔勅が政策に大きな影響を与えうる可能性は否定できない。実際、沖縄選挙区の参政党候補、和田知久氏は討論会で、首相を天皇の「臣下」とし、「陛下が国民の安泰を願っているのだから、減税を打つべき」と述べた。これは露骨な天皇の政治利用と言える。憲法に「詔勅」を明記し、天皇の権威を党利党略に利用しようとする志向が、この憲法案から窺える。
参政党の「新日本憲法」案は、皇位継承における曖昧さ、教育への国家介入の強化、国民主権の否定、そして天皇の権威を政治利用する可能性など、現行憲法とは大きく異なる、様々な論点を提起している。これらの提案内容が、今後の日本の政治社会にどのような影響を与えるのか、その議論の行方が注目される。