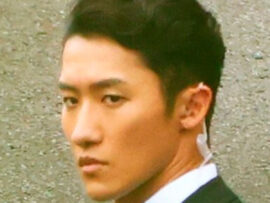駅前やショッピングモールでおなじみの菓子専門店「おかしのまちおか」。運営元である「株式会社みのや」は、創業71年目にして東京証券取引所スタンダード市場への上場を果たしました。近年、小売業界、特にスーパーマーケットでは激しい競争による寡占化が進む中、「おかしのまちおか」はなぜ菓子専門店というニッチなジャンルで目覚ましい成長を遂げ、「独り勝ち」の状態を築いているのでしょうか。その成功の背景にある独自のビジネスモデルと成長戦略を探ります。
 おかしのまちおかの店舗外観と店頭に並ぶ特売品
おかしのまちおかの店舗外観と店頭に並ぶ特売品
驚異的な成長と積極的な出店戦略
「おかしのまちおか」を運営する「みのや」は、ここ数年、右肩上がりの成長を続けています。直近の2024年6月期決算では、売上高225億円、営業利益9億6700万円を記録しました。これは、わずか3年前と比較して売上高が約3割増、利益に至っては驚異的な約5倍近くに拡大していることを意味します(開示されている経常利益で計算)。
この急成長を支えるのが、積極的な店舗展開です。2024年7月15日現在、全国で209店舗を展開しており、直近1年間だけで17店舗を新規開店しています。上場後には、さらに出店を加速させる方針であるとみられ、その勢いはとどまるところを知りません。多くの小売業が苦戦する中で、菓子小売専門店の業態でこれほどの多店舗展開と業績向上を達成している点は注目に値します。
「独り勝ち」を支える二つの戦略
おかしのまちおか」が菓子専門店という分野で「独り勝ち」を実現しているのには、緻密に練られた二つの戦略があります。現地視察と取締役への取材から、その具体的な理由が見えてきました。
顧客を惹きつける「スポット商品」と割引販売
「おかしのまちおか」の店舗に足を運ぶ客の目を引くのは、店頭に大々的に陳列された大幅な割引商品です。筆者が7月初頭に都内数店舗(荻窪店、阿佐ヶ谷駅前店、高円寺北口店など)を巡った際も、「コイケヤ ピュアポテト」が47%オフ、「東ハト 七夕キャラメルコーン」が40%オフなど、半額近い特売品がポップとともに並んでいました。
これらは「スポット商品」と呼ばれるもので、メーカーがスーパーやコンビニで販売しきれなかった旧規格品や期間限定品を、「みのや」が好条件で一括して大量に仕入れることに成功しています。これにより、破格の価格で商品を消費者に提供することが可能となり、通りがかりの顧客が思わず足を止め、お菓子を手に取る強力な動機となっています。また、近隣の食品スーパーやコンビニエンスストアでは見かけない珍しい商品が見つかるという「宝探し」のような楽しさも、リピーター獲得に貢献しています。この独自の仕入れ戦略が、他社との差別化を図る大きな要因です。
緻密に計算された店内レイアウトと顧客体験
20〜30坪程度の店内に入ると、壁の両面にはびっしりとお菓子が陳列されており、通路は人が2人すれ違うのがやっとというほど狭くなっています。これは、単に多くの商品を並べるためだけでなく、計算された「併売誘発」の戦略です。通路が狭く、商品が密集していることで、顧客は自然と多くの商品に目を向け、目的の商品以外にも手を取ってしまう傾向があります。
この狭い空間に多様な商品を効率的に陳列し、顧客の「買い回り」を促すことで、平均客単価は600円から650円前後を維持しています。安価な商品が多いため、一点あたりの利益率は低いかもしれませんが、高い顧客単価と併売による販売量の増加が、全体の利益を押し上げています。
まとめと今後の展望
「おかしのまちおか」の目覚ましい成長は、単なる安売り店ではありません。メーカーの過剰在庫や旧規格品を好条件で仕入れる「スポット商品」戦略、そして顧客の購買意欲と併売を巧みに促す店内レイアウトという、独自のビジネスモデルが確立されていることが「独り勝ち」の背景にあると言えるでしょう。
特に、問屋としての長年の経験とメーカーとの強固な信頼関係が、他社には真似できない仕入れ能力を可能にしています。消費者の「お得感」と「発見の楽しさ」を両立させながら、堅実に店舗網を拡大し、業績を伸ばし続ける「おかしのまちおか」。上場を機に、その成長戦略はさらに加速すると見られ、今後の菓子小売市場におけるその動向から目が離せません。