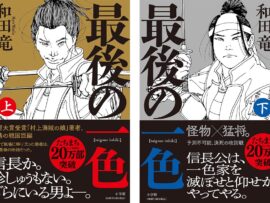戦後80年という節目を迎え、私たちは過去の歴史、とりわけ「あの戦争」とどのように向き合うべきでしょうか。日本がどこで「間違えた」のか、そもそも戦争はいつ始まったのか、そして掲げられた理想は本当にすべて誤りだったのか。これらの素朴な問いは、現代の私たちが歴史を深く理解し、未来へ活かす上で不可欠な視点です。本稿では、右でも左でもない客観的な視点から「あの戦争」の全体像に迫り、その呼称の背景にある政治的意図、そして戦争の起点に関する多様な見解、特に「15年戦争史観」の意義を掘り下げていきます。
呼称の裏に隠された真実:日中戦争と「特別軍事作戦」
歴史を正しく捉えるには、形式的な呼称ではなく、その実態を深く見極めることが重要です。この視点は、現代にも通じる普遍的な原則と言えるでしょう。例えば、ロシアは2022年2月にウクライナへ侵攻した際、この軍事行動を一貫して「特別軍事作戦」と称し、公式には戦争であることを認めていません。この呼称への固執は、ロシア国内の政治的・外交的状況が深く関わっていますが、だからといって国際社会がそれを「戦争ではない」と受け入れる必要はありません。実態を踏まえれば、それが大規模な武力衝突、すなわち戦争であることは明白であり、そう断言することになんの支障もないのです。
同様の構図は、かつての日本にも当てはまります。日本政府が1937年からの日中戦争を「支那事変」と呼称した背景には、当時の日本の外交的・政治的な意図が色濃く反映されていました。この呼称は、国際的な非難を避け、軍事行動の規模を限定的に見せかけるための戦略的なものでした。しかし、その名称に囚われ、本質を見誤ってはなりません。日中戦争は、双方合わせて数百万人以上もの兵士が動員され、広大な戦域で繰り広げられた、明らかに大規模な戦争でした。その実態を踏まえれば、これを「戦争」とみなすことは歴史的事実として極めて妥当であり、むしろ不可避であると言えるでしょう。
「あの戦争」の起点を探る:満洲事変から始まった連鎖
それでは、私たちが語る「あの戦争」は、本当に1937年7月7日に始まった日中戦争が起点なのでしょうか。この問いに対しては、もっと遡って考えるべきだという意見が昔から根強く存在します。その有力な候補こそが、1931年9月18日に起きた「満洲事変」です。
満洲事変は、奉天(現・瀋陽)郊外の柳条湖で日本の関東軍が引き起こした鉄道爆破事件に端を発します。関東軍はこれを中国側の仕業と主張し、自衛を名目に軍事行動を開始しました。その結果、現在の中国東北部に傀儡国家である満洲国が建国されるに至ります。満洲は、日露戦争後に日本が鉄道や付属地などをロシアから獲得した地域であり、当時日本領だった朝鮮半島と隣接し、ソ連との国境にも接する戦略的に極めて重要な拠点でした。加えて、石炭や鉄鉱石の豊富な供給源としても価値が高く、日本にとって軍事・経済の両面で不可欠な場所と考えられていました。
 満洲事変から日中戦争、大東亜戦争へと続く「15年戦争史観」を示す概念図。日本の歴史的転換点を示唆する。
満洲事変から日中戦争、大東亜戦争へと続く「15年戦争史観」を示す概念図。日本の歴史的転換点を示唆する。
日本軍は満洲国を確保した後も、中国との国境地帯にあたる華北を自国の影響下に置こうとする「華北分離工作」を推し進めました。これは、いわば第二、第三の満洲国を作り、満洲国を防衛しようとする試みでした。しかし、この強引な政策は中国側のナショナリズムを強く刺激し、日中間の緊張は急速に高まります。結果として、局地的な軍事衝突に留まることなく、日中戦争が全面戦争へと発展する遠因となったのです。
歴史の全体像を捉える「15年戦争史観」とは
こうした満洲事変から日中戦争への連続性を踏まえて、これら一連の出来事を「あの戦争」の起点と捉える歴史観を「15年戦争史観」と呼びます。実質的には14年に満たない期間ですが、足掛け15年と見なされます。この歴史観は、満洲事変(1931年)、日中戦争(1937年)、そして大東亜戦争(太平洋戦争、1941年)という3つの主要な出来事を、偶然の衝突ではなく、日本の一貫した大陸侵略計画のもとに必然的に結びついた連続した戦争と捉えます。
この視点は、単一の出来事としてではなく、長期的な視点から日本の行動とその結果を評価しようとするものです。そのため、歴史学界や一般社会においては、左派的な歴史観とされることが多い一方で、日本の歴史教科書や多くの一般書を通じて広く浸透している考え方でもあります。15年戦争史観は、一見複雑に見える日本の近代史における戦争の連鎖を、体系的に理解するための有効な枠組みを提供し、現代の私たちが多角的に歴史と向き合う上で重要な洞察を与えてくれます。
結論
「あの戦争」を多角的に理解することは、戦後80年を迎える現代において、私たち日本人に課せられた重要な課題です。呼称の裏にある政治的・外交的意図を読み解き、表面的な形式ではなく実態を見極めること。そして、単一の出来事としてではなく、満洲事変から日中戦争、さらに大東亜戦争へと続く一連の「15年戦争」として歴史の全体像を捉えることで、私たちはより深く、客観的に過去と向き合うことができるでしょう。このような歴史認識を深めることは、未来に向けた平和と国際協調を構築していく上で、不可欠な礎となります。
参考文献
- 辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』(講談社現代新書)