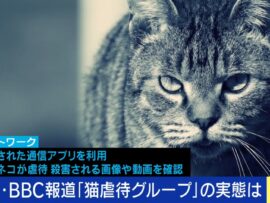2025年参議院選挙で目覚ましい躍進を遂げた参政党は、単なるネット選挙の成功事例に留まらない。この現象は、日本の政治と有権者間の関係性が構造的に変化していることを象徴している。特に注目すべきは、同党の戦略が、SNS時代におけるマーケティングの本質である「共感→参加→シェア」というプロセス設計に極めて忠実であった点だ。これは、現代の有権者の心理を巧みに捉え、政治参加の新たな形を提示したと言える。
SNS時代におけるマーケティングの本質は、商品やブランドを「売る」ことよりも、いかにファンを育成するかという「共創型の関係構築」に重きが置かれている。その核心にあるのが、以下の三段階のプロセス設計である。
 参政党・神谷代表の肖像。2025年参議院選挙における同党の躍進を象徴する写真。
参政党・神谷代表の肖像。2025年参議院選挙における同党の躍進を象徴する写真。
共感:価値観を「自分ごと化」させる
マーケティングにおける最初の、そして最も重要なステップは、感情的なつながり、すなわち「共感」を生み出すことだ。これはもはや商品の性能や価格だけでなく、「このブランド、なんかいいよね」と思わせるような、深い価値観への共鳴を指す。例えば、無印良品やパタゴニアのサステナブルな商品ストーリー、スターバックスのLGBTQ支援に見られる社会課題への姿勢、あるいはAppleのデザインやライフスタイルへの美的共鳴などが挙げられる。この段階では、まだ購入や具体的な行動には至らないかもしれないが、「なんとなく好き」という感情が芽生えることが、その後の関係構築への入口となる。
参加:当事者になってもらう
「良い」と思うだけで終わらせず、次のステップでは、有権者や消費者が「自分も関われる」という体験を設計することが重要となる。これは、商品のアンバサダープログラムへの登録、限定試供やクラウドファンディングへの参加、ワークショップやキャンペーンへの応募、Instagramでのブランドとのコラボ投稿、あるいはファンイベントへの参加といった具体的な行動を促す。このプロセスを通じて、単なる情報の受け手であった人々は、ブランドや政治活動の共創者の一部へと意識を変化させる。「買った人」から「関わる人」への意識変革こそが、この段階の核心である。
シェア:ファンが「語る存在」になる
一度深く関わった人々は、「自分が選び、関わったブランドや活動」を誇らしく語りたくなる心理を持つ。これは、商品の感想をSNSで投稿したり、ストーリーで開封動画を共有したり、ファンイベントで撮影した写真をシェアしたり、他者に積極的に推薦(いわゆる「推し活」)したりといった行動に現れる。ここで注目すべきは、企業や政党が直接広告を打つ必要がなく、生活者自身が自発的に宣伝主体となる点である。これは「ユーザーがマーケターになる」というSNS時代の理想形であり、信頼性、拡散性ともに最も強力なマーケティング手法と言える。
参政党の躍進は、この「共感→参加→シェア」というSNS時代のマーケティング原則を政治分野に応用し、見事に成功させた事例として、今後の政治運動やブランド戦略に多大な示唆を与えている。有権者との新たな関係性を構築し、彼らを単なる投票者から「語る存在」へと変容させるこの戦略は、現代社会における情報伝達とコミュニティ形成のあり方を再定義するものである。
参考文献
- PRESIDENT Online (2025年7月23日). 「参政党の躍進を「マーケティング」で読み解く」. Yahoo!ニュース 掲載記事.
https://news.yahoo.co.jp/articles/834a19236dab860dfad0e511943c108641d1d4f3