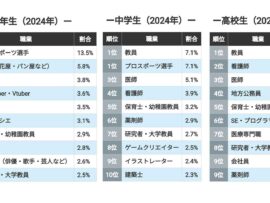日本の生活保護制度が、その本来の目的から逸脱し、高齢者世帯の主要な所得保障手段となっている現状が浮き彫りになっています。2024年度の生活保護申請件数は約26万件とこの12年間で最多を記録し、2025年3月時点で生活保護を受給する165万世帯のうち、半数以上にあたる91万世帯が高齢者世帯(うち単身高齢者世帯が85万世帯)を占めています。この高齢者層の急増は、制度の設計思想と運用の間に大きな乖離を生じさせており、日本の社会保障制度全体に疑問を投げかけています。
生活保護の本来の目的と「トランポリン型制度」の理念
生活に困窮する高齢者を生活保護で支えることは、一見すると当然のようにも思えます。生活保護法第1条には、憲法第25条に基づき「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」と明記されています。高齢者は現役世代に比べ生活困窮のリスクが高いため、生活保護の対象となるケースが多いのは自然な流れとも考えられます。
しかし、同条文にはその後に「その自立を助長することを目的とする」とも謳われています。「助長」とは「支援」を意味し、生活保護は本来、最低限の生活を維持できなくなった人々に対し、一時的な支援を通じてできるだけ早期に元の生活に戻ることを促す「トランポリン」のような制度であるべきだとされています。
高齢者世帯の増加がもたらす制度の歪み
この「トランポリン型」の理念と、今日の高齢者保護の現状との間に大きな隔たりがあります。そもそも高齢者層は、現役層と比較して「自立」が困難な場合が多いのが現実です。このような状況にもかかわらず、高齢者層が制度の主要な対象となっている現状は、制度本来の役割に無理が生じているのではないでしょうか。
実際、他の先進国では、高齢者層の所得保障は高齢者向けの別の制度で賄い、生活保護の対象からは外すケースも多く見られます。生活保護制度は、基本的には自立可能な現役層を支援の対象と暗黙のうちに想定している側面があるため、高齢者層への適用拡大は、制度の根幹を揺るがしかねません。
 日本の生活保護制度における高齢者世帯の経済的負担増加の現状
日本の生活保護制度における高齢者世帯の経済的負担増加の現状
日本の高齢者セーフティーネットと生活保護の現状
日本の高齢者を対象とする社会保障制度は、社会保険制度と社会扶助制度という二重のセーフティーネットによって構成されています。しかし、上層のネット、すなわち社会保険制度からこぼれ落ちてしまった高齢者世帯が2010年代に入って以降、大幅に増加しています。その結果、生活保護は制度本来の姿から乖離し、高齢者層の所得保障のための仕組みという色彩を強めてしまいました。
この問題はこれまで、大きな社会問題として意識されることが少なかったのが実情です。その主な理由は、生活保護の受給者数自体が、総人口から見ればかなり限定的であったためと考えられます。しかし、高齢化がさらに進む中で、この問題は今後ますます深刻化し、社会全体でその「負担」をどのように受け止めるべきか、根本的な問いを突きつけることになるでしょう。
結論
生活保護制度が「トランポリン型」から、実質的に高齢者層の終身的なセーフティーネットへと変貌している現状は、日本の社会保障システム全体が抱える構造的な課題を示唆しています。高齢者の生活を支えることは社会の責務である一方、その負担を生活保護制度が単独で担い続けることの是非、そして制度の持続可能性について、深い議論が求められています。高齢者の所得保障と自立支援のバランスをいかに取るか、社会全体の「セーフティーネット」のあり方が今、問われています。