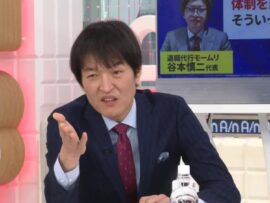人間は誰しも、悩みを打ち明けたい時もあれば、喜びを分かち合いたい時もあるものです。学校の教員も例外ではありません。この記事では、辛い経験への共感、心温まるエピソード、成功体験の共有など、学校現場の知られざる「リアル」をお届けします。今回、お話を伺ったのは、かつて国立大学附属小学校に勤務されていた篠原一美さん(仮名)です。彼女が「すさまじい荒れ具合だった」と語るほど、子どもたちは暴力的な言動を繰り返し、授業を成立させることすら困難だった当時の状況を振り返っていただきました。
授業が成立しない日々:暴言と破壊行為が横行する教室
篠原さんが国立大学附属小学校(以下、国立小)に着任して以来、毎日児童たちから投げつけられた言葉は「死ね」「うざい」「キモイ」「授業に来るな」といったものでした。特定のきっかけがあったわけではなく、初回の授業から私語が絶えず、指示に耳を傾けないどころか、屁理屈や揚げ足取りが飛び交うような状況だったといいます。
「通常であれば、強く注意すれば『まずい!先生が怒っている』という雰囲気が生まれ、多少は静まるものです。ところが、私が勤めていた国立小では、児童たちは静まるどころか、むしろ笑い声をあげてますます騒ぎ出すのです。何とか授業を始めようとしても、教材を床に投げつけて踏みつけたり、とにかく散らかし放題で片付けもしません。班活動をしようにも、すぐに子ども同士がいがみ合いを始めてしまうほどでした」

辛抱強く子どもたちと向き合おうとした篠原さんに対し、児童たちは冒頭で述べたような暴言を投げかけ始めました。「篠原」と呼び捨てにし、小馬鹿にするような挑発的な言動を繰り返す日々。この状況は、一部の児童や特定のクラスに限定されるものではなかったといいます。
教科によって豹変する児童の態度:実技教科の教員が見た現実
篠原さんは、いわゆる実技教科(音楽、図画工作、家庭、体育など)の教員であったため、多くのクラスで授業を担当しました。その経験から、多少の程度の差こそあれ、どのクラスも同様に荒れていたと証言します。彼女は「おそらく子どもたちは、実技教科の授業を狙って暴れていたのだと思います」と語ります。担任の先生や、受験で主要となる国語・算数・理科・社会といった教科の先生からは、「私語がやまない」といった話すら聞いたことがなかったからです。
篠原さんが勤めていた国立小では教科担任制が採用されており、教員は自身が担当しない授業で子どもたちがどのように振る舞っているかを知りません。子どもたちはこの点を察知し、教科や担当の先生によって態度を変えていたのではないか、と篠原さんは推測しています。この現象は、教育現場における教科担任制の課題を浮き彫りにする一例とも言えるでしょう。
教育実習生が証言する「学校現場の異変」
この国立小の教育現場の状況を目の当たりにしていたのが、教育実習生たちでした。多数の教育実習生を受け入れている国立小では、実習生がすべての教科の授業を体験します。
「私が話した実習生たちは、口をそろえて『教科によって子どもたちが豹変することに驚いた』と言っていました。私と同じように暴力的な言動を受け、『あんな状態では授業ができない』と涙を流す実習生もいましたね」実習生たちのこの言葉は、篠原さんの証言が単独のケースではないことを裏付けています。教育現場における児童の行動変容、特に国立大学附属小学校のような模範的な教育機関とされる場所で起きている「授業崩壊」の実態は、深く考えるべき社会的な課題と言えるでしょう。
国立大学附属小学校で教員が直面した授業崩壊は、単なる一教員の経験に留まらず、日本の教育現場全体が抱える潜在的な問題を示唆しています。児童の暴力的な言動、授業の不成立、そして教科による態度の豹変といった現象は、教育システム、教員の負担、そして子どもたちの心の状態に深く関連している可能性があります。このような「学校現場のリアル」に目を向け、真摯に向き合うことが、より良い教育環境を築くための第一歩となるでしょう。