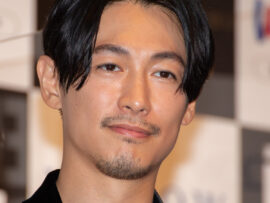第二次世界大戦終結から80年を迎えようとする中、多くの戦争の悲劇が語り継がれてきました。しかし、敗戦後に東南アジア各地で日本軍兵士たちが経験した「南方抑留」というもう一つの悲劇は、あまり広く知られていません。特にインドネシアのジャワ島では、戦時中に日本軍によって抑留されていたオランダ人が、立場を一転して日本人を抑留する側となり、復讐心から日本人に対し厳しい強制労働を課しました。
 ビルマの収容施設に抑留され、過酷な状況下にあった降伏日本軍人の姿。戦後の南方抑留における日本人の苦難を象徴する一枚。
ビルマの収容施設に抑留され、過酷な状況下にあった降伏日本軍人の姿。戦後の南方抑留における日本人の苦難を象徴する一枚。
林英一氏の著書『南方抑留:日本軍兵士、もう一つの悲劇』(新潮選書)は、日本軍人らの貴重な日記類を読み解き、この歴史的背景と過酷な実態を明らかにしています。同書では、ジャワ島で最も過酷と言われたタンジュン・プリオク港の作業隊に配属されていた陸軍主計中尉・大庭定男氏の日記を通して、当時の日本人兵士たちが置かれた状況が克明に再現されています。
ジャワ島抑留下で経験した屈辱と精神的苦痛
大庭氏の日記は、厳しい強制労働やオランダ人から受けた屈辱について多くを語りませんが、詳細に読み解けば、抑留中に敗者の悲哀を何度も味わっていたことが伝わってきます。例えば、オランダ船への石炭積み込み作業に従事した際、大庭氏は「我々が汗まみれ、埃まみれになって作業している時、この船に乗船しているオランダの子供は嬉々として戯れていた。兵隊の中には極度に反感の情を表すものがあった」(1946年6月18日)と記しています。これは、かつての占領者と被占領者の立場が逆転した状況での、精神的な苦痛を物語っています。
また、アムステルダムから寄港した豪華船のポーターを務めていた際には、「この船の監視に来ていたMP(憲兵)より我々は不愉快なる取扱を受けた。このような取扱いを受けるにつけ我々はこれがかって一年前まで我々の中の誰かがやっていたことの仕返しであると思うにつけ益々残念になるのである」(1946年6月23日)と述べています。これは、かつて日本軍が行ったことへの報復という認識が、日本人兵士たちの中にあったことを示しています。
こうした状況の中で、現地インドネシアの人々からも軽視される場面もありました。大庭氏は「インドネシアの苦力も最近においては我々を馬鹿にするようになってきた」(1946年11月5日)と記し、さらにポーター作業中に「何かしら威張りたい人達であり、気分的にも嫌になり、本当に重い荷物を背負って狭い船中をあちらにぶつかりこちらにぶつかって行く時にはつくずく人生の悲哀を感じた」(1947年1月14日)と、極限状態での精神的負担を吐露しています。
タンジュン・プリオク港の作業隊で発行されていた雑誌『たんじょん』第四号に掲載された絵河潤之介の漫画「君よ知るや南の国」には、甲板上で日光浴する水着姿のオランダ人女性の間を、トランクを担いで汗だくで歩く日本人の姿が描かれています。こうしたオランダ人との接触は、抑留された日本人にとって苦い思い出として深く刻まれることとなりました。
戦後史の記憶として
第二次世界大戦後の南方抑留は、日本が敗戦国として直面した厳しい現実の一つであり、特にインドネシア・ジャワ島での経験は、人道の観点からも深く省みられるべき歴史的事実です。大庭定男中尉の日記が示すように、強制労働だけでなく、心理的な屈辱や敗者の悲哀は、抑留された人々にとって計り知れない苦痛でした。これらの記憶は、戦後80年を迎える現代において、戦争の多面的な影響と、歴史から学び平和を希求する重要性を改めて教えてくれます。
参考文献
- 林英一 (著)『南方抑留:日本軍兵士、もう一つの悲劇』新潮選書