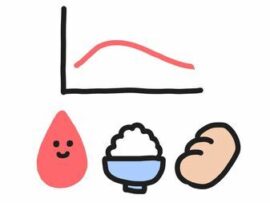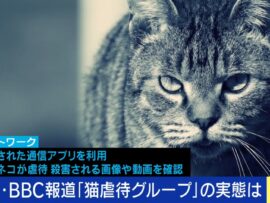マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」への移行が進む中、多くの国民健康保険(国保)加入者と後期高齢者医療制度の加入者が持つ従来の健康保険証は、2024年7月31日に有効期限を迎えました。厚生労働省は、この期限切れに伴う混乱を避けるため、国保加入者に対して2025年3月まで期限切れの保険証の使用を一時的に認めるなど、柔軟な対応策を講じつつ、マイナ保険証へのスムーズな切り替えを引き続き呼びかけています。
 「マイナ保険証」への移行に伴う旧健康保険証の有効期限を示すイメージ
「マイナ保険証」への移行に伴う旧健康保険証の有効期限を示すイメージ
旧健康保険証の有効期限と現状の普及率
今回、有効期限を迎えたのは、主に自営業者らが加入する国民健康保険の約7割にあたる約1,700万人分と、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入するすべての人、約1,900万人分の従来の健康保険証です。これらの保険証の新規発行は2023年12月に停止されています。
一方、大企業の会社員らが加入する健康保険組合や、中小企業が対象の全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険証は、2024年12月1日に有効期限を迎える予定です。
政府が推進するマイナ保険証の登録者数は、2024年6月末時点で8,484万人に達していますが、普及率は全体で約7割にとどまっています。特に国保加入者では65%、後期高齢者では70%と、依然として完全に普及しているとは言えない状況です。
「資格確認書」の交付と高齢者への暫定的運用
このような状況に対応するため、政府はマイナ保険証を所有していない人や、申請があった介護が必要な高齢者などの「要配慮者」に対し、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付しています。この資格確認書を医療機関で提示すれば、従来の健康保険証と同様に保険診療を受けることが可能です。
さらに、2024年4月には、75歳以上の後期高齢者を対象に、マイナ保険証の有無にかかわらず、全員に資格確認書を交付する「暫定的運用」として、2025年7月までの期間で配布を完了しました。これは、マイナンバーカードの管理に不安を訴える福祉施設などの声に応じたものです。
 医療機関で提示されるマイナンバーカードの見本
医療機関で提示されるマイナンバーカードの見本
国民健康保険加入者への特例措置
加えて、2024年6月には、国民健康保険の加入者を対象とした特別な措置が通知されました。これにより、期限切れとなった健康保険証、あるいはマイナ保険証の保有者向けに送付された「資格情報のお知らせ」という書類のみでも、2025年3月までは保険診療に利用できることになりました。この特例措置は、健康保険証の期限切れに気づかなかったり、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を混同して医療機関に持参したりする利用者に配慮したものです。
厚生労働省は、2024年12月に期限を迎える健保組合の加入者らに対しても同様の対応を取るかどうかは、現時点では決定していません。
マイナ保険証への移行促進とメリット
厚生労働省は、マイナ保険証への切り替えを一層促進したい考えです。マイナ保険証を利用することで、患者本人が同意すれば、医師が過去の受診歴や処方薬などの情報を確認できるようになります。これにより、医療の安全性が向上し、重複投薬の回避や適切な診療につながるなど、医療の効率化にも寄与する大きな利点があると訴えています。
まとめ
マイナ保険証への移行は、日本の医療DXにおける重要な一歩です。従来の健康保険証の有効期限切れに伴い、厚生労働省は「資格確認書」の交付や、国民健康保険加入者への一時的な特例措置など、段階的かつ柔軟な対応を進めています。これらの措置は、国民が安心して医療を受けられるようにするための配慮であり、今後の制度運用の透明性や利便性の向上が期待されます。国民一人ひとりが最新の情報を確認し、必要に応じて手続きを行うことが、円滑な移行の鍵となります。
Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/cbecfde472ac6893d20e0f39396f8fc2b1b48405