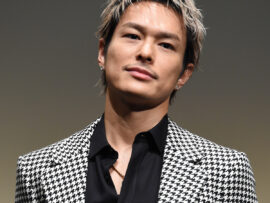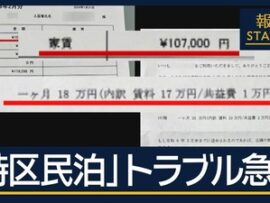参議院選挙で減税を否定し、農業補助金や現金給付を掲げて大敗を喫した自民党。税金は社会を支える基盤である一方、家計や企業の重い負担となるのは事実です。経済誌「プレジデント」の元編集長であり、作家の小倉健一氏は、「減税が経済に与える影響を再考すべき」と提言しています。政治家による口利き、パーティ券、バラマキ政策など、歳出拡大が止まらない日本の政治。なぜこの「増税の地獄ループ」から抜け出せないのでしょうか。本稿は、小倉健一、土井健太郎、キヌヨ氏共著の『図解 「減税のきほん」新しい日本のスタンダード』(ブックフォース刊)からの抜粋(一部編集)に、最新の動向を加筆したものです。
 日本の財政課題と増え続ける政府支出を示す硬貨の山
日本の財政課題と増え続ける政府支出を示す硬貨の山
政治家が「歳出拡大」の圧力に晒される理由
政治家は常に歳出拡大を求める強い要請にさらされています。地元支援者との会合では、地域経済の活性化を名目に公共事業の誘致や、福祉制度の拡充、特定の補助金の提供などが頻繁に要求されます。また、政治資金パーティの開催時には、パーティ券の購入者が具体的な支出要望を提示する場となることが多く、ロビイストとの会合では、特定の業界や団体の利益を守るための予算拡充が強く主張されます。
ほとんどの議員にとって、これらの支援者の要請を無視することは、次回の選挙での支持獲得に悪影響を及ぼす可能性があるため、非常に困難です。結果として、歳出拡大は支持を得るための有効な手段と認識され、議員自身の推進動機につながりがちです。
「減税」の声が届かない政治と有権者の不均衡
政治家の周囲で「ムダ遣いをやめろ」と強く求める声が非常に少ないのが現状です。パーティ券を購入しつつも補助金や口利きを一切要求せず、その上で減税を求める有権者は、残念ながら極めて稀であると言えるでしょう。多くの有権者は、減税や財政健全化の必要性には賛同するものの、個々の補助金削減や公共事業の見直しといった具体的な歳出削減策については、具体的な提案を行うことがほとんどありません。
このような状況は、歳出拡大を求める圧力が強く、議員が歳出削減を積極的に推進する動機が生まれにくい環境を形成しています。この政治家と有権者の間の不均衡が、議会全体の財政運営における構造的な問題を引き起こしており、これは世界中で共通して見られる政府の腐敗とも関連する現象です。
有識者会議が「歳出拡大」を助長する構造
さらに、政府の有識者会議や審議会においても、支出拡大を支持する意見が主導権を握る状況が多く見られます。例えば、農業補助金や地方創生事業など、特定の政策に関する議論の場では、その支出から恩恵を受ける関係者が中心となり、意見が交わされます。
発言者には、政策を所管する省庁の担当者や、補助金の恩恵を受ける地方自治体の代表、さらに政策を支える関連団体の代表が含まれるのが常です。一方で、政策の基本的な価値を疑問視する専門家や、歳出削減を求める意見を持つ関係者が招かれることはほとんどなく、客観的な評価や批判が行われにくい状況が続いています。これにより、有識者会議は、本来あるべき政策の客観的評価や批判を行う場ではなく、むしろ政府支出の正当性を補強し、さらなる拡大を推進する場と化しているのです。
参考文献
小倉健一, 土井健太郎, キヌヨ. 『図解 「減税のきほん」新しい日本のスタンダード』ブックフォース, 2024年.