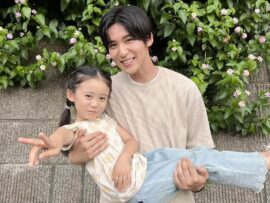2025年の首都圏中学入試は、「難関疲れ」と「英語入試元年」という二つの大きな特徴で注目されました。しかし、この史上最高水準の受験状況を支えているもう一つの重要な側面が、中堅・中位校の人気の高まりです。特に女子受験生の間で、どのような入試が多くの志願者を集めているのか、その実態を詳細に分析し、2026年の入試に向けた傾向と対策を考察します。
首都圏女子中学入試の多様化と「難関疲れ」の背景
首都圏の中学受験において、女子受験生は男子に比べて「難関疲れ」の傾向が顕著に見られます。2025年2月1日に偏差値60以上の難関・上位校を受験した女子の割合は25.2%で、男子の32.3%よりも低い数値を示しており、これは女子が背伸びせず、自身の学力や志望校に合わせた選択をする傾向があることを示唆しています。
中堅・中位校の人気を支える要因の一つとして、女子校の存在が挙げられます。男子の中堅・中位校が共学校中心であるのに対し、女子には伝統ある女子校が多く、多様な教育理念や環境が提供されています。また、近年は共学化への動きや新規開校も活発です。2026年に男女別学校から共学校に移行する学校としては、男子校の日本学園(明治大学付属世田谷)、女子校の鎌倉女子大学(鎌倉国際文理)、東京女子学院(英明フロンティア。25年高校に続き26年中学も共学化)が挙げられます。首都圏以外では、盛岡白百合学園(岩手・盛岡市)と園田学園(兵庫・尼崎市)が校名をそのままに男子募集を開始します。
さらに、中学校の新規開校も進んでおり、2026年には東京・大田区の羽田国際(蒲田女子から高校が校名変更・共学化)、さいたま市緑区の浦和学院、東京・府中市の明星Institution中等教育部などが開校予定です。順天が北里大学附属順天となり内部進学が始まることや、三田国際学園が三田国際科学学園に校名を変更することも、受験生にとっては新たな選択肢となります。
 2025年中学入試で人気を集める神奈川学園。女子受験生の中堅・中位校への関心の高まりを示す一例です。
2025年中学入試で人気を集める神奈川学園。女子受験生の中堅・中位校への関心の高まりを示す一例です。
地方校「東京会場入試」が牽引する女子受験生の動向
2023年から2025年にかけて、特に多くの女子受験者を集めたのが、東京会場で実施される地方校の「お試し受験」です。これらの入試は、首都圏の受験生にとって本命校の前に力試しができる機会として、また多様な選択肢を検討する上で重要な役割を果たしています。
人気の高い入試回をいくつか見てみましょう(いずれも女子受験者数で、学校名[入試名](25年の受験者数・実倍率)で示します)。
-
佐久長聖[東京]:長野県の学校ですが、1月13日[(1)](1384人・1.2倍)と14日[(2)](319人・1.2倍)の東京会場入試は女子にも人気です。特に13日の回は男子の9割に迫る受験者数で、偏差値は48と、受けやすいながらも一定の学力が求められます。23年から24年にかけて受験者数は微減傾向にあります。
-
盛岡白百合学園:2026年から共学化する岩手県の学校です。1月7日の[首都圏4教科](879人・1.2倍)と[首都圏1教科](195人・1.2倍)の入試区分があり、特に1教科型は受験者数を増やしています。偏差値はいずれも44と、比較的挑戦しやすい水準です。
-
宮崎日本大学[首都圏]:1月12日実施の入試は、2023年の1425人から大きく受験者数を伸ばし、2025年には1597人(2倍)に達しました。男子よりも女子の受験者数が多い点が特徴的で、偏差値は35とさらに門戸が広く、多くの受験生にとって魅力的な選択肢となっています。
-
早稲田佐賀[一般1月首都圏]:1月13日実施の入試は、男子の半分以下ではありますが、314人(1.4倍)の女子受験者を集めました。偏差値は男子の56よりも高い58で、中堅上位校以上の学力を持つ受験生に特に人気があります。
これらのデータは、受験生が自身の学力レベルや志望に合わせ、多様な学校の中から最適な選択肢を見出そうとしている現状を浮き彫りにしています。特に「お試し受験」は、本命校へのステップアップだけでなく、併願校として、あるいは全く異なる教育環境への関心から選ばれるケースも多いようです。
2026年入試に向けた展望と戦略的アプローチ
女子受験生の中堅・中位校人気の背景には、単に難関校を避けるだけでなく、より多様な教育環境や無理のない受験スケジュールを求める傾向が見られます。偏差値表に載る学校名だけでなく、各学校の教育方針、進学実績、クラブ活動、通学利便性など、多角的な視点から学校を選ぶ傾向が強まっていると言えるでしょう。
2026年入試に向けては、以下の点が注目されます。
- 共学化・新規開校校への関心: 新たに共学となる学校や開校する学校は、当初は比較的狙い目となる可能性があります。特に、共学化によって教育内容や雰囲気が刷新される場合、新たな魅力を求める受験生からの注目を集めるでしょう。
- 「お試し受験」の継続的な活用: 地方校の東京会場入試は、今後も重要な選択肢であり続けるでしょう。自身の立ち位置を確認する機会としてだけでなく、実戦経験を積む場として、戦略的に活用することが重要です。
- 多様な入試形式への対応: 英語入試の広がりなど、入試形式も多様化しています。単なる学力だけでなく、思考力や表現力を問う入試、特定科目に特化した入試など、自身の得意分野を活かせる形式を選ぶことも有効です。
総じて、女子の中学受験は、画一的な「難関志向」から、個々のニーズに合わせた「多様な選択」へとシフトしていると言えます。2026年入試に臨む受験生とその保護者は、最新の動向を把握し、柔軟な視点を持つことで、最適な進路を見つけることができるでしょう。
参考文献
- ダイヤモンド社教育情報
- 四谷大塚「合不合判定テスト」80%偏差値(2024年12月)
- Yahoo!ニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/34f29bd10a6975c025e30140d81d3e056eaa9078)