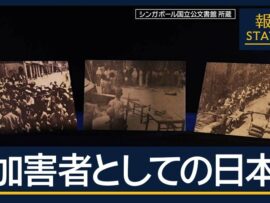1985年8月12日、羽田発伊丹行の日航機が御巣鷹山の尾根に墜落する未曽有の大事故から40年が経過します。当時の劣悪な通信環境下での現場特定は困難を極め、陸上自衛隊第1空挺団が到着したのは事故翌朝でした。生存者である12歳少女をヘリに吊り上げ救出した故・作間優一二曹の姿は、事故の象徴として今も語り継がれています。今回、その作間二曹の部下として少女の救出に携わった元自衛隊員が、40年という節目に初めて重い口を開きました。彼の証言から、過酷な救助活動の舞台裏と、その後のPTSDとの闘いが明らかになります。
 日航機墜落事故で12歳少女を救助する作間優一二曹(左)と、事故から40年を経て初めて取材に応じる元自衛隊員・相田氏(右)。救助活動の象徴的な光景と、その舞台裏を語る証言者の対比。
日航機墜落事故で12歳少女を救助する作間優一二曹(左)と、事故から40年を経て初めて取材に応じる元自衛隊員・相田氏(右)。救助活動の象徴的な光景と、その舞台裏を語る証言者の対比。
生存者を救出した自衛隊員の苦悩と沈黙
日航機墜落事故直後、当時の週刊誌には今では考えられないほど衝撃的な報道写真が数多く掲載されました。黒焦げの遺体、木に引っかかった腕、土中から突き出す足など、凄惨な現場の様子を伝える写真です。1985年8月30日号のある写真週刊誌には、墜落機体から12歳の少女を救出したばかりの元陸上自衛隊第1空挺団の相田さん(仮名、当時24歳、現在64歳)が呆然とした表情で写っていました。事故以降、相田さんは深刻なストレス障害と闘いながら生きてきました。これまでの40年間、彼はメディアからの「一切の取材を断ってきた」と語る彼が、40年という節目の年に「ようやく語る気になった」として独占取材に応じたのです。彼の深い沈黙の裏には、想像を絶する現場の光景と、それに起因する心の傷がありました。
精鋭部隊と畏敬された上官
陸上自衛隊第1空挺団は、日本唯一の落下傘部隊として、国家の最も困難な局面において迅速に任務を遂行する精鋭部隊です。相田さんが師事した作間優一二曹は、部下たちから「悪魔二曹」とあだ名され、恐れられながらも絶大な信頼と敬意を集めました。作間二曹は「まず自分を守れ」「つまらない怪我はするな」「基本をしっかりやれ」と相田さんを指導し、時には模擬銃で胸部や喉を突き合う現代武道である銃剣道で厳しくしごいたといいます。「作間二曹を嫌う人はいませんでした。『悪魔と同じ塹壕なら生き残れる』とまで言われるほど信頼が厚く、気前が良く面倒見のいい大先輩でした」と相田さんは振り返ります。彼の教えは、過酷な任務を生き抜くための礎となったのです。
出動命令:不確実性から行動へ
1985年8月12日、相田さんは19時近くの臨時ニュースで日航機が行方不明になった第一報を知ります。当初は「墜落するなら海か」と楽観視し、2日後の休暇を控えていたため出動はないと考えていました。しかし、テレビの速報で墜落現場が山梨、長野、群馬などの山間部と判明するにつれ、千葉県船橋市にある陸上自衛隊習志野駐屯地の空気はにわかに緊迫していきました。22時の消灯後も命令は出ていませんでしたが、予感を感じた相田さんは深夜に当直室へ。そこで防衛庁長官からの災害派遣命令が下り、ヘリからのリペリング(ロープでヘリから直接下降すること)救助が予測されていることを知ります。翌早朝4時過ぎ、命令受領ラッパが鳴り響き、相田さんは背のうに水筒や乾パンを詰め込み、作間二曹と同じ救助ヘリV-107の二番機に乗り込み、過酷な救助活動へと向かったのです。
結び
日航機墜落事故から40年。元自衛隊員・相田さんが語った証言は、過酷な救助活動の裏に隠された苦悩と、その後のPTSDという深い傷を浮き彫りにします。作間二曹との絆や緊迫した出動時の描写は、当時の状況の厳しさを再認識させます。この貴重な記録は、歴史的悲劇の裏側に存在した人間ドラマを後世に伝えるものでしょう。