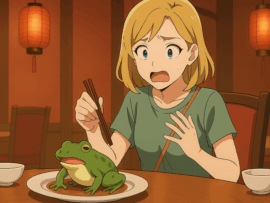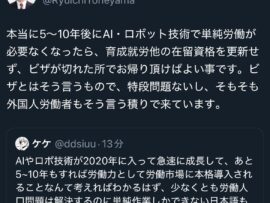太平洋戦争を命懸けで戦い抜いた零戦搭乗員たち。彼らは終戦後、英雄として迎えられるどころか、ときに社会の「手のひら返し」とも呼べる冷遇に直面し、過酷な運命に苦しめられました。本記事では、その一人である元零戦パイロットの進藤三郎氏が、敗戦後の日本社会、特に故郷広島で目の当たりにした現実と、家族との再会、そして悲報について、『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』(講談社)より一部を抜粋し、その胸中に迫ります。
焼け野原の広島で父と再会、そして家族の悲報
進藤三郎氏が広島へ帰郷した際、故郷の街は一面の焼け野原と化していました。生家は爆心地から約2.8キロという至近距離にありながら、奇跡的に類焼を免れ、爆風で大きな損傷を受けながらも、父・登三郎さんと母・タメさんが二人で無事暮らしていました。厳格な父が目に涙を浮かべ、「三郎、ご苦労さんじゃったなあ」と迎えてくれたその瞬間、進藤氏は初めて敗戦という現実と、これまで抑え込んできた悔しさを体中で実感しました。父子は抱き合い、長い間涙を流し続けました。
 戦後の進藤三郎氏:広島帰郷後の零戦パイロットの姿。厳しい戦後社会を生き抜いた彼の表情
戦後の進藤三郎氏:広島帰郷後の零戦パイロットの姿。厳しい戦後社会を生き抜いた彼の表情
家族の安否について、妻の和子さんと、1945年5月25日に生まれたばかりの長男・忠彦さんは、和子さんの母方の実家がある広島県北東部の庄原町に疎開していたため無事でした。しかし、白島にあった和子さんの実家が、経営する病院ごと原爆で焼け落ち、和子さんの姉・孝子さんが亡くなっていたという悲報を知らされます。さらに、進藤氏の次兄・次郎さんも陸軍上等兵として中国大陸で戦死していたことも判明。残る二人の弟は独立し、二人の妹もそれぞれ嫁いで広島を離れていました。その後しばらくの間、進藤氏は深い放心状態に陥り、原爆の爆風で荒れ果てた自宅の片付けをしたり、自宅から3キロほど南に位置する宇品海岸で釣りをしたりして日々を過ごしました。
戦後の日本社会において、国のために戦った元兵士たちが直面した厳しい現実、そして彼らが抱え続けた心の傷は計り知れません。進藤三郎氏の体験は、当時の社会が戦争の犠牲者たちにどのような形で向き合ったのか、そして個人がいかに過酷な運命に翻弄されたかを如実に物語っています。彼の物語は、決して忘れてはならない歴史の一部として、私たちに多くのことを教えてくれます。
参考文献
- 『零戦搭乗員と私の「戦後80年」』講談社
- Yahoo!ニュース / 文春オンライン 「どうせわかりっこない。カエルでも食わせてやれ」中国軍将官を日本語で罵倒→予想外の返答に絶句…元零戦パイロットがふり返る“衝撃の瞬間”