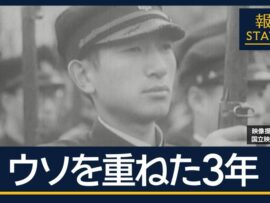都市部で電動キックボードの利用が急速に広まる中、深刻な社会問題としてその飲酒事故の増加が指摘されています。特に「特定小型原動機付自転車」として定義される電動キックボードにおける飲酒運転の割合は、他の車両と比較して著しく高く、その危険性が浮き彫りになっています。一般的に飲酒運転は厳禁という「常識」が、なぜこの新しい移動手段には浸透していないのでしょうか。本稿では、警察庁の最新データに基づき、この問題の背景と潜在的な危険性について深く掘り下げていきます。
 夜の繁華街で走行する電動キックボードLUUPの利用者。都市部の交通手段としての普及と、飲酒運転のリスクを想起させる光景。
夜の繁華街で走行する電動キックボードLUUPの利用者。都市部の交通手段としての普及と、飲酒運転のリスクを想起させる光景。
警察庁の衝撃発表:特定小型原付の飲酒事故率は他車両の数十倍
警察庁交通局が発表した「令和7年上半期における交通死亡事故の発生状況」は、電動キックボードの飲酒運転に関する驚くべき実態を明らかにしました。リリースによると、特定小型原動機付自転車(主に電動キックボード)による事故のうち、飲酒が関係する事故の構成比は約2割に達しています。これは、一般原付の約30倍、自転車の約22倍という突出した割合であり、専門家である自転車評論家の疋田智氏も「にわかに信じがたい」と指摘しています。
飲酒運転は自動車や自転車においても重大な犯罪行為であり、その危険性は広く認知され、社会全体で撲滅に向けた取り組みが進められてきました。しかし、電動キックボードに限ってはこの「飲酒運転厳禁」という常識が十分に浸透していない現状が、警察庁のデータによって浮き彫りになった形です。約5台に1台が飲酒運転によって引き起こされているという事実は、この新しい移動手段が抱える深刻な安全課題を示唆しています。
なぜ電動キックボードで飲酒運転が多発するのか?LUUPの利用実態と若年層の意識
特定小型原動機付自転車のほとんどは電動キックボードであり、その中でも首都圏や近畿圏で圧倒的多数を占めるのがシェアサービス「LUUP」です。街中で頻繁に見かけるその利用者の多くは、学生から若いサラリーマン世代が中心であり、警察庁の集計でも、事故を起こしたユーザーの7割以上が20〜30代の若い年齢層であることを裏付けています。
LUUPのポートは都内の繁華街を中心に多数設置されており、仕事終わりに居酒屋で仲間と過ごした後、ほろ酔い気分で終電に乗り遅れそうになった際などに、手軽な移動手段として電動キックボードを選択してしまうケースが容易に想像できます。「クルマじゃないから大丈夫だろう」といった安易な認識が、飲酒運転へと繋がりやすい背景にあると考えられます。この手軽さと、飲酒運転に対する意識の低さが、事故多発の一因となっていると言えるでしょう。
危険な「自爆事故」の実態と深刻な事例
電動キックボードによる事故は、特に段差などによる「自爆事故」が頻繁に発生しています。ホイール径が小さいため段差の乗り上げには不向きで、素面(しらふ)であっても転倒のリスクが高い乗り物です。繁華街で多く見かける電動キックボードのナンバープレートが歪んでいるのは、こうした転倒事故が日常的に発生している証拠とも言えます。
実際に、飲酒状態での段差乗り上げが原因で死亡事故も発生しています。例えば、東京都中央区勝どきでは、50代の会社役員が飲酒後に電動キックボードに乗って帰路につき、マンションの駐車場で車止めに衝突し転倒、頭部を強打して死亡するという痛ましい事故が起きています。この男性は事故から約8カ月後、道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で容疑者死亡のまま書類送検されました。このケースは自損事故であったものの、もし他者を巻き込んでいたらより甚大な被害が生じていた可能性も否めません。
飲酒運転の「常識」が浸透しない背景と今後の課題
自転車評論家の疋田智氏が指摘するように、電動キックボードにおける飲酒運転の「常識」がなぜ浸透していないのか、その背景には複数の要因が考えられます。一つは、特定小型原動機付自転車という新しいカテゴリーの乗り物であるため、その法規制や危険性に対する利用者の認識がまだ不足している点です。また、自転車のように手軽に乗れるイメージから、自動車や原付バイクと同じレベルでの飲酒運転に対する意識が希薄になりがちであることも指摘できます。
警察庁のデータが示すように、一般原付の30倍、自転車の22倍という飲酒事故率は、この問題が単なる一過性の現象ではないことを示しています。飲酒運転の予備軍がこれほど多く存在するということは、今後も同様の事故が起き続けることが避けられないという厳しい現実を突きつけています。
結論:電動キックボードの飲酒運転は社会全体で意識改革を
電動キックボードは都市の新しい移動手段として利便性を提供する一方で、その飲酒運転問題は看過できない喫緊の課題となっています。警察庁の衝撃的なデータは、この乗り物に対する「飲酒運転は厳禁」という常識の浸透が急務であることを明確に示しています。
利用者はもちろんのこと、シェアサービス提供事業者、行政、そして社会全体が連携し、電動キックボードの正しい利用方法、特に飲酒運転の危険性とその重大な法的責任について、より一層の啓発と意識改革を進める必要があります。手軽さの裏に潜むリスクを正しく理解し、安全な利用が徹底されること。それが、この新しいモビリティが社会に真に定着するための不可欠な条件となるでしょう。
参考文献
- 警察庁交通局「令和7年上半期における交通死亡事故の発生状況」
- PRESIDENT Online / Yahoo!ニュース (記事 gốc: 疋田智「電動キックボードの飲酒事故が「一般原付の30倍、自転車の22倍」という驚きの数値…なぜこの常識は浸透しないのか」2024年8月16日)