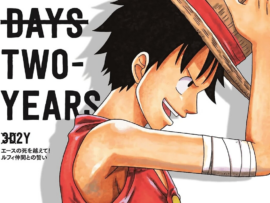7月、川崎市川崎区のライブハウス〈クラブチッタ〉に、熱狂的な若者たちが押し寄せた。彼らの視線を集めたのは、地元が生んだ新世代ラッパー、Candee(キャンディー)とDeech(ディーチ)だ。長らく「治安が悪い」というイメージがつきまとってきた川崎区で、数カ月前には痛ましい事件も発生した。そんな複雑な街で、彼らは今何を歌い、何を伝えようとしているのか。川崎の深層に迫るベストセラー『ルポ 川崎』の著者である磯部涼氏による独占インタビューから、その真髄を紐解く。
川崎が生んだヒップホップの新潮流
ヒップホップ/ラップミュージックシーンに名を馳せるCandeeとDeechは、現在最も注目されるアーティストの一角を占めている。彼らのキャリアにおける重要な節目となったのが、7月15日に川崎駅前の〈クラブチッタ〉で開催されたツーマンライブだ。キャパシティ1300人のこの会場は、1988年の開業以来、日本のヒップホップを支え、多くのラッパーにとっての登竜門として知られる。例えば、同じ川崎区出身の幼馴染で結成されたラップグループBAD HOPも、2016年の〈クラブチッタ〉でのフリーイベントを足掛かりに、2024年には東京ドームでの解散公演を成功させるまでに成長した。CandeeとDeechはBAD HOPの二つ下の学年にあたり、彼らもまた東京ドームのステージに立つなど、新世代の旗手として存在感を示している。
 川崎のクラブチッタに熱気あふれる観客が集結し、CandeeとDeechのライブを盛り上げている様子
川崎のクラブチッタに熱気あふれる観客が集結し、CandeeとDeechのライブを盛り上げている様子
この記念すべき地元での初の大規模イベントは、大成功のうちに幕を閉じた。チケットは完売し、開場前から〈クラブチッタ〉周辺には全国から集まった若者たちが溢れかえり、その熱気は近隣クラブ〈mamuC〉で行われたアフターパーティまで継続した。この日、CandeeとDeechが主催したイベントのタイトルは『WELCOME 2 SOUTHSIDE』。ここでいう「SOUTHSIDE」とは、彼らの地元である川崎市南部、特に川崎区を指している。
「ダークサイド」から生まれる独自の芸術表現
川崎区は、京浜工業地帯の中核を担い、駅前の繁華街では労働者をターゲットとした「飲む・打つ・買う」の業種が発展してきた歴史を持つ。また、仕事を求めて日本国内外から多様な人々が集まることで、多文化社会が形成されている。しかし同時に、公害問題や差別問題、少年の非行問題など、現代日本が抱える「ダークサイド」の象徴として見られる側面も持ち合わせてきた。
このような環境で育ったBAD HOP、そして続くCandeeとDeechは、荒廃した土地だからこそ新たな芸術が芽吹くことを世に知らしめた。彼らの表現は、地元川崎区を超えて、多くの若者たちから深い共感を集めている。特に『WELCOME 2 SOUTHSIDE』では、現代の若者が直面する過酷な現実をあえて強調せず、むしろ一瞬でもそれを忘れられるような、最高のダンスパーティとして演出された。Candeeの複雑な生い立ちを歌った名曲「在日ブルース」が選曲されなかったのは惜しまれたが、ライブ終盤に披露された「カサブタ」のパフォーマンスからは、彼らの強いメッセージが伝わってきた。

「晴れた空に 吹かしてる煙 金を稼ぎ 癒してる痛み 昔のことならもういい カサブタを剥がすように 忘れてない 傷だらけの日々 何もなかったかのように 過ぎ去る一日 昔のことならもういい カサブタを剥がすように」(Candee & ZOT on the WAVE「カサブタ」より)
この歌詞は、過去の「傷」よりも、それを乗り越えつつある現在の「カサブタ」を表現することの重要性を示唆している。しかし、それは過去の忘却を意味するのではなく、そっとカサブタを剥がすように、過去の傷と向き合うことの必要性を訴えかけているのだ。
音楽が紡ぐ川崎の未来
CandeeとDeechは、川崎という街の光と影を自らの音楽で表現し、多くの若者に希望と共感を与えている。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントに留まらず、社会的な課題が色濃く残る地元を肯定し、その中で生きる人々の感情を代弁する芸術としての役割を果たしている。過去の傷と向き合いながらも、前向きに現在を生きる彼らのメッセージは、日本のヒップホップシーンだけでなく、社会全体にも新たな視点を提供していると言えるだろう。
参考文献
- 集英社オンライン (2025年8月20日). 「CandeeとDeechが歌う「治安が悪い」川崎の「悲劇」と「カサブタ」」. Yahoo!ニュース. https://news.yahoo.co.jp/articles/f38f77656b5e91488f90886c2b2c7de3a0a72990