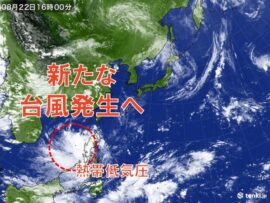「大学受験」は、日本の10代にとって人生を左右する大きな出来事の一つです。良い大学への進学が、希望する職業に就ける確率を高め、将来の「人生の選択肢」を広げる傾向にあるのが現状です。この影響力の大きさから、「自分らしい大学進学」を考えるための書籍『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売されました。本記事では、著者のびーやま氏への特別インタビューを通じ、「大卒の価値」と「学歴格差」の実態に迫ります。
 変わりゆく大学の価値を背景に、将来の選択肢を模索する学生
変わりゆく大学の価値を背景に、将来の選択肢を模索する学生
時代とともに変貌する「大卒」の価値観
Fラン大学であろうと名門大学であろうと、卒業すれば同じ「大卒」であるにもかかわらず、社会では「どの大学を出たか」で「学歴格差」が生まれているように感じられます。この問いに対し、びーやま氏は「たびたび議論になるテーマ」だと語ります。単に「大卒という価値は同じなのにどうして差がつくんだ!」という意見も理解できるとしつつ、大学名が「学歴」に含まれるようになった背景には、時代の大きな変化が関係していると指摘します。
エリートの時代から「大学全入」時代へ
かつて学生数が多かった時代、大学は真の「エリート」だけが進む場所でした。当時は、現在では誰でも入れるとされているような大学でさえ非常に「難関」で、大学に入ること自体に高い「価値」がありました。しかし時代は移り変わり、現在では「大学進学」を希望する者の数よりも、大学の「募集人数」の方が上回る「大学全入時代」を迎えています。選ばなければ「誰でも大学に入れる」状況になったことで、「大学卒業の価値」は「相対的」に低下しました。その結果、単に「大卒」であるだけでなく、「どこ大卒」であるかまで見られるのは避けられないことになったとびーやま氏は分析します。
びーやま氏によれば、昔は非常に高い「倍率」が存在し、入試も「一般入試」が主流であったため、大学入学は現在よりもはるかに高いハードルであったことは間違いありません。この「大学全入」という社会の変化が、現代の「学歴社会」における「大卒の価値」の多様化に繋がっていると言えるでしょう。
まとめ
今日の日本において、「大学受験」とその後の「学歴」が持つ意味合いは、時代とともに大きく変化しています。かつては大学入学自体が「優秀さ」の証でしたが、現代では「どこ大卒」であるかが重視される傾向にあります。この変化の背景には、「大学全入時代」という社会構造の変化があり、これからの「人生の選択肢」を考える上で、この現状を深く理解することが重要だと言えるでしょう。
参考文献
- びーやま 著『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』
- Yahoo!ニュース