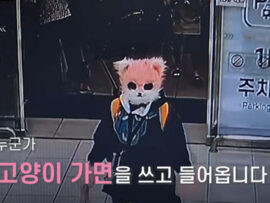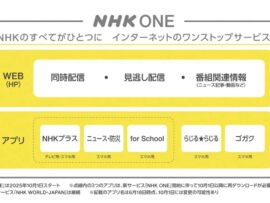スマートフォンは私たちの生活を限りなく便利にし、世界とのつながりを常にもたらします。しかし、この「常時接続」の世界で、私たちは心の平穏を保ち、本来人間にとって不可欠な「孤独」の時間をどのように守れば良いのでしょうか。デジタルデトックスという言葉が広がる一方で、スマホを手放すことが非現実的になった現代において、自己と向き合い、思考を深めるための孤独が失われつつある現状を、哲学的な視点から掘り下げます。本記事では、テクノロジーがもたらす効率化の裏側で、私たちから奪われている内省の機会と、その社会的・心理的影響について考察します。
効率化された生活がもたらす「ひとりの時間」の侵食
現代社会は、あらゆる面で効率化を追求し、私たちの体験を簡素化しています。2022年以降のポケモンゲームに実装された「おまかせバトル」による半自動的な経験値稼ぎ、テーマパークのファストパス、ECサイトの即日発送、家電のほったらかし機能、動画配信サービスの倍速機能や10秒スキップ、レコメンド機能、そして交通系ICカードによるスムーズな支払いなど、挙げればきりがありません。これらの時短や効率化の手法は、私たちの日常生活に深く浸透し、貴重な時間を節約しているように見えます。
 スマートフォンを操作する手が映し出され、現代の「常時接続」社会における孤独感と自己対話の喪失を示唆するイメージ
スマートフォンを操作する手が映し出され、現代の「常時接続」社会における孤独感と自己対話の喪失を示唆するイメージ
しかし、こうした消費環境の変化には、節約された時間を「有効に活用すべき資源」と捉えるという前提そのものに問題が潜んでいます。心理学者のシェリー・タークルは、「私たちが孤独の恩恵を受けようとしないのは、孤独になるために必要な時間を、活用すべき資源と考えるからだ」と指摘しています。実際に、私たちは浮いた時間を自己対話や内省に充てるのではなく、別のマルチタスクで埋めてしまいがちです。風景を眺めたり、ただ周囲の音に耳を傾けたりするような、心身を休める「ダウンタイム」は、スマートフォンを手にした瞬間から失われていきます。スマホを手に取るたびに、私たちは反射的に細切れのタスクを追いかけ、心を落ち着かせる間もなく情報に溺れてしまうのです。
SNSでの「ひとり時間」は真の孤独ではない
「マルチタスクではなく、SNSや動画に没頭している時こそ孤独を感じる」と反論する人もいるかもしれません。しかし、本記事で議論する「孤独」の概念は、複数の自分、つまり自己との対話をもたらす状態を指します。SNSや動画コンテンツに深く浸りきることは、この自己対話に必要な注意力を分散させ、真の孤独とはかけ離れたものになりかねません。
このような反論における「孤独」は、むしろ哲学者のハンナ・アーレントが言うところの「寂しさ」に近いと解釈できます。アーレントは、「一人であること」を「孤立」「孤独」「寂しさ」の3つに分類しました。「孤立」は何かを成し遂げるために他者に邪魔されずにいる状態、「孤独」は心静かに自分自身と対話するように「思考」している状態、そして「寂しさ」は、たとえ人に囲まれていても自分がたった一人だと感じ、他者に依存的に救いを求めてしまう状態です。SNSで膨大な情報に触れながらも虚無感に襲われるのは、まさに「寂しさ」の現れと言えるでしょう。
「SNSを通じて自分と向き合い、新たな自分を発見することがある」と主張する人もいるかもしれません。しかし、オンライン生活を通じて自己と向き合い、理解しようとする際、私たちは知らず知らずのうちに、その場に暗黙のうちに期待されている役割に合わせてしまう傾向があります。タークルが指摘するように、人間は他人の目にさらされると、無意識のうちに他人が期待する自己へと調整してしまうものです。
ここに、いつでも私たちと共にあるメディアとしてのスマートフォンが加わると、事態はさらに複雑になります。ちょっとした出来事も気軽にシェアし、「いいね」し合える環境では、私たちはいつでも、どこでも、誰といても、常に膨大な他者の視線に自分をさらし続けることになります。これにより、静かに自分自身と対峙し、内省を深める貴重な機会を逃してしまう可能性があるのです。
「自分らしさ」さえもSNSに求める現代のパラドックス
自己と対話するために、流れてくる言葉や写真に目を留め「いいね」をする。自己と対話するために、自分の言葉や姿を不特定多数に公開する。自己対話の機会でさえソーシャルな環境の中に見出そうとするとき、私たちは多くの大切なものを失っていくとタークルは警鐘を鳴らしました。現代社会において、テクノロジーは確かに効率と利便性をもたらしましたが、その代償として、本来人間が持つべき自己と向き合う時間、すなわち真の「孤独」を奪い去っているのかもしれません。このパラドックスは、デジタル時代の「心の健康」や「自己肯定感」といった現代人が直面する課題と深く結びついています。
結論
スマートフォンの普及と生活のあらゆる側面の効率化は、計り知れない恩恵をもたらす一方で、私たちから「孤独」の時間を奪い、自己対話の機会を減少させています。多くの人がSNS上で「ひとり時間」を過ごしていると感じるかもしれませんが、それは哲学的意味での内省的な「孤独」とは異なり、むしろ「寂しさ」に通じる状態である可能性が高いのです。常に他者の視線にさらされ、無意識のうちに自分を調整してしまう現代において、真の「自己」を見失わないためにも、意識的にメディアとの距離を置き、意図的に「ダウンタイム」を確保し、「内省」の時間を創出することが不可欠です。この「常時接続の世界」で心の平穏と深い自己理解を育むためには、テクノロジーとの健全な関係性を再構築し、失われた孤独を取り戻すための意識的な努力が求められています。
参考資料
- 谷川嘉浩 (2022). 『スマホ時代の哲学「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険【増補改訂版】』ディスカヴァー・トゥエンティワン.
- シェリー・タークル (Sherry Turkle), 『Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other』 (邦訳: 『セカンド・チェンジ:インターネットは私たちをどう変えるのか』、早川書房)
- ハンナ・アーレント (Hannah Arendt), 『人間の条件』 (邦訳: 『人間の条件』、ちくま学芸文庫)