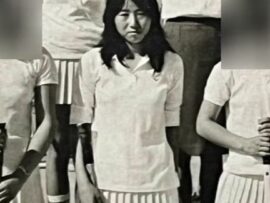インターネットやSNSが社会の隅々まで浸透した現代において、「ルフィ事件」に代表される匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)による詐欺や窃盗が猛威を振るっています。かつてのような牧歌的な時代は遠い過去となり、わずかな“隙”をも見逃さない犯罪者が常に身近に潜む危険性が増しています。このような状況下で、私たち自身や大切な人々を犯罪から守るためには、どのような対策を講じるべきなのでしょうか。本稿では、犯罪学の権威が提唱する「犯罪機会論」に基づき、令和時代に即した最新の防犯術と、日本に深く根付く従来の犯罪観との違いを詳細に解説します。
日本人の「犯罪原因論」信仰とその限界
日本では古くから、ドラマや映画などのフィクション作品を通して、犯罪の「動機」に深く共感する文化が根付いています。「なぜ犯行に及んだのか」「そこには確固たる動機や特有の原因があるはずだ」といった犯罪原因を追求する物語は、多くの日本人の心を掴んできました。このような犯罪観は「犯罪原因論」と呼ばれ、犯罪者の生い立ちや心理的背景、社会経済的要因などを深く掘り下げ、その原因を解明することで犯罪を理解しようとします。
しかし、世界の犯罪学の潮流は、この「犯罪原因論」とは一線を画しています。残念ながら、いくら犯罪原因論を突き詰めても、実際の犯罪抑止や効果的な防犯対策には直結しないという現実があります。なぜなら、たとえ同じような境遇やトラウマを抱えていても、犯罪に走る人もいれば、そうでない人もいるからです。犯罪の原因を探求すること自体が無意味とは言いませんが、そのアプローチだけでは、現代社会で増加する多様な犯罪、特に機会を狙うタイプの犯罪に対しては、十分な抑止力とはなり得ないのです。
令和の防犯を強化する「犯罪機会論」とは
では、現代の多様な犯罪に対応し、防犯力を高めるためにはどうすれば良いのでしょうか。その答えの一つが、「犯罪機会論」を知ることにあります。この理論は、犯罪は特定の機会が存在することで発生するという考え方に基づいています。つまり、犯罪者の内面的な動機だけでなく、犯罪が行われやすい物理的・社会的な「機会」を排除することが、防犯において極めて重要だとするのです。
この「犯罪機会論」を日本に広く提唱しているのが、立正大学文学部教授の小宮信夫氏です。小宮教授は日本人として初めてケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科を修了し、法務省や国連アジア極東犯罪防止研修所での研鑽、さらには警察庁の「持続可能な安全・安心まちづくりの推進方策に係る調査研究会」座長も務めた、まさに犯罪抑止・防犯の第一人者です。彼の指摘によれば、日本の防犯対策は「犯罪者天国」と映るほど遅れていると言わざるを得ません。犯罪者の動機にばかり目を向け、彼らが行動に移す「機会」を看過していることが、その大きな要因であると警鐘を鳴らしています。
 立正大学の小宮信夫教授。犯罪学の権威が令和時代の防犯対策を語る。
立正大学の小宮信夫教授。犯罪学の権威が令和時代の防犯対策を語る。
「たった70円」が誘発した窃盗犯の心理:機会が犯罪を生む
2024年に兵庫県で発生したある事件は、「犯罪機会論」の重要性を如実に示しています。市立中学校の校長が、コンビニのセルフサービス式コーヒーで、レギュラーサイズの110円を支払ったにもかかわらず、実際には180円のラージサイズを注いでいたとして、窃盗容疑で書類送検され、懲戒免職処分を受けました。たった70円の差額のために、彼は社会的地位も退職金も全てを失う結果となったのです。
「なぜたった70円のために、そこまで愚かな行動を取ったのか?」と多くの人が疑問に感じるでしょう。しかし、この一件は犯罪の本質の一面を浮き彫りにしています。世の中には、たとえ費用対効果が極めて悪く見えても、そこに「機会」さえあれば、犯罪に手を染めてしまう人が存在するのです。この校長の場合も、70円分の金銭的利益を得ようとしたというよりも、目の前にあった「他人に気づかれずに少しだけ得をする」という“カタルシス(ストレス解消)”や“優越感”を得られる「機会=チャンス」に誘発されて犯行に及んだ可能性が高いと考えられます。つまり、その「機会」こそが、犯罪を誘発する引き金となったのです。この事例は、犯罪は動機だけでなく、環境によって提供される「機会」によっても生み出されるという「犯罪機会論」の核心を明確に示しています。
結論
現代社会において、犯罪から身を守るためには、従来の「犯罪原因論」にのみ依存するのではなく、「犯罪機会論」という新たな視点を取り入れることが不可欠です。犯罪者の内面や動機を深く探ることも重要ですが、より実践的な防犯対策としては、犯罪が発生しやすい「機会」をいかに排除するかに焦点を当てるべきです。
今回ご紹介した小宮信夫教授の提唱する「犯罪機会論」は、まさに現代の犯罪状況に対応するための有効なアプローチであり、日本が喫緊に取り組むべき課題を示唆しています。私たち一人ひとりが日常生活の中で、不審な隙を作らない、防犯意識を高めるといった行動を取ることで、犯罪者が犯行に及ぶ「機会」を減らし、安全で安心な社会を築き上げていくことができるでしょう。今後、個人の防犯意識の向上はもちろん、地域社会や行政が連携し、犯罪機会を排除するための具体的な環境整備を進めることが、令和時代の新たな防犯対策として強く求められます。
参考資料
- Yahoo!ニュース / デイリー新潮: 「ルフィ事件」の教訓も「日本の防犯は『犯罪者天国』」…70円のコーヒー泥棒も生む「犯罪機会論」とは(2025年8月30日)