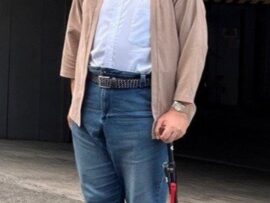日本が第二次世界大戦で敗戦した翌年から、ひとりの男性が全国を巡り、特攻隊員の遺族一人ひとりから丁寧な聞き取りを行い、膨大な数の遺品を預かっていました。その人物こそ、近江一郎氏です。彼はどのようにして遺品を受け取り、当時の遺族たちは、戦後の厳しい社会の中でその訪問をどのように受け止めたのでしょうか。この記事では、書籍『一億特攻への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』(文藝春秋)の一部を抜粋し、近江氏の足跡と、戦死した特攻隊員の遺族が抱いた複雑な心情を辿ります。
歴戦の特攻隊員・原田嘉太男とその遺族の物語
近江一郎という人物の存在は、長年語り継がれてきましたが、具体的な話が明らかになったのは2016年2月、鳥取県米子市出身の特攻隊員、原田嘉太男(はらだ・かたお)さんのご遺族を訪ねた時のことでした。原田さんは、太平洋戦争開戦時の真珠湾攻撃にも参加した900名近い精鋭部隊の一員であり、数々の激戦を生き抜いてきた歴戦の搭乗員でした。
しかし、アメリカ軍が硫黄島に上陸を開始した直後の昭和20年2月21日、原田さんは32機からなる「第二御楯隊」の隊長機として、千葉県の香取基地(現在の旭市、匝瑳市)から八丈島を経由し、硫黄島沖のアメリカ艦隊への体当たり攻撃に向かい、戦死しました。原田さんには達子さんという新婚の妻がおり、彼が妻に宛てた遺書が原田家には大切に残されています。戦後、兄に代わって原田家を継ぎ、田畑を守り続けてきた弟の昭さんは、嘉太男さんのこと、そして残された新婚の妻、さらに「嘉太男命(いのち)」とまで言われた母親の深い愛情について語ってくれました。

突然の訪問者、謎多き「近江中将」との出会い
原田昭さんが、兄・嘉太男さんの思い出を語る中で、数十年来の疑問を絞り出すように「近江一郎、という人のことはご存じですか?」と突然尋ねてきました。昭さんによると、近江氏は戦後すぐ、原田家を訪ねてきたというのです。昭さんが中学生になる頃、つまり戦争が終わってから3、4年後のことだったと記憶しています。近江氏は「兄(嘉太男さん)の弔いをさせてほしい」と申し出ました。
当時の原田家の父親は、その言葉に心から喜びました。終戦を迎え、それまでの価値観が180度転換した時代です。特攻隊員の遺族であると公言しても、社会からはほとんど顧みられず、「犬死にだった」「無駄死にだった」などと揶揄する声も聞かれ、遺族は肩身の狭い思いをしていた時期でした。そんな中、見ず知らずの近江氏が慰霊のために訪ねてきたのです。父親は喜び、物のない貧しい時代にもかかわらず、近江氏にご飯を食べさせ、家に泊まってもてなし、歓待しました。
しかし、近江氏にはひとつ奇妙な点がありました。彼は自分が何者であるかをはっきりと明かさなかったのです。国民服にゲートル、そして杖という質素な身なりで、「海軍の特攻隊員の遺族の元を回って慰霊している」とだけ語りました。かなり年配に見えたため、父親が「おたくは、海軍の大将か何かですか?」と尋ねると、近江氏は穏やかに「いやいや、違います」と答えました。さらに「では中将ですか?」と問うと、「まあ、そんなところにしておきましょう」という返事。それ以来、父親は近江氏のことを敬意を込めて「近江中将」と呼ぶようになったといいます。
近江一郎氏の訪問は、戦後の混乱期において、特攻隊員の遺族にとっては希望の光であり、忘れ去られようとしていた記憶と尊厳を守るための重要な存在でした。彼の地道な活動は、多くの遺族に心の拠り所を与え、後世に語り継ぐべき歴史の証言を集め続けたのです。
参考文献
- 『一億特攻への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』(文藝春秋)
- Yahoo!ニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/439927f12d59e46a122b991e8ccc499a68cd84b8)