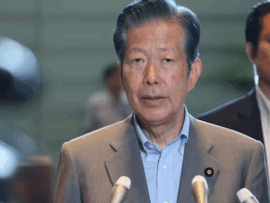現代社会において、企業における従業員のメンタルヘルスは重要な経営課題の一つです。しかし、日本国内の一部のメンタルクリニックから発行される「謎の診断書」が、企業の人事総務担当者の間で不信感を生み、適切な職場環境の維持を困難にしている実態が浮き彫りになっています。筆者は精神科医として、また産業医として企業の健康管理に携わる中で、この問題に頻繁に直面しています。企業側が抱く疑問や困惑は、単なる事務処理上の問題を超え、日本の労働社会における深刻な課題として認識されるべきでしょう。
突如現れる「謎の診断書」が引き起こす混乱
企業の人事総務担当者から寄せられる相談の中で、特に問題視されているのが、簡潔すぎるメンタルクリニックからの診断書です。ある日突然、「3ヵ月の休職を要する」という一行だけの診断書が提出され、その日から従業員が出社しなくなります。そして3ヵ月後、再び「復職可能」とだけ書かれた一行診断書が送られてくる。これらの診断書には、病状の詳細な説明も、休職期間がなぜ3ヵ月という長期にわたるのかの理由も、今後の治療方針や見通しも一切記載されていません。会社側としては、何が原因で休職に至ったのか、どのように対応すれば良いのか、全く見当がつかない状況に置かれます。
さらに、休職期間中に患者である従業員がどのような治療を受け、どのような状態に変化したのかも不明なままです。久しぶりに職場に姿を現した従業員は、表情に乏しく、動作は緩慢で、口調も重々しく、明らかに「病人らしい」様子であることが少なくありません。これを見て、人事担当者は「これで本当に職場復帰できるのか?」と強い疑念を抱かずにはいられません。ある人事担当者が「突然、我が子をカルト宗教に奪われた親のような心境だ」と率直に語ったのは、従業員の心身の健康と、働きやすい職場づくりに真剣に取り組んできたからこそ出てきた言葉でしょう。このような「一行診断書」は、企業の休職・復職支援を妨げ、深刻な人事管理上の課題を突きつけています。
 メンタルヘルス問題に頭を抱えるビジネスパーソンの様子
メンタルヘルス問題に頭を抱えるビジネスパーソンの様子
「診断書自動販売機」と化したクリニックの裏側
なぜ、このような「一行診断書」が横行するのでしょうか。その背景には、一部のメンタルクリニックが「診断書自動販売機」と化しているという実態があります。患者が「休みたい」と希望すれば「要休職」の診断書を、期間を伝えればその通りの期間を、復職を望めば「復職可能」と記載する。患者の要望通りに、あたかも自動販売機のように診断書を発行する傾向が見られます。
これらのクリニックは、「自己決定権の尊重」を盾に、精神医学的な状態を十分に評価することなく、患者の希望を優先します。医師法第19条に「正当な事由がなければ、診断書の交付を拒否してはならない」という文言があることを根拠に、「診断書を拒否する正当な事由はない」と解釈し、即座に診断書を発行してしまうのです。
クリニック側の視点から見れば、患者は「貴重な顧客」です。「要休職」の診断書発行で文書料を得て、休職期間中も定期的な通院を促して治療費を得、復職時の診断書発行で再び文書料を得る。その後も通院が継続されれば、さらなる医療収入に繋がります。患者が休職を希望した際に即日診断書を発行することは、その後の安定した医療収入を確保するための重要なビジネス戦略となり得ます。メンタルクリニック業界は顧客満足度が経営を左右するため、患者を喜ばせる「顧客サービス」の一環として、診断書発行が中心に据えられているのが現状です。
インターネットで「休職 診断書 即日発行」と検索すれば、数多くのメンタルクリニックがヒットします。これらのクリニックは、厳しい競争環境の中で生き残るため、「診断書がいかにあなたを守ってくれるか」といった謳い文句で顧客を惹きつけ、経営の持続可能性を支える要素として即日発行サービスを競い合っているのです。このようなビジネスモデルが、企業のメンタルヘルス対応における混乱と不信感を生み出す一因となっていることは否定できません。
健全な職場環境のために求められること
メンタルクリニックが発行する「一行診断書」の問題は、企業の人事管理を複雑化させるだけでなく、適切な医療と患者の職場復帰支援のあり方にも疑問を投げかけています。従業員の健康を守り、健全な職場環境を維持するためには、診断書の質と内容、そして企業と医療機関間の連携の改善が不可欠です。透明性のある情報提供と、従業員の真の回復を優先する医療の実現が、今後の日本の労働社会における喫緊の課題と言えるでしょう。