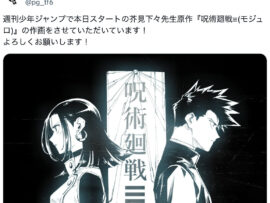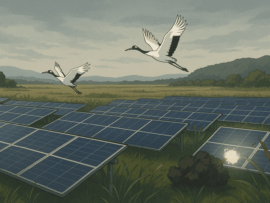東京地検特捜部の捜査対象である国会議員を別人と取り違え一面トップで報じるという、前代未聞の誤報。さらにその直前には「石破首相退陣へ」との号外で”大外し”を演じるなど、読売新聞は近年、前例のないレベルの誤報を連発し、その報道機関としての信頼性が大きく揺らいでいる。一体、日本の代表的なメディアである読売新聞の社内で何が起こっているのか。この一連の問題の背景を深く探ると、そこには山口寿一社長(68)が主導する「編集軽視人事」という、組織の根幹に関わる問題が横たわっていることが明らかになる。本稿では、度重なる誤報の内幕と、その背後にある“知られざる社内事情”、そしてそれが読売新聞のジャーナリズムに与える深刻な影響について詳述する。
相次ぐ「大誤報」が示す報道の質の低下
読売新聞が近年報じた複数の「大誤報」は、単なるミスでは片付けられない、組織的な問題を示唆している。特に世間を騒がせたのが、東京地検特捜部の捜査対象者を誤って報じた件と、「石破首相退陣」の号外である。
まず、国会議員誤報問題では、本来報じるべきではない無関係の議員を、あたかも容疑者であるかのように一面トップで大々的に報じてしまった。これは報道機関として最も重視されるべき「事実確認」と「個人情報保護」の原則が著しく欠如していたことを示す。この誤報は、対象となった議員の人格権を侵害しただけでなく、読者に対して誤った情報を与え、読売新聞に対する信頼感を大きく損ねた。社内では当然、厳しい自己検証が行われたとされるが、その結果が再び類似の誤報を防ぐに至らなかった事実は重い。
次に、「石破首相退陣へ」という内容の号外発行は、速報性よりも正確性が求められる重大な政治ニュースにおいて、その判断がいかに軽率であったかを露呈した。号外という、一般紙の中でも最も注目される形式で報じられたこの情報は、瞬く間に全国に広がり、結果的に事実と異なることが判明した際に、読売新聞の権威と信頼は地に落ちた。これらの誤報は、単発的なミスではなく、編集現場におけるチェック体制の甘さ、あるいは情報ソースの選定における問題、そしてなにより、最終的な報道判断を下す上層部の責任を問う声が社内外から上がった。読売新聞が自らの「検証記事」で述べた内容は表層的なものに過ぎず、その深層にはさらに根深い組織的課題が隠されている。
 読売新聞グループ本社の山口寿一社長が、相次ぐ誤報問題の渦中にいる様子を示す。
読売新聞グループ本社の山口寿一社長が、相次ぐ誤報問題の渦中にいる様子を示す。
山口寿一社長の「編集軽視人事」の構造
一連の誤報問題の核心にあると指摘されるのが、山口寿一社長が推進してきた「編集軽視人事」である。この人事方針は、編集・報道部門の専門性や経験よりも、経営効率や組織管理能力を優先する傾向があると言われている。
具体的には、長年現場で培われた報道の倫理観やノウハウを持つベテラン編集者の意見が軽視されがちになり、経営畑出身者や非編集部門の人間が編集部門の重要なポストに就くケースが増えているとされる。これにより、本来編集部門が持つべき「報道の砦」としての機能が弱体化し、記事の最終チェックや事実確認のプロセスが形骸化する恐れがある。過去の成功体験にとらわれ、時代の変化や情報伝達のスピードに対応できない、あるいは過度な速報性を求めるあまり、確認作業がおろそかになる土壌が形成されているのかもしれない。
このような人事体制は、現場の記者の士気にも影響を与えている。経験豊富な記者が報じた内容が、十分な報道経験を持たない上層部の判断で修正されたり、時には却下されたりすることもあるという。結果として、記者は本来のジャーナリズム精神に基づいた深掘り取材よりも、上層部の意向に沿った「無難な」記事作成に傾倒しがちになる。これは、読売新聞が伝統的に培ってきた「調査報道」の精神を損ない、結果として報道の多様性や深みを失わせる一因となり得る。山口社長の経営判断は、一見すると合理的に見えるかもしれないが、新聞社の生命線である「質の高い報道」を維持するという観点からは、疑問符がつけられる。
「知られざる社内事情」とジャーナリズムの危機
読売新聞の内部からは、こうした「編集軽視人事」が社内の意思決定プロセスに深刻な影響を及ぼしているという声が上がっている。「知られざる社内事情」として指摘されるのは、経営トップと現場の編集部門との間に生じている認識のギャップと、それが引き起こす情報の断絶である。
経営陣が事業拡大や収益確保を優先するあまり、報道倫理や記者倫理といったジャーナリズムの根幹が二の次にされる傾向があるという。特に、デジタル化の波に対応するための組織再編や人員配置が、必ずしも報道の質の向上に繋がっていない現状がある。新しい技術やプラットフォームへの投資が重要であることは間違いないが、それが報道の核心である「正確性」や「公正性」を犠牲にしては本末転倒である。
また、社内コミュニケーションの不全も深刻な問題だ。誤報が発生した際、その原因究明と再発防止策の徹底が不可欠であるが、責任の所在が曖昧になったり、根本原因に踏み込んだ議論が避けられたりすることがあるという。これにより、問題が表面化しても、その解決策が対症療法に留まり、組織的な欠陥が温存されてしまう。報道機関としての「自己浄化作用」が機能不全に陥っている状態は、日本のジャーナリズム全体にとっても由々しき事態と言える。
読売新聞は、その巨大な規模と影響力ゆえに、日本の言論空間において重要な役割を担ってきた。しかし、度重なる誤報と、その背後にあるとされる「編集軽視人事」は、その役割を全うするための基盤を揺るがしかねない。読売新聞が自らの「検証記事」で問題の根深さに切り込まず、表面的な説明に終始していることは、内部からの抜本的な改革への意欲が不足していることの表れとも解釈できる。
結論:信頼回復に向けた抜本的改革の必要性
読売新聞が相次ぐ誤報により直面している信頼性危機は、単一のミスではなく、組織の深部に根差した構造的な問題、特に山口寿一社長が推し進める「編集軽視人事」にその遠因があると言える。国会議員の誤報や「石破首相退陣」の号外といった一連の失態は、編集現場の専門性の軽視、チェック体制の甘さ、そしてジャーナリズムの根幹たる事実確認のプロセスにおける不備が複合的に絡み合って生じた結果である。
日本の報道機関のリーダーとして、読売新聞がその社会的責任を果たすためには、目先の経営効率だけでなく、報道の質と信頼性を最優先する抜本的な改革が不可欠である。これには、現場の記者の専門知識と経験を尊重し、編集部門の独立性を強化する人事制度への見直し、報道倫理と事実確認の徹底を図る社内教育の強化、そして経営陣と編集現場との間の健全な対話と協力関係の再構築が含まれるべきだ。
読売新聞が真の意味で信頼を取り戻し、社会に価値ある情報を提供し続けるためには、自己検証をより深く行い、その結果に基づいて組織全体で変革を断行する勇気と覚悟が求められる。これは読売新聞だけでなく、日本のメディア全体が直面する課題であり、その動向は今後のジャーナリズムのあり方にも大きな影響を与えることだろう。
参考文献:
- 「週刊新潮」2025年9月11日号 特集記事【無関係の維新議員を1面トップで容疑者扱い…大誤報だけではない読売新聞「山口寿一社長」の罪と罰】 (本稿はこの特集記事の一部を再編集したものです)