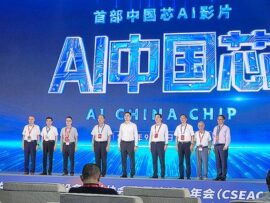例年、年末が近づくとテレビCMなどで盛り上がりを見せる「ふるさと納税」仲介サイトによる宣伝合戦が、今年は異例の活況を呈しています。特に「最大100%還元」といったポイント還元を強調する広告を目にする機会が増えていることでしょう。この背景には、総務省が打ち出した「仲介サイトによるポイント付与の禁止」という大きな変更があり、9月末の期限を前に利用者を取り込もうとするサイト側の動きが加速しているのです。物価上昇が続く中で政府の減税への批判が高まる中、国民の関心を集めるふるさと納税の制度が、今、岐路に立たされています。
活況を呈するふるさと納税宣伝戦と「駆け込み需要」
テレビコマーシャルなどで目にすることも多い「ふるなび」をはじめとするふるさと納税仲介サイトは、今年に入り特に活発な宣伝活動を展開しています。年末商戦を待たずして、「最大100%還元」といった高率のポイント付与を前面に押し出す広告が目立ち、多くの消費者の関心を集めています。これは、総務省が「ふるさと納税の仲介サイトが独自に付与するポイントは、9月末をもって禁止される」と決定したことによるものです。この期日を目前に控え、仲介サイト各社は、ポイント付与が終了する前に「駆け込みで利用したい」と考えるユーザー層を取り込むため、広告に一層力を入れている状況です。
総務省が強調する「ふるさと納税本来の趣旨」
総務省は、今回のポイント付与禁止措置について、「ふるさと納税は、返礼品やポイント目当てではなく、寄付金の使い道や目的から自治体を応援するという本来の趣旨から逸脱している」と説明しています。仲介サイトが提供するポイント還元は、自治体がサイトへ支払う掲載手数料を原資としていると総務省は指摘。これにより、自治体本来の財源がサイト側の顧客獲得競争に流用され、制度の健全性が損なわれるとの懸念を示しています。寄付者が応援したい自治体を選び、その寄付金が地域の活性化に役立つという本来の姿を取り戻すことが、総務省の目指すところです。
仲介業者の強い反発と楽天グループの攻防
総務省の方針に対し、仲介業者からは強い反発の声が上がりました。ポイント還元は民間企業の「営業努力」の一環であり、自治体が支払う手数料にポイント原資が上乗せされているわけではないと主張。むしろ、民間企業の自由な事業活動に過剰な規制をかけることは、総務大臣の裁量権を逸脱していると訴えてきました。
中でも、楽天グループは三木谷浩史会長兼社長が先頭に立ち、この禁止措置に反対する大規模な署名運動を展開しました。2025年3月には、295万件もの反対署名を石破茂首相(当時)に提出し、制度変更への異議を表明しました。さらに、楽天グループは7月に総務省の禁止決定の無効確認を求める行政訴訟まで提起し、法的手段を通じてその決定を覆そうと試みました。
 首相官邸にて、ふるさと納税ポイント還元禁止に関して石破首相と面会する楽天グループ三木谷浩史会長兼社長
首相官邸にて、ふるさと納税ポイント還元禁止に関して石破首相と面会する楽天グループ三木谷浩史会長兼社長
楽天グループ、方針転換し10月からのポイント付与中止を発表
しかし、総務省は一貫して態度を変更することなく、最終的に楽天グループも方針転換を余儀なくされました。2025年9月1日、楽天グループは10月1日以降、ふるさと納税におけるポイント付与を取りやめることを正式に発表。これにより、仲介業者は総務省の通達に従わざるを得ない状況となりました。この決定は、ふるさと納税の利用を検討している消費者や、仲介サイトを利用する自治体にとっても大きな影響を与えることになります。ポイント還元を重視していた寄付者にとっては、今後の自治体選びや寄付行動に変化が生じる可能性があり、制度のあり方が改めて問われることとなるでしょう。
今回のポイント付与禁止は、ふるさと納税が本来目指すべき姿とは何かを問い直し、自治体と寄付者の関係性をより直接的な「応援」へと回帰させようとする総務省の強い意向が反映された結果と言えます。