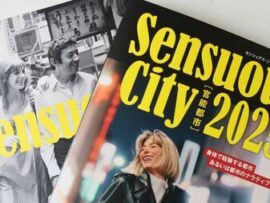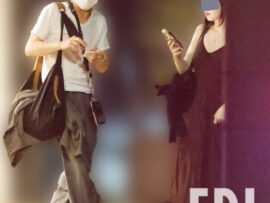来月末、皇位継承順位第1位の皇嗣であらせられる秋篠宮さまが60歳の還暦を迎えられます。この節目の年に、高御座に最も近い地位にありながら、秋篠宮さまご自身が皇位継承の意思をお持ちではないという報道が改めて注目を集めています。干支が一巡し、新たな人生の出発点とされる還暦という時期に、このお気持ちに変化はないのでしょうか。
 秋篠宮さまが来月末に還暦を迎えられる様子。皇位継承の意思について注目が集まる。
秋篠宮さまが来月末に還暦を迎えられる様子。皇位継承の意思について注目が集まる。
「還暦」が意味するものと皇位継承への影響
「還暦」とは、十二支と十干を組み合わせた干支が60年で一巡し、生まれた年の干支に戻ることを意味します。中国の敬老思想から生まれた長寿を祝う慣習であり、日本では奈良時代の聖武天皇の祝賀祭にその原型が見られます。1965年11月30日にお生まれになった秋篠宮さまは、今月末をもって満60歳となられます。皇位継承の最前線に立つ秋篠宮さまが、この伝統的な節目を迎えられるにあたり、ご自身の皇位継承に関するお考えが焦点となっています。
高齢即位への懸念と朝日新聞の報道
朝日新聞は2019年4月21日の朝刊で、天皇陛下の退位を実現する特例法成立後、秋篠宮さまが「兄が80歳のとき、私は70代半ば。それからはできないです」と皇位継承について語られたと報じました。これは、当事者として高齢での即位がもたらす難しさ、具体的には在位期間の短さによる度重なる改元や代替わりに伴う多大なコストへの懸念を指摘したものと受け止められています。宮内庁関係者からも「この記事を読んで『やはりそうか』と感じた職員は多かった」との声が聞かれ、秋篠宮さまの懸念が庁内でも広く共有されていたことが伺えます。
国民負担を避ける姿勢と大嘗祭への異論
秋篠宮さまは、上皇陛下が天皇ご在位中、憲法第4条によって政治的発言が制限される中で、上皇陛下のお気持ちを代弁し、国家財政の節約を強く訴えてこられました。特に、上皇陛下ご自身の陵(墓)の縮小を希望されるなど、国民に過度な経済的負担をかけることを極度に嫌悪されていた背景があります。この考えに基づき、秋篠宮さまは、生前退位に伴う重要な行事である大嘗祭に公的な国費を投じて盛大に実施する政府・宮内庁の方針に異を唱えられました。この苦言に対し、当時の宮内庁次長であった西村泰彦長官(現宮内庁長官)が記者会見で反省の弁を述べる事態に至りました。
このような国民への負担軽減を重視するお考えから、宮内庁内では、ハイコストとなるリスクが高いご自身の高齢即位を秋篠宮さまが「よしとはしないだろう」という見方が根強く、前述の「やはりそうか」という受け止めが大勢を占めたのです。宮内庁元幹部は、大嘗祭に関する「宗教色が強い」という秋篠宮さまのお言葉は、政教分離の建前を述べたに過ぎず、本質的には国民への財政的負担を懸念されたものだと指摘しています。
結論
来月還暦を迎えられる秋篠宮さまの皇位継承に対するお考えは、単に個人的なご意向に留まらず、国民への財政的負担、ひいては皇室のあり方そのものに対する深い配慮に基づいていることが明らかになりました。高齢での即位がもたらす課題と、これまでの皇室運営における国民負担軽減への強い思いが、秋篠宮さまの「皇位継承のご意思なき」という報道の背景にあると言えるでしょう。この還暦という節目を経て、秋篠宮さまのお気持ちが今後どのように推移していくのか、引き続き注目が集まります。
参考資料
- 朝日新聞 2019年4月21日付朝刊 記事
- 日本国憲法 第4条
- 宮内庁関係者への取材
- 宮内庁元幹部への取材