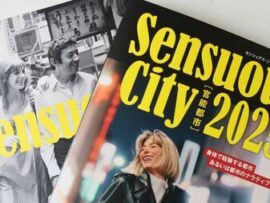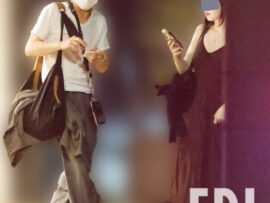人類の歴史は、地球規模の支配を築き上げた壮大な成功の物語のように映るかもしれません。しかし、その輝かしい成果の裏で、ホモ・サピエンスは常に「借りものの時間」を生き続けてきました。何千年にもわたる繁栄の時代は、今、その終わりを告げようとしています。一体なぜ、このような状況が訪れたのでしょうか? 発売からたちまち重版を重ねている話題の書『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』は、人類の輝かしい繁栄の道のりを振り返りながら、絶滅の可能性、その根本的な理由、そして運命を回避するための希望について深く考察しています。サイエンス作家の竹内薫氏も、「深刻なテーマを扱っているにもかかわらず、著者の筆致はユーモアとウィットに富み、読後には痛快な感覚が残る。まさに魔法のような一冊だ」と推薦するなど、日本国内外の第一人者から高い評価を得ています。本書の核心に迫る内容の一部を、ここに特別に公開します。
気候変動が加速させる大規模な人の移動
気候変動の深刻化、世界的な人口の急速な増加、そして経済的・政治的な不安定要素――これらの複合的な要因が、人々が故郷を離れ、新たな場所へと移住を決断する主要な原動力となっています。
ガイア・ヴィンスは著書『Nomad Century(ノマド・センチュリー)』の中で、今後数十年のうちに、地球の南半球に位置する「グローバル・サウス」の灼熱化が進むことで、より穏やかな気候を持つ北半球の先進国、すなわち「グローバル・ノース」への人の移動は避けられない現象であると指摘しています。そして、もし北側の国々が適切な心構えと受容の姿勢を持てば、この大規模な人の移動は、むしろ社会にとって歓迎すべき恩恵をもたらす可能性があると主張します。多くの先進国では自国民の人口が急速に減少していくと予測されており、活気ある移民たちは、この労働力や社会の活力の空白を埋める重要な存在となり得るからです。日本の少子高齢化問題にも示されるように、人口構造の変化は先進国共通の課題であり、移民の受け入れは持続可能な社会を築くための適応戦略の一つとして注目されています。
 灼熱化する土地を離れ、新たな居住地を求める人々の移動の光景
灼熱化する土地を離れ、新たな居住地を求める人々の移動の光景
人類本来の姿としての「移動」の歴史
そもそも、人類にとって移動こそが本来の生きる姿でした。農耕の発明とその後の定住生活が始まったのは、人類の全歴史から見れば、わずか3パーセントほどの短い期間に過ぎません。それ以前の気の遠くなるような長い年月、ホモ・サピエンスの小さな集団は、どこか一か所に腰を据えることなく、常に新たな資源とより良い土地を求めて移動し続けてきました。私たちの遠い祖先たちも、まさに同じような遊牧民としての暮らしを送っていたのです。
人類の歴史において、特に際立って重要な大規模な移動が過去に二度ありました。最初の大きな移動は約200万年前に起こり、ホモ・エレクトスが初めてアフリカ大陸を離れてユーラシア大陸へと進出しました。彼らはやがて多様な種へと分化し、ヨーロッパのネアンデルタール人、東南アジアのホビットたち(ホモ・フロレシエンシス)、ホモ・アンテセッサー、ホモ・ハイデルベルゲンシスなどがその代表です。二度目の大規模な移動は、おそらく複数の波に分かれて、約12万年前から5万年前ごろにかけて発生しました。アフリカ大陸に留まっていたホモ・サピエンスがユーラシアへと広がり、最終的には他のすべてのヒト属の種に取って代わり、地球上に唯一のヒト属として君臨することになったのです。
避けられない「第三の大移動」の波と、その選択
そして今、人類史における「第三の大移動」がまさに始まろうとしています。気候の厳しさが今後ますます増大するにつれて、アフリカやユーラシア大陸の各地から、これまで以上の多くの人々が北を目指して移動してくるでしょう。この巨大な人の流れは、いかなる法律をもってしても、あるいは地中海や北海に配備された巡視艇によっても、その勢いを完全に食い止めることは不可能であると本書は警告します。
しかし、この過酷な環境下で全ての人が移動を選ぶわけではありません。ますます暑く、湿度が高く、時には甚大な洪水にも見舞われる地域に暮らす人々の多くは、基本的にその場に留まることを選択するかもしれません。しかし、もしそうした選択をした場合、その結果として何十億人もの命が失われる可能性も指摘されています。それは、今世紀末ごろに訪れると予測されている世界人口の減少を、さらに劇的に加速させる要因となるでしょう。一方で、一部の人々は、外部の過酷な環境から完全に隔絶された未来都市を建設することで、その場に適応しようと試みるかもしれません。とはいえ、北へと押し寄せる移民の波は、たとえ膨大な数に見えたとしても、世界全体から見れば依然として少数派にとどまるだろうと予測されています。
結論:移動の必然性と未来への洞察
ホモ・サピエンスの歴史は、常に移動と適応の連続でした。気候変動によって引き起こされる「第三の大移動」は、人類が直面する避けられない現実であり、過去の歴史が示すように、移動は人類の生存戦略そのものと言えるでしょう。この地球規模の動きを理解し、先進国が人口減少という課題を抱える中で移民をどのように受け入れ、共存していくかは、私たち日本を含む世界の国々にとって喫緊の課題であり、未来の社会を形成する上で極めて重要な意味を持ちます。本書は、この複雑な人類の運命に対し、冷静かつ深い洞察を提供し、私たちが未来に向けてどのような心構えを持つべきかを示唆しているのです。
参考資料
- ヘンリー・ジー著『ホモ・サピエンス30万年、栄光と破滅の物語 人類帝国衰亡史』(竹内薫訳、ダイヤモンド社)
- ガイア・ヴィンス著『Nomad Century: How to Survive the Climate Upheaval』