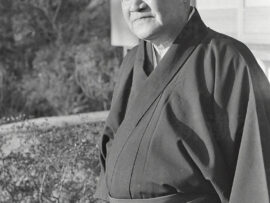近年、日本のPTA(Parent-Teacher Association)の加入者数が顕著に減少しており、この傾向は保護者と学校との関係性に大きな変化が生じていることを示唆しています。教育ジャーナリストの朝比奈なを氏も指摘するように、非加入者の増加は、保護者が学校との距離感を再考し始めた結果かもしれません。PTAが設立された歴史的経緯とその当初の目的を鑑みると、約70年間の間に保護者と学校の関わり方が大きく変容したことが浮き彫りになります。本記事では、文部科学省の調査データに基づき「PTA離れ」の実態を明らかにし、その起源から現代に至るまでの変遷を深掘りすることで、現代日本のPTAが直面する課題と、今後の保護者と学校の協働のあり方について考察します。
文部科学省の調査が示す「PTA離れ」の実態
文部科学省が全国の小学6年生と中学3年生を対象に実施する「全国学力・学習状況調査」は、子どもの学力だけでなく、家庭状況や生活習慣、さらには保護者の教育に関する考え方についても多角的な視点から調査を行っています。特に2013年、2017年、そして2021年の調査では、保護者の学校行事やPTA活動への関わり方に関する詳細なデータが収集されました。
この調査結果を分析すると、保護者の「PTA離れ」が明確に見て取れます。具体的には、授業参観や運動会、音楽会といった一般的な学校行事への参加については、小学校、中学校ともに半数以上の保護者が「いつも参加」または「時々参加」の意向を示しています。これは、保護者が子どもの学校生活や学習状況に対する高い関心を持っていることを裏付けています。
一方で、PTA活動の役員や委員になることに対する参加意欲は著しく低い傾向にあります。「あまりしない」「全くしない」と回答した保護者の割合は、小学校で約52%、中学校では約65%にも上ります。このデータは、保護者が学校行事への参加とは異なり、PTAの運営や具体的な活動への関与には消極的であることを示しており、現代の保護者がPTAに対して抱く意識の変化を浮き彫りにしています。この背景には、多忙な現代社会での時間的制約や、PTA活動の内容に対する疑問などが複雑に絡み合っていると考えられます。
PTAの起源と日本への導入:GHQの要請から
PTA(Parent-Teacher Association)は、その英語名が示す通り、各学校に組織される保護者と教職員が共に子どもの教育を支援する社会教育関係団体です。そのルーツはアメリカにあり、1897年に2人の女性が自主的に開催した「全米母親議会」が始まりとされています。この会議には母親だけでなく、父親や教員なども参加するようになり、後に「全米保護者教師議会」と改名され、現在の「全米PTA団体」へと発展しました。
日本におけるPTAの設立は、戦後の教育改革と深く結びついています。1946年、GHQ(連合国軍総司令部)の要請によりアメリカから派遣された教育使節団の報告書、そして翌1947年の極東委員会による日本の教育制度改革に関する指令を受け、GHQは日本の全国の学校にPTAの設置を強力に推進しました。当時の文部省は、GHQの意向を受けてPTA設立のための詳細な手引書を作成し、これを全国の都道府県知事に通達。この通達を機に、日本全国でPTAの結成が急速に進められることとなります。
GHQと文部省は、戦前の国家主義的な教育体制からの脱却を図り、教育の民主化を推進する上でPTAが重要な役割を果たすと考えていました。地域によっては戦前から存在した後援会などの組織もPTAに合流させながら、全国的な組織化が目指されましたが、当時の政治状況の複雑さから早期の全国組織結成は困難を伴いました。
 学校行事に参加する保護者たちの様子
学校行事に参加する保護者たちの様子
全国組織の確立と現代PTAの変遷
全国的なPTA組織の確立は、GHQの要請から数年後の1952年、東京で開催された「日本父母と先生の会全国協議会結成大会」をもって実現したと研究者は考察しています。この全国協議会の設立を皮切りに、各学校のPTAは上部団体として市町村単位、都道府県単位のPTA連合会を形成していきました。さらに、これらの地域ごとの連合会や学校段階ごとの連合会を束ねる全国組織として、一般社団法人全国PTA連絡協議会が設けられ、PTA活動は制度的にも確立されていきました。
PTAは当初、教育の民主化や地域社会と学校の連携強化を目的として設立されましたが、約70年の時を経て、その役割や活動内容、そして保護者のPTAに対する意識は大きく変化しました。多忙な共働き世帯の増加や、情報通信技術の発展によるコミュニケーション手段の多様化など、社会環境の変容はPTA活動にも大きな影響を与えています。
現代においては、PTA活動のボランティア性や強制加入の慣行、活動内容の不透明性などが課題として指摘されるようになり、冒頭で述べたPTA参加率の激減につながっています。設立当初の目的と現代社会のニーズとの間に生じたギャップは、PTAが持続可能な組織として機能し続けるための抜本的な改革を迫っていると言えるでしょう。
結論
PTA参加率の激減は、単なる組織離れではなく、日本の保護者と学校の関係性が大きく変容している現代の社会状況を反映しています。文部科学省の調査データが示す「PTA離れ」の具体的な数字は、保護者が学校行事への関心は維持しつつも、PTAの運営や活動への積極的な参加には消極的である実態を浮き彫りにしました。
PTAがGHQの要請によって日本の教育民主化の一環として導入され、全国組織へと発展してきた歴史的経緯は、その設立当初の崇高な目的と現代における課題との間に横たわるギャップを理解する上で不可欠です。現代社会のライフスタイルの変化や価値観の多様化は、PTAの活動内容や運営方法、ひいては存在意義そのものに対する再考を促しています。
今後、日本の教育現場において保護者とのより良い連携を築くためには、PTAがその歴史的背景を認識しつつ、現代社会のニーズに合わせた柔軟な組織運営と活動内容の変革を進めることが不可欠です。保護者が真に貢献したいと思えるような、開かれた、そして実効性のある新しい形の協働関係を模索することが、PTAの未来、ひいては子どもの健全な成長を支える上で重要な鍵となるでしょう。
参考文献
- 朝比奈なを. (2025). 『なぜ教員の質が低下しているのか』朝日新聞出版.
- 文部科学省. 全国学力・学習状況調査.
- Yahoo!ニュース. (2025年10月20日). 「PTAの加入者数が激減している。教育ジャーナリストの朝比奈なをさんは「非入会者が増えたのは、学校との距離を遠くしたいと考える保護者が多くなったからではないか。PTAが設立された経緯や目的を鑑みるに、この約70年間で学校と保護者の関係は大きく変化した」という――。」(PRESIDENT Online掲載).