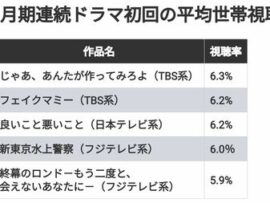近年、日本で「右傾化」「保守化」といった言葉が取り沙汰される中、例えば高市氏の首相就任を巡る議論や、「日本人ファースト」を掲げる参政党の躍進が注目されています。しかし、このような流れは日本に限ったことではありません。「アメリカ・ファースト」を掲げたトランプ政権に代表されるように、世界の主要国で保守的な考え方を支持する人々が急増し、一大潮流となっています。元国連職員でロンドン在住の著述家である谷本真由美氏(Xでの名義は“めいろま”として25万人以上のフォロワーを持つ)による新連載「世界と比較する日本の保守化」では、一般的な「保守VSリベラル」の対立軸とは異なる、世界のリアルな実情が客観的に語られます。日本人はこの世界的な保守化の本質を本当に理解しているのでしょうか。
 高市早苗氏と日本の保守化動向
高市早苗氏と日本の保守化動向
世界的な「保守化」の潮流とその背景
世界では、これまでリベラルや左翼が強かった国々においても、保守的な思想への支持が近年劇的に増加し、大きなうねりとなっています。この「保守化」の流れは、アメリカや欧州の主要先進国に留まらず、東欧や南アジアにまで広がりを見せています。
日本のメディアでは、この保守化の流れを特定の国や政治家によって仕組まれたものだとする論調が目立ちますが、果たして本当にそうなのでしょうか。また、他国の保守化と日本との間にはどのような違いがあるのでしょうか。日本のメディアだけを見ていると、なぜ世界がこれほどまでに保守化しているのか、その根深い理由を把握しにくいのが現状です。欧州と日本を往復している谷本氏の視点から見ると、日本人はその背景を十分に理解していないように思われます。
日本が見落としてきたグローバル化の「負の側面」
先進国の保守化を語る上で、日本人がまず思い起こすのはアメリカでしょう。1990年代のクリントン政権時代は、グローバル化を積極的に推進し、当時の世界経済の自由化の波に乗る「経済的リベラリズム」と、同時に「治安・国境管理の強化」という二つの政策を共存させていました。
冷戦終結後の1990年代のアメリカは、国家間の移動がより緊密になり、開かれた世界、自由な貿易、自由な人の移動を促進する中で、世界経済との繋がりを強化し、自国をさらに豊かにするという課題に直面していました。1994年には北米自由貿易協定(NAFTA)を締結し、関税の撤廃、投資の自由化、労働条件の均一化を通じてカナダ、メキシコとの経済的結びつきを強化しました。
しかし、人の移動や貿易の自由化は、様々なマイナス面も同時に引き起こしました。アメリカの調査機関であるピューリサーチのデータによれば、1990年代には年間平均でおよそ110万人程度の移民がアメリカに流入し、ピーク時の2000年には150万人に達しています。その一方で、クリントン政権下では、IT改革の波に乗るため、技能労働者向けのビザである「H1-B」の上限を大幅に引き上げました。高度な技能を持つIT系技術者などは主にカリフォルニアや東海岸に居住し、そのままアメリカに移住するケースが多く見られました。彼らの多くは、地元の平均的なアメリカ人に比べるとはるかに高い報酬を得ていたのです。
同時に、クリントン政権下ではカリフォルニアなどで不法移民問題が顕在化し、不法滞在者や低賃金移民に対しては厳しい政策を講じていました。これは、現代であれば「超保守系の排他主義」と指摘されてもおかしくないような厳格な移民政策だったのです。この事実は、日本だけでなく各国のリベラルや左翼が都合よく指摘しない、非常に重要な側面と言えるでしょう。
まとめ
世界の「保守化」は、単純なイデオロギー対立や特定の政治家の登場だけで説明できるものではありません。クリントン政権下のグローバル化がもたらした経済的恩恵の裏側で、移民問題や国内の格差拡大といった「負の側面」が積み重なり、それが人々の間に保守的な感情を醸成していった経緯があります。日本がこの世界的な潮流を深く理解するためには、メディアが報じないような「都合の悪い真実」にも目を向け、多角的に分析することが不可欠です。