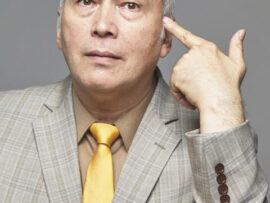約1000万人の納税者が利用する人気の「ふるさと納税」制度が、今、深刻なトラブルと法廷闘争の渦中にあります。自治体と国、さらにはサービス仲介企業と国との間で裁判が相次ぎ、その背景には、多くの利用者が目を向けずにきた制度自体の構造的な問題が横たわっています。単にお得な返礼品を受け取るだけの制度として喜んでばかりはいられない、その複雑な実態を深掘りします。
 東京都内で開催された楽天超ふるさと納税祭で賑わう会場の様子
東京都内で開催された楽天超ふるさと納税祭で賑わう会場の様子
ふるさと納税制度の誕生とその浸透
「地方から東京に来た人たちは、自分を育ててくれたふるさとに何らかの形で貢献をしたい。絆を持ち続けたい。そうした私の考えから『ふるさと納税』を発案し、実現に移したのであります」。この言葉は、菅義偉元首相がかつて自身の首相就任会見で、肝いり政策の生みの親として誇らしげに語ったものです。第1次安倍政権で総務相を務めていた菅氏が主導し、2008年にスタートしたこの制度は、故郷や応援したい自治体へ寄附を行うことで、そのうち2000円を超える部分が住民税と所得税から控除される仕組みです。控除の上限は個人の年収によって異なり、おおよそ住民税の2割程度。これにより、寄附額が大きいほど実質的な“節税”効果が期待できる上、自治体からは魅力的な返礼品が贈られるため、利用者の間で急速に浸透しました。
現在では、納税義務者の約6人に1人にあたる約1000万人が利用する一大制度へと成長。日本の全自治体の9割以上、1600を超える市区町村および都道府県が参加し、総務省の統計によれば、この15年間で寄附金の総額、利用者数共に一貫して右肩上がりで推移しています。これは、地域活性化と税制優遇が結びついた成功例として広く認識されてきました。
返礼品競争が生んだ「官製通販」の歪み
しかし、ふるさと納税の人気の裏側では、多くの寄附金を集めようと全国の自治体間で過熱な返礼品競争が繰り広げられてきました。結果として、この制度はあたかも“官製通販”のような様相を呈し、本来の「地方創生」という理念から逸脱しているとの批判も少なくありません。豪華すぎる返礼品や、地域との関連性が薄い返礼品が問題視され、総務省はこれまでにも度々、制度の適正化に向けたルール変更を行ってきました。寄附額の3割以下、地場産品に限るなどの基準が設けられ、違反する自治体は制度から除外される措置も講じられてきたのです。
泉佐野市と国との法廷闘争:アマゾンギフト券問題の顛末
こうした制度の運用を巡っては、近年、国と自治体との間で法廷闘争に発展するケースが頻発しています。中でも注目を集めたのが、大阪府泉佐野市が国を相手取った裁判です。今月8日、大阪高裁は、この訴訟において重要な判決を言い渡しました。
社会部デスクが説明するには、泉佐野市は2018年度に、返礼品としては異例の「アマゾンギフト券」を提供するキャンペーンを実施。この結果、同市は全国トップの約498億円もの巨額な寄附金を集めました。これに対し、総務省は2019年に寄附金の集まった額に応じて特別交付税の配分を決定する省令改正を行い、泉佐野市への配分を実質的に9割減額する措置を取りました。市はこの減額措置を違法であるとして国を提訴。一審では市が勝訴し、国が控訴していましたが、今回の大阪高裁の判決でも一審判決が支持され、総務省による減額には法的根拠が乏しいとの判断が示されました。泉佐野市はこれまでも、地場産品とは無縁の高級和牛やビールなどを返礼品として提供し、その「なりふりかまわぬ」手法が度々物議を醸してきました。このような自治体の攻めの姿勢に対し、総務省は「返礼品は寄附額の3割以下」「地場産品に限る」といったルール変更で対応してきた経緯があります。
仲介サイト「楽天」も提訴:制度設計への異議
しかし、度重なる国のルール変更に「話が違う」と異議を申し立てているのは、泉佐野市のような自治体だけではありません。先月には、ふるさと納税の仲介サイトを運営する大手企業である楽天が、国に対して起こした裁判が始まりました。これもまた、制度運用を巡る政府の方針転換が、ビジネスモデルに大きな影響を与えていることの現れであり、制度設計のあり方自体が問われる事態へと発展しています。
まとめ
ふるさと納税は、地方への貢献と納税者の節税メリットを両立させる画期的な制度として発展してきましたが、その裏側では返礼品競争の過熱、「官製通販」化、そして国と自治体・事業者間の法廷闘争といった様々な課題が顕在化しています。泉佐野市の勝訴判決や楽天による提訴は、制度の根本的な設計や運用、そして法的な正当性について、改めて社会全体で議論すべき時期に来ていることを示唆しています。単なる税優遇や魅力的な返礼品という側面だけでなく、制度が抱える構造的な問題を深く理解し、その持続可能性と公平性を追求することが今後の重要な課題となるでしょう。