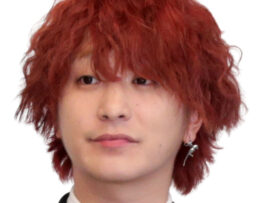日本株市場の熱狂が止まりません。日経平均株価が史上初めて5万円の大台を突破したというニュースは世間を賑わせました。しかし、こうした歴史的な株価の高騰とは裏腹に、多くの家庭では日々の生活が厳しさを増しているのが実情です。この矛盾とも言える状況は一体どこから生じているのでしょうか。近著『株高不況』が話題となっている第一生命経済研究所の藤代宏一氏に、その背景とメカニズム、そして個人が今後の経済動向をどう理解すべきかについて詳しく聞きました。
 史上初めて5万円を突破した日経平均株価の推移を示すグラフ
史上初めて5万円を突破した日経平均株価の推移を示すグラフ
今の株価上昇は「バブル」ではない:経済成長率から見る実態
株価が過去最高値を更新するたびに、「生活が苦しいのに、とても景気が良いとは思えない」という街の声が聞かれ、多くの人が共感しています。藤代氏は「今の株価上昇がバブルではないかと、様々な場所で問われます」と語ります。氏の著書『株高不況』には、「株価は高いのに生活が厳しい本当の理由」というサブタイトルが添えられています。
藤代氏によれば、「現在の株価は、企業収益に対して適正な範囲内」であり、1989年に日経平均株価が4万円に迫った「バブル経済期」とは根本的に異なるという見解を示しています。この点を裏付けるデータは複数ありますが、ここでは「経済成長率」を用いてその違いを明らかにしていきます。
街角の「景気実感」と「実質GDP」の連動性
経済成長率は、一国の経済規模が特定の期間にどれだけ拡大したかを示す指標です。これは、国内で一定期間に新たに生み出された生産物やサービスの合計額である「国内総生産(GDP)」の対前年比伸び率で表されます。GDPには、物価変動の影響を取り除いた「実質GDP」と、物価変動を含んだ「名目GDP」の二種類が存在します。通常、経済成長率という場合は、実質GDPの伸び率を指すことが一般的です。
藤代氏は、「世の中の人々が感じる景気の実感に最も近いのは実質GDPの動き」であると指摘します。ここ数年の実質GDPの伸び率を見ると、横ばいの推移が続いており、このような状況では多くの人が景気の好転を感じにくいのは当然と言えるでしょう。しかし、ここで名目GDPに目を向けると、状況は一変します。
インフレが加速させる「名目GDP」と「株価」の連動
日本の名目GDPは、2022年頃からその増加速度を加速させています。2023年には590兆円に達し、2024年には初めて600兆円を突破し608兆円となる見込みです。これは約3年間で50兆円以上の増加に相当し、実質GDPとは明確な格差が生じています。
この実質GDPの伸び悩みと名目GDPの急拡大の背景にあるのは、他ならぬ「物価上昇」、すなわちインフレの進行です。インフレとは、物価や賃金を含め、あらゆるものの価格が全般的に上昇する現象を指します。藤代氏は、この物価上昇の流れの中で「株の値段」も上がっていると理解できると説明します。実際、名目GDPと株価は長期的に強い連動性を示すことが知られています。
企業が販売する製品やサービスの価格が値上げされれば、販売数量が変わらなくても売上高や利益は増加します。その結果、株価の重要な裏付けとなる企業収益(一株当たり利益)も増加し、株価の上昇へと繋がるのです。人々の景気実感に近い実質GDPの動きが停滞し、食料品や日用品の値上がりによる不況感が漂う中でも、この物価上昇そのものが名目GDPを押し上げ、ひいては企業業績を増進させています。これこそが、現在の日本株高を牽引する主要な原動力となっているのです。
結論
日経平均株価の記録的な高騰は、一見すると実体経済の感覚と乖離しているように見えます。しかし、第一生命経済研究所の藤代宏一氏が指摘するように、現在の株高は1980年代後半の「バブル経済」とは異なり、企業の適正な収益に裏付けられています。この現象の背景には、物価変動の影響を除いた「実質GDP」が横ばいである一方で、物価上昇(インフレ)によって「名目GDP」が大きく拡大しているという経済構造の変化があります。インフレは企業の売上や利益を押し上げ、結果として株価上昇の強力な原動力となっているのです。今後も、この名目GDPと実質GDPの乖離、そしてインフレの動向が、個人の家計と株式市場の行方を理解する上で重要な視点となるでしょう。
参考文献
- 藤代宏一 (著). 『株高不況: 株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』. 講談社現代新書.
- Yahoo!ニュース (元記事). 「10月27日、日経平均株価は「史上初めて」5万円を超えた」.
https://news.yahoo.co.jp/articles/e2b4ea162e5165c241ace7ba3d5391e8ed913179 - 第一生命経済研究所 (機関).