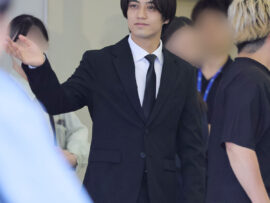近年、日本において弁護士や裁判官を志す若者の数が著しく減少しており、これは将来の日本の司法制度の根幹を揺るがしかねない深刻な問題として浮上しています。東京大学名誉教授の内田貴氏は、この現状について、「旧司法試験時代には多くの優れた人材が法曹資格を目指して集まったが、新司法試験制度は致命的な欠陥を抱えており、優秀な人材が進路選択の対象から法曹を外しつつある」と警鐘を鳴らしています。この法曹志望者の激減は、単なる人気の低迷にとどまらず、将来的に日本の司法を担う人材の質の低下に直結する可能性を秘めています。
 日本の法曹界が直面する課題をイメージさせる写真
日本の法曹界が直面する課題をイメージさせる写真
かつての人気職から一転、法学部の凋落と法曹志望者の減少
明治時代から約一世紀にわたり、日本の文科系エリート層はこぞって法学部を目指し、大学入試の偏差値においても法学部が常にトップを占める時代が続きました。しかし、バブル経済崩壊後の1990年代を境に、この傾向は大きく変化し、法学部の人気は次第に凋落の一途を辿ります。現代社会において、すべての優秀な若者が法学部を目指す必要がないのは当然ですが、司法試験の志望者数減少は看過できない事態です。
その理由は、ある分野における人材の質は、それを志す人々の潜在的な数の大きさに大きく依存するからです。例えば、多くの少年少女がサッカー選手に憧れて練習すれば、やがてプロサッカー選手の質は向上します。これとは逆に、その数が減少すれば、プロの質も低下するでしょう。同様に、司法試験を受けて弁護士、裁判官、検察官といった「実務法曹」を志望する人の数が減ることは、将来の法曹全体の質の低下を招く可能性が高いのです。これは、日本の司法制度を支える人材の質が低下するという意味で、極めて深刻な問題と言わざるを得ません。
司法制度改革の誤算:法科大学院制度が招いた「多様性」の欠如
さらに問題なのは、このような実務法曹志望者の減少が、むしろ優秀な法曹の数を増やそうとした政府の政策の失敗によって引き起こされた可能性が高いという事実です。2000年代初頭に大規模な司法制度改革が実施され、刑事裁判における裁判員制度の導入などが行われました。この改革の目玉政策の一つとして、2004年には「法科大学院制度(ロースクール)」が導入されました。司法試験を受験するためには、この大学院レベルの法科大学院を修了することが必須要件とされたのです。これは、アメリカのロースクール制度を範としていますが、日本独自の事情と相まって、意図せぬ結果を招きました。
アメリカの大学には法学部が存在せず、学生は様々な分野を専攻して多様な専門性を身につけた上でロースクールに進学します。このため、アメリカの法律家は、法学以外の分野で博士号を持つ者も珍しくなく、例えば理科系の専門知識を持つ法律家は科学関連の法問題で、経済学やビジネススクールの学位を持つ法律家はビジネス関連の法問題で高度な専門知識を発揮します。歴史学や哲学の博士号を持つ法律家は、法制史や法哲学の研究において深みのある議論を展開できるのです。
しかし、日本の法科大学院制度は、従来の法学部を残した上に、司法試験を依然として最難関の国家試験として維持しました。その結果、他分野から法科大学院に入学した人々は、学部時代から一貫して法律を勉強してきた法学部出身者と司法試験で競争せざるを得なくなりました。必然的に、法律のみを専門に学んできた者が勝ち残る傾向が生まれ、多様なバックグラウンドを持つ人材が法曹界に参入しにくい構造が固定化されてしまったのです。
結び:日本の司法制度の未来と多様な人材確保の重要性
日本の法曹界が直面する弁護士や裁判官の激減は、単なる職種の人気低迷ではなく、将来の司法制度の質を脅かす構造的な問題です。特に、新司法試験と法科大学院制度が、アメリカのような多様な専門性を持つ人材を法曹界に呼び込むという本来の目的を果たせず、むしろ門戸を狭めてしまっている現状は深刻です。日本の司法制度が社会の変化に対応し、公正かつ質の高いサービスを提供し続けるためには、優秀な人材の確保が不可欠です。そのためには、法曹への道を志す人々の数を増やし、同時に多様な専門知識と経験を持つ人材が法曹界に参入しやすい環境を整備することが、喫緊の課題と言えるでしょう。
参考資料
- 内田貴編著『弁護士不足』(ちくま新書)
- Yahoo!ニュース (PRESIDENT Online掲載記事より一部再編集)