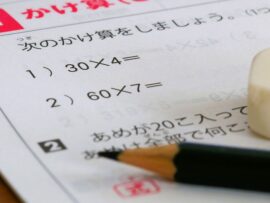「令和の米騒動」は一過性の出来事ではない。緊縮財政のもと農業予算が削減され続けてきた農政の末路である。東京大学大学院特任教授(食の安全保障)の鈴木宣弘さんは 『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』 (文春新書)で分析する。いまこそ「農業にこそ積極財政」を。「財政の壁」を超えられるかどうかが、日本の未来を左右しそうだ。 果たして高市新政権下で日本の食をめぐる政策は良い方向に向かうのか? 「おこめ券」配布の是非は?
「財政の壁」を乗り越える 今こそ「農業にこそ積極財政」を
高市新総理は以前から「食料自給率100%を目指す」と宣言していた。すぐに達成できるかと言えば実現性の乏しい目標ではあるが、その方向性と意欲は賛同できる。令和の米騒動で多くの人が実感したように、食の安全保障は命に関わる一大事だからだ。
また、「積極財政」を掲げていることも評価される。緊縮財政のもと、米国からの要請に対応した多大な支出を埋め合わせるために、農業予算は長らく歳出削減の標的にされてきた。今度こそ、「農業にこそ積極財政」を実現できるか。まさに正念場だろう。自民党の「積極財政議員連盟」リーダーの城内実議員が引き続き入閣されているのも期待したいところだ。
植物工場で食料自給率向上?
しかし、どうやって食料自給率を上げていくのか具体的な方策について問われ、総理から第一に挙げられるのは植物工場だ。これでは、現場の実態をよく把握しているとは言い難い。
屋内で生育環境を人工的に制御しながら野菜などを栽培する植物工場は、初期投資もランニングコスト(特にエネルギーコスト)も高く、採算ベースに乗っているものはベビーリーフ(葉丈10〜15cm程度で収穫した幼葉の総称)などかなり少ない事例だと関係者は口を揃えて言う。土壌からの微量栄養素に欠けるという問題はさておいても、植物工場で食料自給率が大幅に向上できるという発想は現実離れしている。
しかも、外国のお客様に饗するのは自国の自慢料理が当然なのに、訪日したトランプ大統領に米国産米と米国産牛肉を出すのはおもてなしではない。日本の国産米と和牛のレベルの高さを実感してもらうのが自給率向上の観点からも当然ではないか。