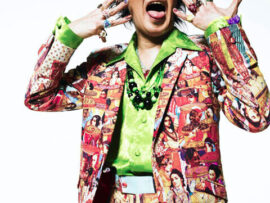戦後80年という節目を迎える今、「あの戦争」をどのように捉え、何と呼ぶべきかという問いは、専門家の間でも依然として活発な議論の対象となっています。多岐にわたる呼称が存在する中で、近現代史研究者たちは、その「答え」を探し続けています。本稿では、戦争の名称に込められた政府の意図と、満洲事変を起点とする「15年戦争史観」に焦点を当て、歴史認識の複雑性を深く掘り下げていきます。単なる呼称の問題に留まらず、それが示す歴史の実態と、現代日本が未来を考える上での重要性を探ります。
政府の意図が隠された戦争の呼称:実態と形式の乖離
歴史を正しく理解するためには、形式的な呼称に囚われることなく、その裏にある実態を見極める洞察力が必要です。この原則は、現代の国際情勢を鑑みても明らかです。例えば、2022年2月にウクライナへ侵攻したロシアは、その軍事行動を「特別軍事作戦」と呼び、公式には「戦争」であることを認めていません。この呼称に対する固執は、ロシア国内の政治的状況と深く結びついており、その背景を理解することは、ロシアという国家の内情を把握する上で極めて重要です。しかし、この事実が、私たちにロシアの主張を尊重し、「これは戦争ではない」と考えることを強いるものではありません。広大な戦域で無数の人々が犠牲になっている実態を踏まえれば、それが戦争であることは明白であり、そう断言することに何ら支障はないはずです。
同様の構図は、かつての日本にも見られました。日本政府が日中戦争を「支那事変」と呼称した背景には、明確な外交的・政治的な意図が存在しました。この意図を読み解くことは、当時の日本の国際的立場や国内情勢を理解する上で欠かせない要素です。しかし、呼称にこだわり過ぎて、戦争がもたらした悲惨な実態、すなわち数百万人以上もの兵士が動員され、広大な地域で繰り広げられた大規模な武力衝突という事実を見失っては本末転倒です。日中戦争は、その規模と影響から見ても、歴史的事実として「戦争」とみなすことが妥当であり、むしろ不可避であると言えるでしょう。
 戦後80年を迎える日本の歴史を考えるイメージ
戦後80年を迎える日本の歴史を考えるイメージ
「15年戦争史観」:満洲事変を起点とする連続した戦い
それでは、「あの戦争」の起点は、一般的に言われる1937年7月7日の盧溝橋事件なのでしょうか。いや、もっと過去に遡って考えるべきだという意見も、長年にわたり根強く存在します。それが、満洲事変こそが日中間の武力衝突の発端であるとする立場です。満洲事変は、1931年9月18日、奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖で関東軍が引き起こした鉄道爆破事件に端を発します。関東軍はこれを中国側の仕業と主張し、自衛を名目として軍事行動を開始しました。その結果、現在の中国東北部に傀儡国家である満洲国が建国されるに至ります。
満洲は、日露戦争後に日本がロシアから鉄道やその附属地などを獲得した地域であり、当時日本領であった朝鮮半島と隣接し、ソ連との国境にも接する、戦略的に極めて重要な拠点でした。加えて、石炭や鉄鉱石といった豊富な資源の供給源としても高い価値を持ち、日本にとって軍事・経済の両面で不可欠な場所と考えられていたのです。そのため、日本軍は満洲国を確保した後も、中国との国境地帯にあたる華北を自国の影響下におこうとする「華北分離工作」を推し進めました。これは、いわば第二、第三の満洲国を作り、満洲国の防衛線を広げようとする試みでした。この一連の動きが、中国側のナショナリズムを強く刺激し、日中戦争が局地的な軍事衝突に留まらず、やがて全面戦争へと発展する遠因ともなったのです。
こうした歴史的背景を踏まえて、満洲事変を「あの戦争」の起点として捉える歴史観を「15年戦争史観」と呼びます(実質的には14年に満たないものの、足掛け15年と見なされます)。この歴史観は、満洲事変、日中戦争、そして大東亜戦争という三つの出来事を、日本が大陸侵略を一貫して計画的に進めてきた結果として必然的に結びついた連続した戦争と捉えるものです。そのため、この史観は一般的に左派的な歴史観とされることが多いですが、一方で教科書や一般書を通じて広く浸透している考え方でもあります。
上皇陛下のご発言に見る歴史観の浸透
この「15年戦争史観」の普及の度合いを象徴する出来事として、平成の天皇(現・上皇陛下)が2015年1月、戦後70年の節目に発せられたご発言が挙げられます。陛下は「本年は終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々、広島、長崎の原爆、東京を始めとする各都市の爆撃などにより亡くなった人々の数は誠に多いものでした。この機会に、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今、極めて大切なことだと思っています」と述べられました。このご発言は、満洲事変を起点とする戦争の歴史を深く学ぶことの重要性を国民に訴えるものであり、まさに「15年戦争史観」が社会全体に広く浸透していることを示すものと言えるでしょう。
まとめ:歴史の教訓を未来へ繋ぐために
戦後80年を迎え、私たちは「あの戦争」の呼称が持つ政治的・歴史的意味合い、そしてそれが示す歴史の実態について深く考察する必要があります。ロシアによる「特別軍事作戦」や日本がかつて用いた「支那事変」といった呼称が、時の政府の意図を反映している一方で、歴史家たちは常にその実態を見極め、真の姿を明らかにしようと努めてきました。特に、満洲事変を起点とする「15年戦争史観」は、単一の出来事として戦争を捉えるのではなく、一連の連続した侵略行為としてその歴史的背景を深く理解することを促します。
上皇陛下のご発言が示すように、この歴史観は学術界に留まらず、広く社会に受け入れられています。過去の戦争の教訓を未来に活かすためには、多角的な視点から歴史を学び、その複雑さを認識することが不可欠です。私たちは、これからも「あの戦争」が何だったのかを問い続け、そこから得られる知見を、平和な国際社会の実現と日本のあり方を考える上で重要な指針としなければなりません。
参考文献:
- 辻田真佐憲, 『「あの戦争」は何だったのか』, 講談社, 2025年.
- Yahoo!ニュース, 「戦後80年を迎え…“あの戦争”をなんと呼ぶのか?専門家の間で議論が分かれる中、近現代史研究者が導き出した「答え」とは」, 2025年11月12日掲載.
https://news.yahoo.co.jp/articles/0bc1c884803761eeb5ac945c1f201840cdfe22bc