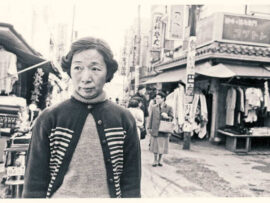NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉八雲の妻をモデルにしたトキ(髙石あかり)の奮闘を通じて、明治時代の異文化交流を描いています。特に注目を集めたのは、八雲をモデルとするヘブン(トミー・バストウ)が求める「ビア」を巡るエピソード。ドラマではトキが「ビア」が何か分からず奔走する姿がコミカルに描かれましたが、果たして史実はどうだったのでしょうか。この記事では、ドラマの創作と史実の狭間にある興味深い「ビール」の物語と、異文化コミュニケーションに苦悩する八雲の姿を深掘りします。
「ビア」を知らないトキは創作?明治時代のビール事情
ドラマ「ばけばけ」の第36回では、ヘブンが「ビアを買っておいて」と頼むものの、トキをはじめ誰もが「ビア」が何を指すのか分からず、琵琶やヒエなどを準備してしまうシーンが描かれ、多くの視聴者を笑わせました。しかし、実際のところ、明治時代には「ビール」は既に日本で広く知られたアルコール飲料となっていました。
ビールは幕末の開港直後から輸入が始まり、その人気はすぐに偽物が出回るほどでした。明治10年代には国産ビールの製造も本格化し、牛鍋屋や西洋料理店では定番のメニューとなります。樽売りのビールが主流だったこの時代、明治20年代までにはコップ売りの店が急増し、庶民にも手が届く存在になっていました。1891年に編纂された国語辞典『言海』にも「ビイル」という項目があり、「バクシュ。ビヤ」といった別称も記されていたことからも、その普及度がうかがえます。
したがって、トキが「ビア」という言葉に全くピンとこないという描写は、ドラマを面白くするための創作であると言えるでしょう。
小泉八雲も愛飲した「アサヒビール」と松江の薬店
では、小泉八雲自身はビールを飲んでいたのでしょうか。八雲と妻セツの結婚後に雇われた女中、高木八百の証言には、八雲が毎晩アサヒビールを愛飲していたことが残されています。
「先生は夕食後には必ずアサヒビールを2本ずつ飲まれました。そのビールは当時松江大橋詰の山口卯兵衛薬店だけにあったかと思います。始終アサヒビール何ダースかを買い置きまして毎晩差し上げました。」
この史実が、ドラマの細部にまで反映されている点には驚かされます。第37回で、ビアが分からず困り果てたトキが錦織(吉沢亮)に教えられ駆け込むのが、松江で唯一の舶来品店「山橋薬舗」です。これは、史実の「橘泉堂山口卯兵衛商店」、すなわち八雲がビールを購入していた薬局をモデルにしています。
ちなみに、この橘泉堂山口卯兵衛商店は現在も営業を続けており、店内には「まちかど博物館」が設けられています。現在は「山口薬局とビールとヘルンさん」をテーマに展示が行われており、当時の文化や八雲の生活に触れることができます。
 NHKドラマ・ガイド『連続テレビ小説 ばけばけ Part1』の書籍表紙
NHKドラマ・ガイド『連続テレビ小説 ばけばけ Part1』の書籍表紙
ヘブンの気難しさとトキの奮闘:文化と言葉の壁
「ばけばけ」では、ビールの一件だけでなく、ヘブン(八雲)の気難しさも描かれています。常に不機嫌で「ジゴク‼ ジゴク‼」と怒り、魚の骨が取り切れていないことや、糸こんにゃくが出されたことにまで腹を立てる姿は、異文化に適応しようとしながらも、言葉や習慣の違いに苛立つ八雲の複雑な心情を表しているのかもしれません。ついにはトキに「クビ」と言い放つほどでしたが、それでもめげずに八雲を支えようとするトキの姿は、当時の異文化間のコミュニケーションの困難さと、それを乗り越えようとする人々の努力を象徴しています。
演じるトミー・バストウの、言いたいことが伝わらない不快感を表現する演技は、まさに異国の地で暮らす人々の苦悩をリアルに伝えています。
まとめ
NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の「ビール」を巡るエピソードは、ドラマとしての面白さと、小泉八雲と妻セツを取り巻く明治時代の文化・史実が巧みに融合していることを示しています。ビールが既に普及していたという史実と、それを知らないというドラマの創作は、視聴者に歴史的背景への興味を掻き立てると同時に、異文化間での「当たり前」の違いを浮き彫りにします。八雲の気難しさとトキのひたむきな努力は、言葉や習慣の壁を乗り越えることの難しさ、そしてその先にある理解と受容の重要性を教えてくれるでしょう。