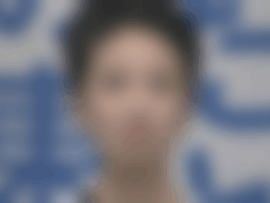帝国データバンクの調査によると、2025年7月の飲食料品値上げは前年比5倍の2105品目に達しました。年間では1万8697品目となり、前年通年の実績を大幅に上回るペースで推移しており、物価上昇は収まる気配を見せず、家計を圧迫しています。こうした物価高の時代において、家計防衛策として改めて注目されるのが「貯蓄」です。
本記事では、総務省統計局の最新データをもとに、日本の勤労者世帯の貯蓄額の現状、特に平均と中央値に焦点を当て、その実態に迫ります。
勤労者世帯の貯蓄額 平均・中央値データ
総務省統計局が発表した「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果-(二人以上の世帯)貯蓄の状況」によると、日本の勤労者世帯の貯蓄額は以下の通りです。
- 平均値: 1579万円
- 貯蓄保有世帯の中央値: 947万円
- 貯蓄現在高が「0」の世帯を含めた中央値: 885万円(参考値)
※家計調査における「勤労者世帯」は、世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯を指します。ただし、世帯主が社長、取締役、理事など会社団体の役員である世帯は別の分類となります。
勤労者世帯の貯蓄額の平均値は1579万円と1000万円を超えていますが、中央値は貯蓄ゼロを含めても885万円となっています。これは、一部の高額貯蓄世帯が平均値を引き上げていることを示唆しています。
実際の貯蓄分布を見ると、貯蓄現在高が「100万円未満」という家庭も11.1%存在しており、勤労者世帯内でも貯蓄状況には大きなばらつきがあることがわかります。若い世代や、教育費・住宅ローンなどライフイベントに伴う負担が大きい年代では、貯蓄額が相対的に低くなる傾向があると考えられます。
 日本の勤労者世帯 貯蓄額の金額別割合を示すグラフ
日本の勤労者世帯 貯蓄額の金額別割合を示すグラフ
貯蓄4000万円以上の勤労者世帯 世帯年収は?
かつて「老後2000万円問題」が議論を呼びましたが、継続する物価高を背景に、将来への不安から、老後資金にはその倍の4000万円程度が必要ではないかと考える方もいるようです。では、こうした「貯蓄4000万円以上」を保有する世帯は、どの程度の世帯年収があるのでしょうか。総務省統計局「家計調査 貯蓄・負債編 第8-11表<貯蓄・負債>貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯・勤労者世帯)」のデータを見てみましょう。
まず、二人以上世帯全体で貯蓄4000万円以上の世帯に絞ると、世帯年収は平均791万円です。
次に、本記事で焦点を当てている勤労者世帯のうち、貯蓄4000万円以上の世帯に限定すると、世帯年収は平均1087万円となりました。
このデータから、貯蓄額が4000万円を超える世帯、特に勤労者世帯においては、世帯年収も平均で1000万円を超えており、高年収である傾向にあることがわかります。もちろん、年収が高ければ必ずしも貯蓄が多いわけではありませんが、高年収は計画的な貯蓄を達成するための有力な基盤となる可能性が高いと言えるでしょう。
本記事では、日本の勤労者世帯の貯蓄状況について、最新の統計データをもとに検証しました。平均貯蓄額は1579万円ですが、より実態に近い中央値は885万円であり、世帯間での貯蓄格差が示唆されました。また、貯蓄4000万円以上の世帯は、世帯年収も平均で1087万円と高く、年収と貯蓄額にある程度の相関関係が見られます。物価高が続く現状、将来に向けた貯蓄の重要性は増しています。自身の家計の状況を正確に把握し、計画的な貯蓄に取り組むことが、不確実な時代を乗り切るための鍵となるでしょう。
【参考】
- 帝国データバンク「7 月の飲食料品値上げ、2105 品目前年比 5 倍に大幅増加」
- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果-(二人以上の世帯)貯蓄の状況」
- 総務省統計局「家計調査 貯蓄・負債編 第8-11表<貯蓄・負債>貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高(二人以上の世帯・勤労者世帯)」