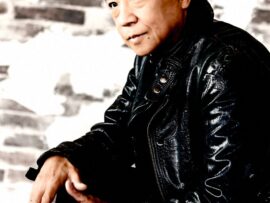2024年、兵庫県の斎藤元彦知事の「禊」とされた出直し選挙で、一躍注目を浴びたPR会社「merchu」代表の折田楓氏。彼女の選挙戦におけるSNS戦略とその公開を巡る一連の行動は、「プロの仕事ではない」という厳しい評価を招くこととなりました。特に、承認欲求や自己顕示欲が、広報という専門職においていかに問題を巻き起こしうるかを示唆する事例として、多くの議論を呼んでいます。ITジャーナリストの高橋暁子氏は、自身のコンサルタント経験に基づき、このケースから見えてくるプロフェッショナルとしてのあり方について警鐘を鳴らしています。
「キラキラ広報女子」と呼ばれた行動とその公開
問題の発端となったのは、折田氏が自身のnote記事で公表した『兵庫県知事選挙における戦略的広報』と題された記事です。この記事の中で、彼女は選挙期間中に自身が担当したSNS戦略の詳細を赤裸々に記しました。具体的には、斎藤氏への戦略説明資料、プロフィール写真の撮り直し、キャッチコピーやメインビジュアルの刷新、新たなSNSアカウントの立ち上げ、ハッシュタグ「#さいとう元知事がんばれ」とその変更経緯、さらにはポスター、チラシ、選挙公報、政策スライドなどの選挙資材制作、そしてX(旧Twitter)の本人アカウント及び公式応援アカウント、Instagram、YouTubeといった多岐にわたるSNS運用の全てにおいて、自身が中心的な役割を担ったことを強くアピールする内容でした。その緻密な戦略と実際の成果を詳細に綴った記事は、彼女の実績を示すものとして非常にインパクトのあるものでしたが、これが後に大きな波紋を広げることになります。
 「キラキラ広報女子」として兵庫県知事選挙のPR戦略を公開し問題となった折田楓氏のSNS画像
「キラキラ広報女子」として兵庫県知事選挙のPR戦略を公開し問題となった折田楓氏のSNS画像
なぜ問題となったのか?:公職選挙法違反とプロフェッショナル倫理
折田氏の記事が問題視された最大の理由は、それが選挙運動の対価としての報酬(買収)に当たるのではないかという公職選挙法違反の疑念を招いた点です。公職選挙法では、候補者が当選を目的に選挙運動の関係者に金銭を渡したり受け取ったりする行為を原則として禁じています。PR会社やコンサルタントが選挙に関わること自体は問題ありませんが、その具体的な内容や報酬を公にすることは、買収行為と見なされるリスクを伴います。
さらに、プロフェッショナルとしての倫理の観点からも重大な問題がありました。通常、選挙関連のコンサルティングやPR業務に携わった場合、その実績を外部に公開する際には、必ずクライアントである候補者側からの事前の確認と許可が必要です。これは広報やPRに限らず、多くの事業分野でクライアントとの信頼関係を維持するための基本原則です。クライアントが自社の利益や戦略上の理由からコンサルティングを受けている事実を公開しないと判断している場合、コンサルタント側が勝手に実績として公表することは、クライアントの意向を無視し、不利益をもたらす行為に他なりません。高橋氏は自身の経験を踏まえ、大手企業のSNSコンサルティング実績を公開しない理由として、企業側が公開しない以上、クライアントのメリットを最優先に考えるべきだと述べています。折田氏の場合、この基本的な確認プロセスを怠り、一切お構いなしに情報をオープンにしてしまったことが、クライアントである斎藤知事に思わぬ火の粉を浴びせる結果となりました。
動機と波紋
折田氏は自身の記事の中で、様々なメディアで「大手広告代理店が担当している」「都内のPRコンサルタントが手掛けている」「400人のSNS投稿スタッフがいた」といった憶測やデマが飛び交っていることに不満を感じ、自分が実際に手掛けたことを世間にアピールしておきたいという動機があったことを明かしています。承認欲求や自己顕示欲が、プロフェッショナルとしての判断を曇らせた可能性が指摘されています。結果として、彼女の行動は自身の評判を落としただけでなく、協力関係にあったクライアントにも法的な疑念や批判の目を向けさせるという、広報の目的とは真逆の事態を引き起こしました。
結論
兵庫県知事選挙における折田氏の一件は、PRやコンサルティング業務において、単に戦略を成功させるだけでなく、プロフェッショナルとしての倫理規範やクライアントとの信頼関係がいかに重要であるかを浮き彫りにしました。特に、成果を自身の承認欲求や自己顕示欲を満たすためのツールとして扱う姿勢は、プロフェッショナルな仕事とは根本的に相容れないものです。クライアントの利益を最優先に考え、情報の取り扱いに細心の注意を払うことこそが、真のプロフェッショナルに求められる資質と言えるでしょう。この事例は、情報が瞬時に拡散する現代社会において、広報担当者が負うべき責任の重さを改めて認識させる出来事となりました。
参考文献: