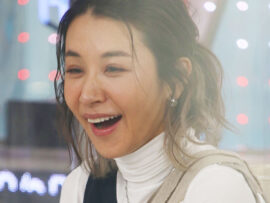霧島連山の新燃岳では、噴火活動が続いています。7月3日には一時、噴煙が火口上5000メートルに達し、鹿児島空港発着の空の便に影響が出たほか、霧島市などで降灰に見舞われました。こうした状況の中、7月7日には火山学の専門家が上空から火口などの様子を視察。「いつマグマ噴火に移行してもおかしくない」と改めて警戒を呼びかけています。
 霧島連山・新燃岳の火口を上空から撮影した写真。噴煙が立ち上り、活動の様子がうかがえる
霧島連山・新燃岳の火口を上空から撮影した写真。噴煙が立ち上り、活動の様子がうかがえる
火山活動の活発化を示す新たな兆候
7月7日に新燃岳の状況を上空から確認したのは、火山学や自然災害科学を専門とする鹿児島大学の井村隆介准教授です。連続噴火が始まった6月27日と比較して、火口列が増加していることを指摘しました。当初は北東方向に伸びていた割れ目火口に加え、この視察では新たに南東から南にかけての方向にも火口列が形成されていることが確認されたといいます。この現象について、井村准教授は「新燃岳の下にはまだまだポテンシャルを持っているものがある」と述べ、火山活動が一層活発化する可能性を示唆しています。新たな火口列の出現は、地下からのマグマ供給やガスの放出が活発になっていることの現れと考えられます。
警戒が必要な「火砕流」の発生
上空からの観察では、6日午後に発生した黒煙についても分析が行われました。井村准教授によると、これは南側の火口から発生した火砕流だったということです。井村准教授は「まだ本格的なマグマ噴火になっていないので、熱量が足りず、上に上がらなくて、密度の濃い噴煙が斜面を流れ下って火砕流になっている状況」だと説明しました。分析によれば、現時点での火砕流は、典型的なマグマ噴火に伴う大規模なものとは異なるものの、その温度は100℃から200℃に達する可能性があり、決して安全な状態ではありません。井村准教授は「そういう中にいると命を落とすことになる」と強く警告し、立ち入り規制区域はもちろん、その周辺地域においても十分な注意を払うよう重ねて呼びかけています。
マグマ噴火移行の可能性と求められる備え
新燃岳の初回噴火から約2週間が経過した時点での状況について、井村准教授は「水蒸気噴火だけなら、これだけ長くは続かず収まっていいはずだ」と指摘します。一方で、現状はマグマ噴火への移行の可能性が継続していると分析。「マグマが積極的に地表に出てくるような噴火に移行する可能性が続いており、それが迫ってきているというよりは、いつ起きてもおかしくない状況が続いていると考えたほうが良い」との見解を示しました。そして、井村准教授は「半歩前、一歩先の防災対策をしていったほうがいい」と強調。住民や関係機関に対し、不測の事態に備えた事前の準備を着実に進めることの重要性を促しています。
最新の活動状況と規制情報
井村准教授が上空から視察した7日の夕方、気象台は「連続噴火は停止したもよう」と発表しました。しかし、同日午後8時30分には再び噴火が観測され、その後も噴火活動は続いています(7月9日午後1時時点)。火山活動が依然として不安定な状態が続く新燃岳では、現在も噴火警戒レベル3の「入山規制」が維持されています。気象台は、火口からおおむね3キロメートルの範囲では大きな噴石に、おおむね2キロメートルの範囲では火砕流に、それぞれ引き続き厳重な警戒を呼びかけています。今後の火山情報の推移に注意が必要です。
鹿児島テレビ