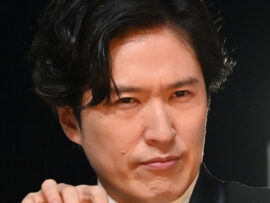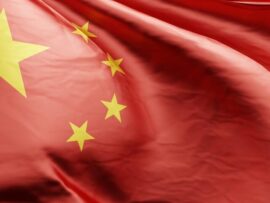「電動」の乗り物は、その快適さから多くの人々に利用されています。しかし、利便性の裏側には常に危険が潜んでおり、社会的な問題も発生しています。特に近年、電動キックボードや電動自転車の一種でありながら原付バイクに近い性能を持つ「モペット」が若者を中心に広まり、無免許運転や飲酒運転といった違法行為が問題視されています。元警察官の秋山博康氏も、こうした新たな電動モビリティがもたらす危険性に警鐘を鳴らしています。本稿では、電動キックボードとモペットを中心に、その普及の現状と潜む危険、そして法的な課題や安全対策について詳しく解説します。
電動キックボードの普及と潜む危険性
都市部、特に東京の街では電動キックボードを利用する若者を見かける機会が増えました。シェアリングサービスの拡充により、スマートフォン一つで手軽に借りられる便利な移動手段として、観光地でも注目されています。しかし、その利便性の陰で、電動キックボードに関連する事故や交通違反が急増しているのが現状です。
電動キックボードは、正式には「特定小型原動機付自転車」という車両区分に該当します。2023年7月に道路交通法が改正されたことにより、16歳以上であれば運転免許が不要となり、さらにヘルメットの着用が「努力義務」(可能な限り着用するよう努めるべきという任意規定)に変更されました。こうした法改正は電動キックボードの利用を急速に拡大させましたが、同時に摘発件数も激増させています。改正法が施行された2023年7月からの半年間で約7000件だった違反摘発件数は、翌年の同じ時期には約2万3000件と、実に3倍以上に跳ね上がったのです。
電動キックボードを含む自動車やバイクは、法律で「自賠責保険」への加入が義務付けられています(シェアリングサービスの場合は利用料に含まれていることがほとんどです)。もちろん、車両にはナンバープレートの装着も必要です。電動キックボードは原則として車道や自転車専用道を走行すべき車両ですが、中には歩道を猛スピードで走行する利用者も見られます。このような行為は極めて危険であり、万が一、小さな子どもと衝突した場合、命に関わる大事故につながる可能性があります。実際に、転倒して頭部を強く打ち、重傷を負った事例も報告されています。電動キックボードは免許不要とはいえ、信号や標識の確認を怠らず、交通ルールをしっかりと理解してから乗ることが強く求められます。
 元刑事が国民に伝える防犯対策図鑑の表紙または関連イラスト
元刑事が国民に伝える防犯対策図鑑の表紙または関連イラスト
繰り返される危険運転と厳しい罰則
残念ながら、電動キックボード利用者のヘルメット着用率は非常に低いのが現状です。警察庁のデータによれば、ヘルメットの着用率はわずか約4%にとどまっています。ヘルメット着用は努力義務ではありますが、自身の命を守るための重要な行為であるという認識を持つべきです。安全のためにも、積極的にヘルメットを着用することを強く推奨します。
特に危険な行為として挙げられるのが、スマートフォンなどを操作しながら運転する「ながら運転」です。また、イヤホンを使用しながら電動キックボードに乗ることも法律で禁止されています。そして、最も許容できない重大な違反が飲酒運転です。飲み会の後に「終電がなくなったから、電動キックボードで帰ろう」といった安易な考えは、立派な飲酒運転という犯罪行為です。飲酒運転を行った場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金といった厳しい罰則が科される可能性があります。
電動キックボードが関連する交通事故の割合は増加傾向にあり、2024年1月から6月までの統計では、事故全体の17.2%を占めており、自転車や原付バイクと比較しても高い割合となっています。飲酒運転による事故で負傷した場合、自賠責保険による治療費の補償は受けられません。つまり、事故による医療費などは全て自己負担となってしまうのです。

結論
電動キックボードやモペットといった新たな電動モビリティは、私たちの移動をより便利にする可能性を持っています。しかし、その手軽さゆえに、交通ルールの軽視や危険な運転が増加し、重大な事故につながるリスクも高まっています。免許不要やヘルメット努力義務といった規制緩和があったとしても、交通法規を遵守し、安全運転を心がける基本的な姿勢は何ら変わりません。飲酒運転、ながら運転、そしてヘルメット非着用といった危険行為は、自身だけでなく他者の命をも危険に晒す許されない行為です。これらの電動車両を利用する際は、その責任と危険性を十分に理解し、常に安全を最優先に行動することが、利用者全てに求められています。
参考文献
- 秋山博康 著『元刑事が国民全員に伝えたい シン・防犯対策図鑑』KADOKAWA, 2023年