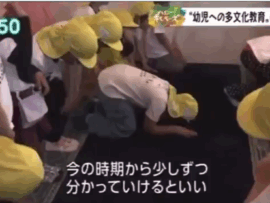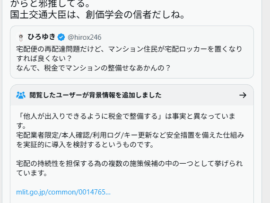近年、千葉県を中心に大繁殖し、生態系や農作物に甚大な影響を与えている特定外来生物「キョン」。そのギャアアという特徴的な鳴き声とともに、メディアでも頻繁に取り上げられるようになり、その存在は多くの日本人の知るところとなりました。しかし今、この「害獣」として駆除の対象となっていたキョンが、意外な形で注目を集めています。それは、その肉が「人気の食材」として流通し始めているという事実です。一見すると矛盾するこの現象の背景には、駆除される命を無駄にせず、新たな価値を生み出そうとする一人の猟師の熱い想いと、日本の抱える深刻な環境問題への具体的な取り組みがありました。
特定外来生物「キョン」の肉、意外な人気と課題
キョンの特性と現状、そして食肉への道
キョンは中国や台湾を原産地とするシカ科の動物で、中型犬ほどの大きさです。日本では特に伊豆半島や千葉県で大増殖し、希少な植物を食い荒らすなど、在来種の生態系に大きな影響を与えています。本来は駆除の対象であり、捕獲されたキョンが「ゴミ」として扱われることも少なくありませんでした。
[
特定外来生物として日本で大繁殖しているキョン。中型犬ほどの大きさで、ギャアアという特徴的な鳴き声を発する。](https://news.yahoo.co.jp/articles/0279ce4b4d42f356714ab533f4da59b9cb1c7aa6/images/000)
そんな中、キョンの肉の美味しさを世間に広め、その価値を再発見させたのが、千葉県君津市に拠点を置く「猟師工房」の代表である原田祐介氏です。食肉処理業の許可を持つ原田氏は、「我々と同じ生き物なのに、命を奪ったうえで“ゴミ”として捨てられてしまうのは心苦しい。供養のためにも」という強い思いから、約7年前からキョンの肉の販売を開始しました。中国や台湾では高級食材として扱われるキョンですが、日本ではその利用が進んでいませんでした。
労力と需要のギャップ、そして新たな展望
キョンは一頭あたりから得られる可食部が約2kgと非常に少なく、捕獲から処理までの労力を考えると「労多くして」な食材です。しかし、原田氏の努力が実を結び、最近では「人気になってしまって、入ってもすぐに売れてしまう」と原田氏は語ります。この人気は、駆除されるキョンの命を有効活用するという点では喜ばしいことですが、特定外来生物であるキョンが商品価値を持つことで、「駆除しなければならないのに安定供給を考えなければならなくなる」という複雑なジレンマも生んでいます。
この状況を受け、原田氏はキョンの肉の需要を掘り起こすことに一定の道筋をつけたと感じ、今後は「キョンのように駆除されて捨てられるだけだった中小型獣の肉の二次利用」に活動の軸を移そうと考えています。アライグマやハクビシン、タイワンリスなど、他の害獣の肉の活用にも目を向け、持続可能な循環型社会の構築を目指しているのです。
「猟師工房」の活動拠点と猟への同行
廃校を活用したユニークな拠点
原田氏の活動拠点である「猟師工房」は、廃校になった旧い小学校を利用しています。店内では、シカやイノシシの毛皮に触れることができ、シカの角を使ったキーホルダーなどのグッズや、解体処理された獣の肉が販売されています。この日は、原田氏の知人が長野県で捕獲したというツキノワグマの肉も販売されていました。かつての校庭だった芝敷きのスペースは、ドッグランやソロキャンプ場としても利用されており、地域に開かれたユニークな施設となっています。
効率的な罠猟の現場
原田氏は、猟銃ではなく主に罠を使った猟を行っています。かつてアパレル業界に身を置いていた彼が猟に出始めた頃は、銃を担いで複数人で山に入るレジャーハントが主流でした。しかし、猟師の高齢化による害獣の増加という社会問題に直面するうち、害獣捕獲の効率性を追求するようになり、現在の罠猟へとシフトしたと言います。
普段は朝6時頃から、仕掛けてある25ヶ所の「くくり罠」と2ヶ所の「箱罠」を見回るのが日課です。取材当日、私たちは原田氏とともに罠の設置場所へ向かいました。意外にも、その場所は山の奥深くではなく、交通量の多い道路沿いの林の中でした。
「ここはもともと有料道路だったんですよ。ちょっと路側帯が広いところがあるでしょう。そこに車を止めてゴミを捨てるドライバーがいるんです。酷いドライバーになると走りながら窓から投げ捨てる。何日かごとにゴミ拾いをするんですけど、そのゴミを漁りに獣がやって来るんです」と原田氏は説明します。山奥では光が十分に届かず、草や昆虫が少ないためエサも限られますが、道路沿いは光が入りやすく、草や昆虫も豊富で、さらに人間の捨てるゴミまでが獣の食料源になっているのです。原田氏は、道路からわずか数メートルの斜面など、獣道となっている場所に罠を仕掛けていました。
アニマルウェルフェアへの配慮と捕獲の現実
アニマルウェルフェア(動物福祉)の観点から、ギザギザの刃が付いた「トラバサミ」は使用が禁止されています。また、罠にかかった獣が苦しまないよう、仕掛けた罠は一日一回見回ることが義務付けられています。この日は複数の罠を見て回りましたが、このエリアでの収穫はありませんでした。
原田氏は、「獣はまず山間の田畑に出て来て、その後、町に出て来る。被害を出さないためには田畑に出て来る前に何とかしなくちゃいけないんです」と、捕獲の重要性を強調します。
[
千葉県の山林で、くくり罠にかかり動き回るメスのシカ。地域住民の農作物被害を食い止めるための捕獲活動の一環。](https://friday.kodansha.co.jp/article/432663/photo/23f814ee?utm_source=yahoonews&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerlink)
少し離れた場所、山村脇の林に設置された罠を確認しに行くと、メスのシカがくくり罠にかかっていました。畑と細い道を挟んですぐの林の中でした。シカは動き回り、もがいていました。「この近くの家庭菜園がシカに荒らされているって、近所の人から聞いていたんですよ。良かったです」と原田氏は安堵の表情を見せます。
原田氏が解体所に連絡すると、すぐに職員が到着。職員は抵抗するシカをものともせず、わずか2〜3秒で後ろ脚を束ね、首元を足で押さえながら小さなハンマーでシカの額をコツンと叩きました。シカは小さく「キューン」と鳴いて失神。職員は間髪入れずにナイフを鎖骨のあたりから心臓にスッと入れました。その一連の作業は、トータルで10秒もかからない迅速さでした。この日は、他に箱罠には何もかかっておらず、捕獲したのはこのシカ一頭のみでした。
害獣問題の全体像と「命の二次利用」の意義
命の授業と環境保全の重要性
「猟師工房」に戻り、改めて原田氏から話を聞きました。彼は、小学生や教職員を対象に「命の授業」を行っていると言います。「みんなが食べる給食にもお肉は入っているよね。生き物を殺めないと、お肉は食べられないよね」と語りかけ、子どもたちが「いただきます!」の意味を深く理解できるよう促しています。同時に、山で今何が起きているのか、なぜ害獣を捕獲しなければならないのかも伝えています。
害獣の増加は、農作物被害にとどまらず、山林の荒廃、獣道が深くえぐれることによる土砂災害のリスクを高めます。土砂が川に流れ込み、それが海に達すると、海水が濁り光合成を妨げ、アオモやサンゴといった海洋生態系にも悪影響を及ぼしかねません。キョンはシカと食性が重なるため、貴重な山の植物がさらに食べ尽くされ、生態系が崩壊する危機に瀕しているのです。
駆除後の利用率の低さと不法投棄の問題
日本全国では年間120~130万頭もの獣が駆除されています。これは農業被害の軽減や自然環境保護のため、やむを得ず行われている現実です。しかし、そのうちジビエや飼料として利用されるのはわずか10%程度に過ぎません。残りの多くは単に駆除されただけで、「ゴミ同然」に扱われています。
埋設が求められているにもかかわらず、実際には葉っぱなどをかけて隠すといった違法な遺棄が行われるケースも少なくありません。その死肉を食べて栄養を蓄える害獣も現れており、新たな問題を引き起こしています。原田氏は、「奪った生命を無駄にしないために、やはり二次利用が必要だと思う」と強く訴えます。
産業化を目指す未来への展望
原田氏の活動は、他の人々にも影響を与えています。「本心ではどう思っているかは分からないけど、“商売ではなく、その命を無駄にしないために……”とキョンの肉を売る新たな人間たちも出てきました。ある程度、道筋は作ったつもりです」と原田氏は語ります。
今後、彼はアライグマやハクビシン、タイワンリスなどの中小型獣に対しても、キョンと同様の「二次利用」のサイクルを確立しようと考えています。他の地域から肉を仕入れるルートも検討しつつ、まずは自身が捕獲した獣から取り組みを始める予定です。将来的に自前の解体設備が整えば、その可能性はさらに広がるでしょう。自然を守り、捕獲された害獣を無駄にせず、二次利用するサイクルを確立し、それが一つの産業として成り立っていくこと。それが原田氏の描く未来の姿です。
現在、「猟師工房」ではツキノワグマの肉を販売しており、「ツキノワグマ肉汁うどん」も提供されています(提供される肉や料理は時期によって変わります)。埼玉県出身の原田氏らしい、少し茶色がかった武蔵野うどん風の麺を、ツキノワグマの肉と一緒に柚子が香る醤油仕立てのつけ汁でいただくその味は、まさに絶品でした。有害鳥獣駆除という喫緊の課題に対し、単なる排除ではない「命の有効活用」という新たな価値創造で挑む猟師たちの取り組みは、日本の未来を考える上で重要な示唆を与えてくれるでしょう。
参考文献
https://news.yahoo.co.jp/articles/0279ce4b4d42f356714ab533f4da59b9cb1c7aa6