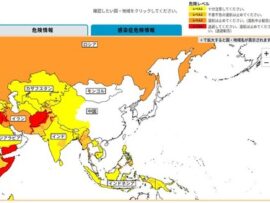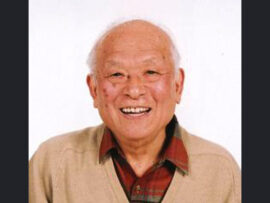いまだ収まらない物価高の波は、日本のエンターテイメントや伝統芸能の世界にも大きな影を落としています。例えば、今年10月に上演予定のミュージカル「エリザベート」では、平日のSS席が2万円(土日祝日、千秋楽は2万1000円)と、歌舞伎以外の演劇チケット代としては異例の2万円台を突破しました。そして、長らく「庶民の娯楽」として親しまれてきた落語の定席寄席も、この物価高の影響を避けられず、次々と木戸銭(入場料)の値上げに踏み切っています。
都内主要寄席で相次ぐ木戸銭値上げの現状
今年6月には、東京・上野の鈴本演芸場や浅草の浅草演芸ホールの木戸銭が500円アップし、3500円となることが発表され、大きな話題となりました。そしてこの8月には、同様に新宿末廣亭も3000円から3500円へと値上げを実施します。都内にある四つの落語定席のうち、池袋演芸場だけは辛うじて3000円に据え置いていますが、これにより主要な寄席のほとんどが値上げに踏み切る事態となりました。
 新宿末廣亭の入り口を照らす看板。物価高騰で木戸銭が値上げされた東京の老舗寄席
新宿末廣亭の入り口を照らす看板。物価高騰で木戸銭が値上げされた東京の老舗寄席
経営を圧迫する光熱費とコロナ禍の余波
寄席の運営を圧迫している要因の一つが、高騰する光熱費です。どの寄席も、昼の部は正午頃から16時過ぎまで、夜の部は17時頃から20時半頃までと、連日8時間を超える長時間にわたって営業しています。当然ながら、客の入りに関わらず、夏場は冷房、冬場は暖房をフル稼働させており、その電気料金は経営に重くのしかかっています。昨年同時期と比較して、今年の光熱費は1.5倍以上に増加しているといい、この異常な値上がりが寄席の経営を厳しくしています。
加えて、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが残した「後遺症」も深刻です。営業自粛を余儀なくされた寄席は、多くが「個人商店」と言えるような零細企業であり、一時は閉場の危機に瀕しました。落語協会と落語芸術協会は、寄席救済のためにクラウドファンディングを実施し、約1億円を集めて都内の寄席に分配することで、何とか危機的状況は脱しました。しかし、肝心の客足はコロナ禍前の水準には戻りきっておらず、厳しい経営状況が続いているのが実情です。
芸人の出演料維持が値上げの背景に
連日、寄席には落語家をはじめ、漫才師、講談師、奇術師、曲芸師など、30人近い芸人が出演します。彼らに支払われる出演料は、その日の観客数、つまり売り上げに左右される仕組みです。さらに、芸人たちには芸歴などによる「格」があり、それに基づいた「割り」と呼ばれる分配方法でギャラが決定されます。
しかし、どの寄席も客席数は満員になったとしても300人程度と限られています。そのため、芸人に支払われるギャラの額も決して多くはありません。全国的な知名度を持つ人気落語家でさえ、1回の出演料は1万円ほどで、若手になると数千円という世界です。ただでさえ少ない芸人への支払いを維持しようとすれば、原資となる入場料を上げるしか選択肢がないのが現状なのです。
寄席側の努力:多様な割引制度の導入
このような厳しい状況下でも、寄席側は入場料を値上げする一方で、少しでも多くの客に足を運んでもらおうと、さまざまな割引制度を工夫して導入しています。従来の学生割引に加え、コアなファンが多い65歳以上の高齢者を対象としたシニア割引も用意されています。さらに、18時以降に入場する場合や、公演途中の休憩(中入り)後に入場する際には、夜間割引が適用されるなど、多様な選択肢を提供することで、来場を促す努力が続けられています。
物価高が生活を圧迫する中、日本の伝統芸能であり「庶民の娯楽」である寄席が直面している経営課題は多岐にわたります。光熱費の高騰、コロナ禍からの客足の回復の遅れ、そして出演する芸人たちの生活を支えるための出演料維持。これらの複合的な要因が、木戸銭の値上げという形で現れています。割引制度などの工夫を凝らしつつも、伝統文化の灯を守るための厳しい戦いが続いています。
参考資料
- 「週刊新潮」2025年7月31日号 掲載 新潮社
- Source link: https://news.yahoo.co.jp/articles/66599fb671b18a13a325a24f7929917dc7398f0c